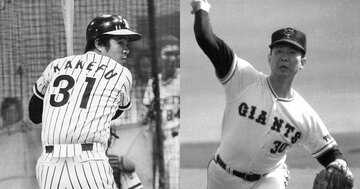1959年に読売をうちまかす。その前から御堂筋行進を夢想していたという。選手だけではなく球団側も、そうちかい、また夢見てきた。いつかは、あそこでやりたい、と。いったい、南海にとって御堂筋は、どのような意味をもっていたのか。
こう書けば、たいていの人は、つぎのように言いかえすだろう。あそこは、大阪を代表する目抜き通りである。ニューヨークの5番街やパリのシャンゼリゼ通りに、市中でのポジションは匹敵する。御堂筋で自らの成功をいわいたがる人たちがいることじたいに、不可解な点はない、と。
たしかに、そのとおりである。そう語ることで議論をまとめても、問題はないのかもしれない。しかし、私はもうひとつべつの理由もあったと、思っている。
球団の夢は叶ったけれど
電鉄の夢は絶たれた南海
南海電鉄は大阪の難波と、その南側をむすぶ私鉄である。大阪府の南部と和歌山県の北部に、その路線はひろがる。南海難波駅は、その最北端にある終点である。これより北側に、同電鉄の路線はない。
また、難波駅には複数の路線が、あつまっている。南海本線と高野線、そして泉北高速鉄道を走る便が、ここから始発する。そのたたずまいは、どこかヨーロッパの終着駅をしのばせなくもない。じっさい、この駅はターミナル駅であると、地元でも言われている。
しかし、より北のほうへと路線をのばす意欲を、南海電鉄がもたなかったわけではない。難波は大阪でミナミとよばれるエリアの、その南側に位置している。これをキタと通称される地域の梅田までとどかせたい。そうすれば、ミナミからキタへといたるドル箱路線がきりひらける。そんな野望を、潜在的には秘めていた。
これをはばんだのは大阪市である。同市は1901年以後、市内交通に関する大方針をうちだした。市中の交通手段は、すべて市営にするという決定をくだしたのである。おかげで、民営鉄道のみならず国営鉄道も、旧市街へははいれなくなった。
この市営優先という考え方を、大阪市のモンロー主義とよぶことがある。モンロー主義は、アメリカ合衆国の孤立主義を意味する用語である。