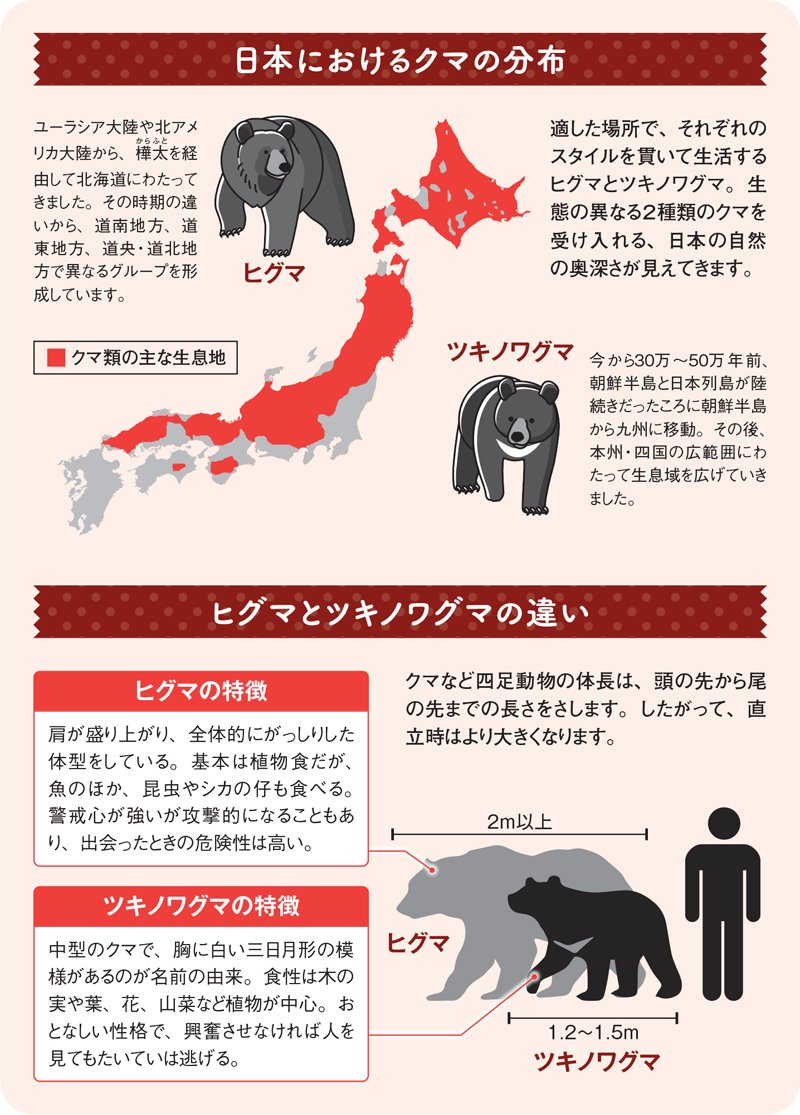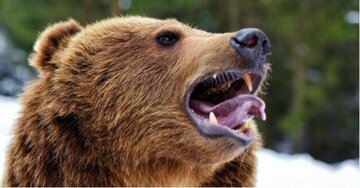両者は性格も異なります。人の気配を感じると身を隠すほど警戒心が強い半面、追いつめられると非常に攻撃的になるヒグマに比べ、ツキノワグマは臆病で人との接触をなるべく避ける慎重な性格をしています。
ともに雑食性ながら、サケを捕まえ、昆虫なども口にするヒグマはややガッツリタイプ。一方、木の実や果実がメインのツキノワグマは草食タイプと、食事の好みも異なります。狭い国土をうまくすみ分けられる理由も、こうした性質の違いにあるのかもしれません。
クマの一生は基本的に“ひとりぼっち”
親に甘えられるのは2歳まで
クマは一生の大半を“ひとりぼっち”で過ごす動物です。多くの哺乳類が群れや家族単位で行動するのに対し、子グマ時代を除いて基本的に単独で生活します。
オスもメスも関係ありません。クマはそれぞれ自分の生活場所を持ち、エサを探したり眠ったり、あるいは危険に対処したりといった毎日の行動すべてを自らの力だけでこなしています。オスとメスが顔を合わせるのも繁殖期のわずかな間だけ。交尾が終われば、それぞれすぐにもとの生活へと戻っていきます。
メスは冬に巣穴で出産すると、春先には小さな子グマと一緒に活動をはじめます。この子育て期間も1年半から長くて2年半ほど。子グマを自立させると再びひとりぼっちに戻ります。ちなみに、オスは子育てにまったく関わりません。
一見して孤独に思えても、自然界では群れないことが生きやすさにつながる場面が多くありるものです。たとえば、クマは巨体を維持するため大量の食べ物を必要としますが、単独で行動することでエサの奪い合いを避けられます。ほかにも、自分のペースで活動できるといった利点もあります。つまり、クマにしてみれば合理的な生活スタイルを貫いているだけなのです。それは厳しい自然を生き抜くため、彼らが身につけた知恵といえるでしょう。