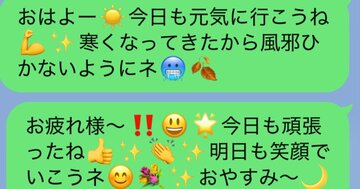写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
スマートフォンでQRコードを読み取ったり、テーブルに据え付けられたタブレットでオーダーをする飲食店が増えている。人件費高騰の折、店員がいなくても注文できるこの仕組みを採用する飲食店が増えている事情はわかるが、「飲み屋のスマホ注文やタブレット注文が嫌だ」という人が一定数いる。いったい、何がイヤなのか?(ライター、編集者 稲田豊史)
スマホ注文の何が嫌なのか
飲み屋のスマホ注文やタブレット注文が嫌だ、という人が一定数いる。
広範囲に統計を取ったわけではない。あくまで筆者(51歳・文筆業)周辺に限った話だが、結構多い印象だ。口に出して言わなくとも、初めて入った店がスマホ注文だとわかった瞬間に「あ……」と無意識に顔が曇る人もいる。
ちなみに、筆者くらいの世代で「注文方法がよくわからないから嫌だ」という人は、ほとんどいない。スマホは使い慣れているし、「電子機器に不慣れなシニア」とは違う。ITにことさら疎いわけではない。
では、スマホ注文の何が嫌なのか。
嫌な理由としてよく聞くのは、工数の多さだ。店員への注文なら一言で済むところ、スマホやタブレットだとそうはいかない。
特にスマホの場合、最初にQRコードを読み取るだの、初めての店ではLINEの友だち登録だのという作業が必要になることもある。いざ注文となると、「飲み物」「焼き物」「揚げ物」「おすすめ」といったカテゴリをタップし、スクロールして目当てのものを探し、数を指定し、カートに入れて、注文。大きな紙のメニューに比べて一覧性が低いため、目当てのものを探しづらいという不満も根強い。
しかも、工数の多い作業は「流れ」をぶった切る。