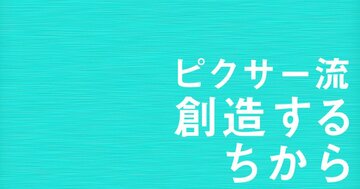独創的なアニメーションを次々ヒットさせ、世界随一のクリエイティブな企業としても多くの人が憧れる、ピクサー・アニメーション・スタジオ。その共同創業者であるエド・キャットムル氏の著書『ピクサー流 創造するちから』より一部を紹介する。今回は、ルーカス・スタジオがエドの率いていたコンピュータ部門を売却することになり、買収相手がなかなか見つからずに万策尽きたかと思えたその時、エドの前に現れたスティーブ・ジョブズの第一印象を語る。

1983年、ジョージ・ルーカスはマーシャと離婚し、その慰謝料の支払いがルーカスフィルムのキャッシュフローに重大な影響を与えた。ジョージ自身は、その野心を露たりとも失っていなかったが、新たな財務的現実を前に、事業を合理化せざるを得なかった。
同時期に、私は、何よりも長編アニメーション映画をつくりたかった我々コンピュータ部門の夢に、ジョージが共感していないことに気づき始めていた。彼はコンピュータには非常に興味を持っていたが、あくまで実写映画の向上に利用するためだった。目指すところは違ったが、一時的には、重なる部分もあった目標を互いに推し進めることもできた。だが、投資の集約を迫られた今、ジョージは我々を売却することにした。
コンピュータ部門の第一の資産は、ピクサー・イメージ・コンピュータを軸に築いたビジネスだった。もともとは映画のフレーム処理のために開発したものだったが、医療用画像やデザイン・設計の試作、連邦政府の情報機関向けの画像処理など、複数の用途に実績があった。
翌年は、私の人生の中で最もストレスの多い一年になった。
ジョージがルーカスフィルムの再編のために呼び入れたマネジメントチームの興味はおもにキャッシュフローに向いており、時が経つにつれ、コンピュータ部門には永遠に買い手がつかないのではないかとおおっぴらに疑問を持ち始めるようになった。このチームのリーダーは二人ともファーストネームが同じで、私とアルヴィは、我々のビジネスについて何一つわかっていなかったこの二人を「ダサいやつら」と呼んでいた。二人はコンサルタンティング用語をやたらと振りかざした(「会社としてのインサイト」を押し売りし、しょっちゅう「戦略的アライアンス」を組むよう迫った)が、コンピュータ部門を誰にどうやって売り込むかについては、まったくアイデアがないように見えた。
あるとき、部屋に呼ばれていくと、椅子に座らされ、部門が買収されるまでの間、コストカットのために社員を一時解雇すべきだと告げられた。買収後に再雇用を相談すればいい、と。我々がこの提案を気に入らなかった理由は、精神的ダメージが確実に生じるだけでなく、ここに集めた人材こそが、我々の本当の「売り」だったからだ。今までアプローチしてきた相手が興味を示したのも、この点だった。それを取ったら何も残らない。
そのため、考え方が瓜二つの絶対君主たちに、レイオフ対象者のリストアップを命じられた私とアルヴィは、二人の名前を提示した。つまり私と彼だ。そのおかげで計画は一時的に保留となったが、1985年が明けるころには、早期に売却が実現しなければ、部門がいつ閉鎖されてもおかしくない状況にあることにはっきりと気づかされた。
ルーカスフィルムは、現金1500万ドルで売ってケリをつけたかったのだが、それには問題があった。コンピュータ部門の事業計画は、この部門が試作から製品になり、自立するためにあと1500万ドルを要する、としていた。これは、買収先として見込んでいたベンチャーキャピタリストたちには受け入れ難い条件だった。企業を買収する際にそのような多額の現金に関する約束は、普通しないからだ。20の相手に話を持ちかけたが、どこも食いつかなかった。そのリストが尽きると、メーカー数社が「品質チェック」に訪れたが、やはりだめだった。
ようやく最後に、ゼネラルモーターズ(GM)とフィリップスとの合意にたどり着いた。フィリップスの目当ては、我々がピクサー・イメージ・コンピュータで開発した、膨大なデータをレンダリングするための基礎技術をCTスキャンやMRIなどのデータに活用することだった。GMは、物体のモデリングにおける先行技術を自動車の設計に活用できると考えていた。だが、あと1週間で契約締結という段階で頓挫した。
このとき失望とともに、安堵が混ざったことを覚えている。GMとフィリップスと関係を持つようになれば、初の長編アニメーション映画をつくるという夢が断たれかねないことはわかっていた。そのリスクは、相手がどこであろうと変わらない。出資する側にはそれぞれの思惑があり、我々の存続はそれと引き換えにある。今となっては、私はその取引が失敗に終わったことを有り難いと思っている。おかげで、スティーブ・ジョブズとつながれたからだ。
私が初めてスティーブに会ったのは1985年の2月、彼はアップルコンピュータの取締役だった。私とアルヴィがグラフィックス部門をジョージから買い取ってくれる相手を探していることを知った、アップルのチーフサイエンティスト、アラン・ケイの計らいによって会うことになった。アランとは、私はユタ大学で、アルヴィはパロアルト研究所で一緒だった。アランはスティーブに、我々を訪ねればCGの最先端が見られると話していた。ホワイトボードと大きなテーブルとそれを囲む椅子のある会議室で行われた会合で、スティーブは長くは座っていなかった。数分後にはホワイトボードの前に立ち、アップルの収入を示すチャートを書き始めていた。
その毅然とした態度を覚えている。無駄話は一切なし。あるのは質問だけだった――おびただしい数の。何を求めているのか、何を目指しているのか、長期的な目標は何なのか。彼は、自分の信念を「めちゃくちゃすごい製品(insanely great products)」という言葉で表現した。彼は明らかにプレゼンテーションを受けるタイプではなく、すぐさま取引について話し始めた。
正直言って、私はスティーブを苦手なタイプだと思った。強引なところを恐れもした。自分より頭のいい人に囲まれることの重要さについて語ってきた私だが、彼の熱っぽさは次元が違いすぎてどう解釈したらいいのかわからなかった。
当時、マクセルというカセットテープの会社の宣伝に使われていた象徴的な画像が頭に浮かんだ。ル・コルビュジエのレザーとクロームでできた背の低い椅子に腰掛けた男の髪が、彼の前に置かれたステレオ音響スピーカーの音で後ろに吹き飛ばされているという絵。スティーブといるとそういう感じだった。彼がスピーカーで、ほかの全員がその男だ。