独創的なアニメーションを次々ヒットさせ、世界随一のクリエイティブな企業としても多くの人が憧れる、ピクサー・アニメーション・スタジオ。その共同創業者であるエド・キャットムル氏の著書『ピクサー流 創造するちから』より一部を紹介する。今回は、『スター・ウォーズ』が大ヒットしたルーカス・スタジオでコンピュータ部門を立ち上げるにあたり、その責任者として白羽の矢が立ったエドが初めてジョージ・ルーカスと対面した時のことを語る。
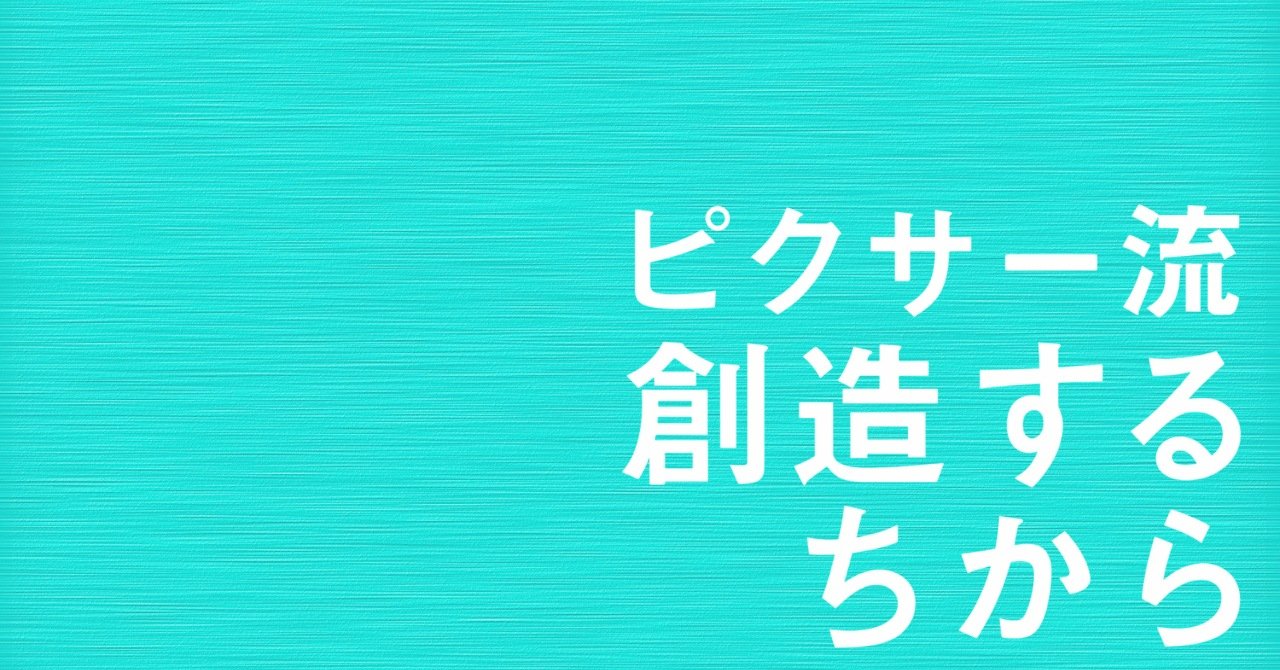
ルーカスと緊張の対面
1977年5月25日、アメリカ全土で『スター・ウォーズ』が封切られた。その巧みな視覚効果――と記録破りの興行成績――はこの業界を永久に変えることになる。しかも32歳のジョージ・ルーカスはまだ駆け出しの脚本家兼監督だった。彼の会社、ルーカスフィルムとその親会社のインダストリアル・ライト&マジックは、すでに視覚効果や音響設計のツール開発で先行していた。映画業界でそうしたものに投資をしようとほんの少しでも考える会社がほかになかったため、ジョージは1979年7月、コンピュータ部門を立ち上げることを決意した。“ルーク・スカイウォーカー”のおかげで十分な資金ができたというわけだ。
彼はその部門を、コンピュータの知識を持っているだけでなく、映画を愛し、コンピュータと映画が共存できるだけでなく、互いを高め合えると信じている人に任せたいと考えていた。やがて私に白羽の矢が立った。
彼の右腕の一人で特殊効果の草分け、リチャード・エドランドがある日の午後、ニューヨーク工科大学(NYIT)の私のオフィスに訪ねてきた。ベルトに大きな文字で“スター・ウォーズ”と書かれた巨大なバックルがついていた。私は彼の訪問をアレックス・シュアーに知られたくなかったので、それを見て不安になったが、何とかアレックスには気づかれずに済んだ。ジョージの使者は、私が見せたものを気に入ったようだった。なぜならその数週間後、私はカリフォルニアのルーカスフィルムに正式な面接を受けるために向かっていたからだ。
最初に会ったのは、ボブ・ジンディーという、ジョージの個人的な建設プロジェクトを担当していた人だった。コンピュータ部門の幹部探しの先鋒としては、意外な役回りだ。最初に聞かれたのは、「ほかに誰を検討したらよいと思いますか」という質問だった。この仕事の適任者として、という意味だ(私はこの仕事に就くために面接に来たのであるが)。私はすかさず、いろいろな技術分野で優れた仕事をしていた数人の名前をスラスラと挙げた。なぜ私がそうしたのかといえば、それは大学時代に培われた世界観による。困難な問題には、多くの知性を同時に集結して解決にあたったがほうがいい。それを認めないのはばかげている。
後から知ったことだが、ルーカスフィルムは私が挙げた人たちをすでに面接しており、やはり同じように推薦者を挙げさせたが、誰一人としてほかの人の名前を挙げなかったそうだ! ジョージ・ルーカスの下で働けるまたとない機会をみすみす逃そうと思う人はいない。だが、業界について聞かれて黙っているのは、競争の厳しさのせいもあるが、自信のなさの表れでもある。私はまもなくジョージ本人と面接することになった。
面接に向かう途中、それまで感じたことのない緊張感に襲われたのを覚えている。ジョージは『スター・ウォーズ』の前から『アメリカン・グラフィティ』という作品で脚本家・監督・プロデューサーとしての実力を認められていた。かたや私はコンピュータ屋で、お金のかかる夢を持っていた。それでも、彼が仕事をしていたロサンゼルスの撮影現場に到着すると、私と彼とは似た者同士だと感じた。痩せて髭を生やし、同じ30代前半、メガネをかけ、脇目も振らずに仕事をし、必要なことしか喋らない。
しかし、すぐにジョージの容赦ない現実主義に衝撃を受けた。彼は、趣味で映画づくりに技術を取り入れるようなタイプではなかった。彼のコンピュータに対する興味は、それがデジタル光学印刷であれ、デジタル音響、デジタルノンリニア編集、CGであれ、それを使うことが映画製作のプロセスに付加価値を与える可能性があるかどうかに始まり、それに尽きた。私はあると確信していたので、そう答えた。
ジョージは私の正直さ、「視界の明瞭さ」、そしてコンピュータの能力に対する揺るぎない信念を気に入って私を雇ったと後から聞かされた。面接後まもなく採用が決まった。
人材をいかに管理すべきか
ルーカスフィルムの新設コンピュータ部門の仮住まいとなるサンアンセルモの2階建てのビルに越した私は、人を管理する方法を考え直すことを自分への宿題にしていた。ジョージがつくりたかったのは、私がNYITで行っていたものよりずっと大がかりな事業だった。高い注目度、多額の予算、そして彼のハリウッドでの成功願望からいって大きな影響力。それらを存分に生かせるようなチームづくりをしなければ……。
NYITでは、ユタ大学で経験したようなフラットな構造と緩やかな管理でスタッフが自由に動き回れるようにして、その結果には比較的満足していた。だが、今思えば、チームはまるで大学院生の集まりのようだったことは否めない。各々のプロジェクトに取り組む思案者たちは、共通のゴールを目指すチームとは言い難い。研究所は大学とは違う。同じ構造をそのまま当てはめるには無理があった。
そこで、ルーカスフィルムでは、自分の下に、グラフィックス、ビデオ、オーディオのそれぞれのグループを束ねるマネジャーを採用した。何らかの階層制度を取り入れる必要があることはわかっていたが、一方でそれがかせとならないか心配でもあった。部分的には必要とわかっていながら、最初は半信半疑で恐る恐る導入した。
コンピュータの目覚ましい進化
1979年のベイエリアは、我々の仕事にとってこれ以上ないほど豊かな環境を呈していた。シリコンバレーでは、コンピュータ会社が急増するあまり、誰もロロデックス(そう、当時その名の回転式卓上名刺フォルダがあった)の整理が追いつかなかった。同じように桁外れに急増していたのが、コンピュータに与えられたタスクの数だ。私がカリフォルニアに来てまもなく、ビル・ゲイツがIBMの新しいパーソナルコンピュータ向けのOSの開発に同意した。言うまでもなく、それがアメリカ人の働き方を一変させることになる。その1年後、アタリが初の家庭用ゲーム機を発売した。これによって、スペースインベーダーやパックマンなどの人気アーケードゲームがアメリカ全土の居間で遊べるようになり、現在では世界で650億ドルという市場が誕生した。
その変化は目まぐるしい。私が大学院生だった1970年、IBMと他のメインフレームメーカー7社(このグループは「IBMと7人の小人たち」とあだ名されていた)が開発した巨大なコンピュータを使用していた。想像できるだろうか。一つの部屋を、機器が積まれた高さ180センチ、幅60センチ、奥行き75センチのおびただしい数のラックが埋め尽くしていた。
5年後、NYITに入ったときには、ミニコンピュータ(大型の衣装箪笥くらいの大きさだった)が台頭し、マサチューセッツのディジタル・イクイップメントがその最大手だった。1979年にルーカスフィルムに加わったときには、ワークステーションが流行しており、サン・マイクロシステムズやシリコングラフィックスなどのシリコンバレーの成り上がり企業やIBMがつくっていたが、そのころには誰もがワークステーションがパーソナルコンピュータ、そして最終的にパーソナルデスクトップコンピュータに代わる過渡期だと認識していた。
この進化のスピードは、技術革新の意欲と能力の持ち主に無限とも思えるチャンスを生み出していた。金持ちになれるという誘惑が、野心あふれる賢い人々を引きつけ、厳しい競争が生まれた。古いビジネスモデルは、次々と破壊的変化に見舞われた。







