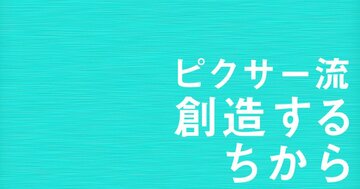独創的なアニメーションを次々ヒットさせ、世界随一のクリエイティブな企業としても多くの人が憧れる、ピクサー・アニメーション・スタジオ。その共同創業者であるエド・キャットムル氏の著書『ピクサー流 創造するちから』より一部を紹介する。今回は、ルーカス・フィルムに転じたエドたちが、新たなCG技術を生み出した一方で、古株のフィルム編集者たちの導入反対に遭い、人を巻き込むマネジャーの姿勢をジョージ・ルーカスの背中に学んだことなどが語られる。

「ピクサー」という名前の由来
ルーカスフィルムは、シリコンバレーから車で北に1時間ほど行ったマリンカウンティーにあった。ハリウッドからも飛行機で1時間だった。これは偶然ではなく、ジョージ自身が誰よりも先に、映画製作者としてシリコンバレーは自分には向かないと判断したのだった。同時に、そこはかとなく品の悪さや似た者同士が集まったような印象を受けるロサンゼルスに近づきすぎるのも嫌った。そのため、映画やコンピュータを愛するが、そのビジネスを象徴するいずれの主力文化にも属することなく孤島を築いた。
そうしてできた環境は、教育機関と同じくらい保護されているように感じた。その考え方がずっと私の中に残り、のちにピクサーでつくろうとしたものの原型になった。実験的な試みは非常に重視されていたが、利益追求企業の切迫感は確実に存在した。言葉を換えれば、理由があって問題解決しているような感じだった。
私はアルヴィをグラフィックスグループの責任者にした。そのグループは最初、ブルースクリーンマッティングをデジタル化することに専念した。ブルースクリーンマッティングとは、一つの画像(たとえば、サーフボードに乗っている人)を別の画像(たとえば、30メートルの波)に落とし込む処理だ。デジタル化以前は、高度な光学機器を使ってフィルム上で行われ、当時の特殊効果の名人たちはその手間のかかる方法を捨てる気がさらさらなかった。
そこを説得するのが我々の仕事だった。アルヴィのチームは、フィルムをスキャンし、特殊効果画像を実写映像と組み合わせ、できたものをフィルムに再び記録することのできる解像度と処理能力を持った専用のスタンドアローンコンピュータの設計に取りかかっていた。およそ4年かかったが、そのとおりの装置が仕上がり、ピクサー・イメージ・コンピュータと名づけられた。
なぜピクサーか。その名称は、アルヴィともう一人のスタッフ、ローレン・カーペンターとのやりとりの中で生まれた。幼少期のほとんどをテキサス州とニューメキシコ州で過ごしたアルヴィはスペイン語に対する愛着があり、「laser」のようにスペイン語の動詞に似た英語の名詞があることに心引かれていた。そこでアルヴィは、「映画(ピクチャー)をつくる」という意味を連想させる(嘘の)スペイン語の動詞「Pixer」という名前を推していた。これに対しローレンは、ハイテクなイメージの強い「Radar(レーダー)」のほうがいいと言った。そうしてひらめいたのが「Pixer + Radar = Pixar」、ぴったりな名前だった。
変化に抵抗する人々との闘い
ルーカスフィルム内の特殊効果の達人たちは、我々のCG技術に比較的無関心だったが、フィルム編集者たちには真っ向から反対された。ジョージからの依頼で、編集者の仕事をコンピュータ化するビデオ編集システムを開発したときにそれが明るみになった。ジョージが思い描いていたのは、撮影した画像を簡単に並べてファイルし、フィルムよりもはるかに速くカットをつくることのできるプログラムだった。
私がニューヨーク工科大学(NYIT)から引き抜いたプログラマーのラルフ・グッゲンハイム(カーネギーメロン大学で映画製作の学位も取得した)がこのプロジェクトを率いた。当時にしてはあまりに先進的だったため、それに対応するハードは存在すらしていなかった(ラルフは、それに近いシステムを試作するための苦肉の策として、レーザーディスクを使った)。そうした問題も立ちはだかっていたが、それさえも、我々の前進を妨げるもっと大きくて気の遠くなるような障害に比べればたいしたことはなかった。その障害とは、変化に抵抗する人間だ。
ジョージは新しいビデオ編集システムの導入を望んでいたが、フィルム編集者たちは違った。すでに習熟しているシステム、つまり、実際にフィルムを剃刀の刃で切り分け、また貼り直すという作業に満足していた。その作業を遅らせるような変化には一切興味を示さなかった。慣れ親しんだ方法を楽だと思い、変化を苦と見なしていた。
はたして、できあがったシステムを試す段になったとき、編集者たちは関わるのを拒否した。工程が飛躍的に改善されると我々がいくら自信を持って勧めても関知せず、ジョージの後押しも無駄だった。新しいシステムが役に立つはずの相手から反発を受けたことで、開発に急ブレーキがかかった。
どうするべきか。
編集者たちに選ばせたら、新しいツールは永久につくられず、改革の余地はない。新しいものに何のメリットも見出さず、コンピュータを使うことでいかに楽に、またはより優れた仕事ができるかを想像することができなかった。だが、編集者たちからのインプットなしの真空状態で新しいシステムをつくり続ければ、そのニーズを満たさないツールができてしまう。自分たちの技術革新の価値に自信を持つだけでは不十分だった。使ってもらう側の支持が必要だった。それなしでは、計画を捨てなければならない。
言うまでもなく、マネジャーは優れたアイデアを持っているだけではだめだ。そのアイデアを取り入れる人たちからの支持が得られなければ。私はこの教訓を胸に刻んだ。
「ヨーダ」に投じられた哲学
ルーカスフィルムで働いていた間、私はマネジャーとして重圧を感じる時期が確実に何度かあった。自分の能力に疑問がわき、もっとアルファオス(群れのボス)のように力ずくのマネジメントスタイルをとってみるべきなのか、自問した時期だ。
自分なりの階層制度を敷き、ほかのマネジャーに権限を与えたが、自分自身もその上のルーカスフィルム帝国の指揮命令系統に属していた。まるで群れの馬たちの背中でバランスをとろうとしているような、疲れ果てた気分で夜、家に帰っていたのを覚えている。サラブレッドは数頭だけで、完全な野生の暴れ馬がいたり、ついてくるのがやっとのポニーがいたりする、そんな群れだ。舵取りどころか、つかまっているのが精一杯だった。
とにかく人を管理するのは難しかった。私にそのコツを教えてくれる人もいなかった。このテーマに関して示唆を与えてくれると約束している本も、読むと中身がなかった。そこで、ジョージがどんなふうにやってのけているのかを観察した。そのやり方には、彼がヨーダというキャラクターに込めた哲学がいくらか反映されているように感じられた。
「やるかやらないかだ。やってみる、というのはなしじゃ」というヨーダのセリフのように、ジョージは、人生の矛盾を噛み砕いて何かに端的にたとえるのが好きだった。たとえば、2万平方メートル近い「スカイウォーカーランチ」スタジオ(住居と制作施設の小都市)をつくる骨の折れる作業を、船長が船外に放り出され、真っ二つに割れた状態で川を下る船にたとえた。「ぜったいにたどり着くぞ。オールを持って漕ぎ続けるんだ!」そう言った。
また、会社をつくることは大西部を目指す幌馬車隊に似ている、ともよく言っていた。豊かな土地に向かう長い旅の道中、開拓者たちは目的意識にあふれ、目指す地にたどり着くのだという目標で一致団結している。たどり着いてしまえば去る者も来る者も出てくる、そういうものだ、と。が、まだたどり着いていない何かに向かう過程こそが彼の理想だった。
幌馬車も船も、ジョージの長期的なものの見方がその原点にあった。彼は未来を信じ、それを形づくる自分の能力も信じていた。『アメリカン・グラフィティ』の成功後、若手映画製作者だった彼が、次の作品『スター・ウォーズ』で「ハリウッドが欲しがる映画だ、高値をふっかけろ」と、もっと高い報酬を請求すべきだと人から助言されたときのエピソードが語り継がれている。
ジョージはそういう人間ではない。彼は昇給をすべて蹴って、代わりに『スター・ウォーズ』のライセンス権と販売権の保有を求めた。配給会社の20世紀フォックスは、損はないと考えて二つ返事で了承した。ジョージはその考えがまちがいであることを証明してみせ、愛する業界を大きく変える素地をつくった。彼は自分に賭け、その賭けに勝ったのだ。