
この世界的なセラミックス企業集団(森村グループ)がいかにして形づくられたのか。その原点が、創業者の次男である7代目市左衛門自身の口から語られている。
幕末の開国時、日本の小判が不利な交換比率で海外へ流出するのを目の当たりにした6代目市左衛門は、「日本から金を奪われるのではなく、商品を輸出して金を取り戻すべきだ」と憤慨した。それが、貿易に従事するに至った直接の動機だったという。
福沢諭吉の教えを受けた異母弟・森村豊を米国に送り出し、1876年、ニューヨークに雑貨店を開設。その年のクリスマスには、日本から送った骨董品、陶器、銅器、うちわ、人形などが原価の数倍で売れ、大きな成功を収めた。民間による本格的な対米貿易の嚆矢とされるエピソードである。
やがて陶磁器類が輸出品として有望であることに着目し、商社でありながら自ら生産に乗り出す。フランスのカップを見本に、瀬戸の職人と試行錯誤を重ねて完成させたコーヒー茶わんの開発秘話は、技術立国日本の原点を感じさせる。
碍子(がいし)については、芝浦製作所(現東芝)の創立者の一人、岸敬二郎から「国産の碍子を作ってほしい」と熱心に口説かれ、門外漢ながら硬質磁器のノウハウを生かして挑戦したところ、その後の電力インフラの発展とともに事業が拡大していった経緯が語られる。
幕末の混乱と民間の海外雄飛、技術開発や品質への執念、顧客志向と倫理観――。現代の日本企業のアイデンティティーにつながる要素が、「一商人の体験」として生々しく描かれている点で、貴重な証言といえる。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
小判の両替で奮起
「貿易で小判を取り戻そう」
私の家はもともと、江戸で袋物の商売をしていた。徳川時代だから参勤交代制があって、日本全国の大小名が江戸に邸宅を持っていた。その連中が国元に帰るときには、何か江戸の土産を持ち帰った。当時の交通機関はせいぜいかごぐらいのもので、大体は足で“テクる”のだから、土産物にしても大きなものは邪魔になる。そこで、袋物が歓迎されたのである。
郷里に帰った者が、これは江戸の森村の袋物だといって宣伝してくれるから、その次に新しく江戸に来た者が、また買ってくれる。
そういうことで、結構、袋物の商売が繁盛したものである。
ところが幕末になると、西洋勢力が東漸してきて、ロシア、イギリス、フランス、米国などのいわゆる黒船が日本の沿海に出没して、開国を迫る。国内は攘夷開国の両論に分かれて、風雲急を告げる。幕府もこれまでのような鎖国主義で武陵桃源を夢見ているわけにいかなくなって、ついに安政5年、米国との間に通商条約の調印となった。そこで幕府は、米国に答礼の意味で、使節を派遣することになった。正使は、時の外国奉行・新見豊前守である。一行には、勝海舟、福沢諭吉先生なども一緒であった。
ところが、新見さんの親戚に跡部甲斐守という人があったが、この人は、大塩平八郎事件を裁いた名奉行で、私の祖父が懇意であった関係から、新見さんの身支度は森村にやらせようということになったのだそうである。
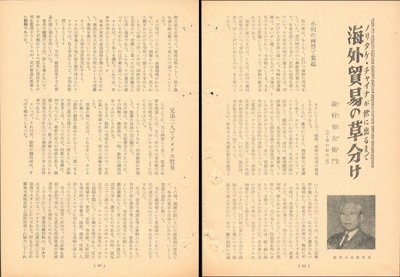 1955年7月臨時増刊『財界人物』より
1955年7月臨時増刊『財界人物』より
当時は外国事情も分からないから、新見さんは、日本流に考えて、向こうに行ったらいつ斬られるかもしれない、そのときの用意にといって、父に命じて白装束を作らせたり、また帷子(かたびら)にはごく細い鎖を入れたものを作らせたそうだ。身支度の方が片付くと、今度は小判をメキシコ・ドルに両替することも頼まれた。
そのときには、江戸城の奥から小判の千両箱を3000箱受領して、それをかごに載せて横浜まで運んだのだが、途中、かごの両側には護衛の武士が従って、警戒は物々しく、鈴ヶ森を通るときは物騒で命懸けで通ったということだ。







