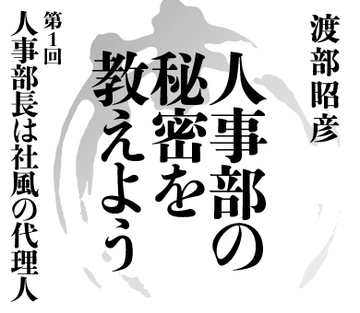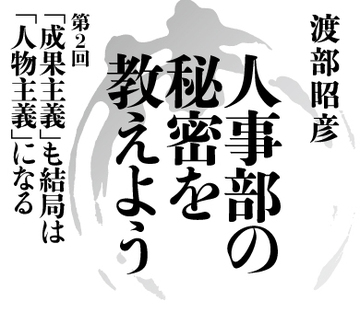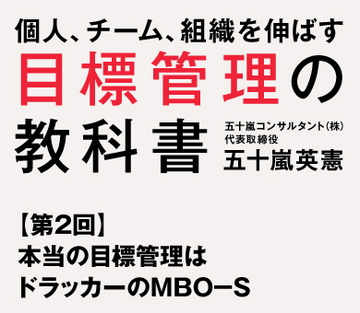上司の評価は必ず「寛大化」する
目標管理は大企業ほど精緻化され、職種や職階に応じて何十種類かの評価シートを使い分ける会社もある。数個から10を超える項目の目標についてそれぞれ達成度に応じた評価を行ない、それらをまとめて最後は総合評価を出す仕組みだ。
目標管理制度についても「達成度にもとづく評価だと、仕事のむずかしさの差が反映せず不公平だ」「目標のバーの高さをどうするかで恣意的に運用されてしまう」「期中で大きな環境変化があった場合にはどうするのか」など、問題点の指摘がなされている。これらの問題は運用である程度は解決可能だが、構造上の最大の問題は、「最後は総合評価を出す」というプロセスにある。たとえば、仮に10個の目標を設定して、きめこまやかな業績管理を行なっても、最後にはS、A、B、C、Dなどの3~5段階の評価にまとめることになる。
10個の各目標に対する評価がすべてSであれば、総合評価もSで問題はない。では、Sが5個、Dが5個だったら平均してBだろうか。Aが7個でCが3個だったら……など、とても悩ましい。理屈っぽい会社は、各評価にS=10点、A=8点などの点数を振り、その平均で総合評価を出したりしているが、こうなると単なる数字のお遊びで、もはやほとんど評価としての意味をなさないのはすぐにわかるだろう。
結局どうするかといえば、管理者は最初におおよそその総合評価を頭のなかで決めたうえ、数学の因数分解のように逆のフローで各目標の評価に遡っていく。「彼は総合評価がAだから各項目の評価はSとAとBを概ね3個ずつにしなければいけないな」などだ。
そして極めつけは、最後の評価は「良い」「普通」「悪い」の三つに収斂してしまうのだ。いくつかの業種での人事経験からいうと、仮にSからDまでの五段階評価の場合、実際にラインの評価者から上がってくる分布は、Sが10%、Aが60%、Bが30%といった感じだ。CとDはまずお目にかかったことがない。人事用語では、評価の「中心化」と「寛大化」と表現される現象だ。
これで、上司の立場からは「君には(平均のBではなく)Aをつけておいたから」と言って部下に恩を売ることができる。かといってSを頻発してしまうと、安易な評価姿勢を人事から指摘されることになる。能力がいま一つの部下についても、まずはBにしておけば無難だ。仮に実際に支給されたボーナス金額が少なくて、本人からクレームがついても「おかしいなあ、少なくとも平均のBはつけておいたんだが」と言いわけができる。
では、どうして上司は「寛大化」に流れてしまうのだろうか。それは厳正な評価をしても得るものは何もないからだ。
ダメな部下にダメとストレートに伝えたとしよう。おそらく本人はやる気をなくし、職場の不満分子になるに違いない。みずから外に転職する力はないだろうし、だからといってわが国の労働法制下では社員をクビにすることはまずできない。社内異動で移そうにも受け入れてくれる部署もない。となれば、Dの人にDとつけても面倒になるだけなのだ。逆に極端な話、部下全員にSをつけても上司は失うものはない。むしろ部下たちは「物わかりのいい立派な上司だ」と褒めながら元気に頑張ってくれる。仮に人事部に「いい加減ですね」と言われても、「当社の人材はみんな優秀なんだから当然。それとも人事部はレベルの低い人を採用しているのですか」と居直ってしまえばよい。
どれもこれも目標管理制度が「絶対評価」を建前としているところから生じる問題点だ。絶対評価というのは全員が目標を達成すれば全員がSでもよいという考え方だ。そうなると全員にボーナスを奮発しなければならない。本当に全員がSの業績であれば、少なくとも部署としては儲かっているはずなので、ボーナスの奮発はOKだ。
では、「寛大化」のなかで絶対評価をすると、どうなるだろうか。いわゆる「合成の誤謬」が発生し、実際の収益に見合わない支出によって赤字になってしまう。