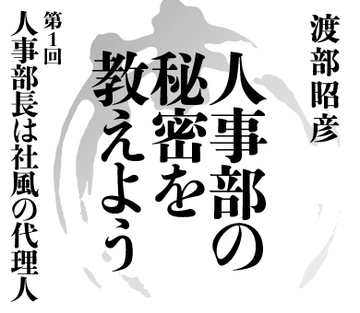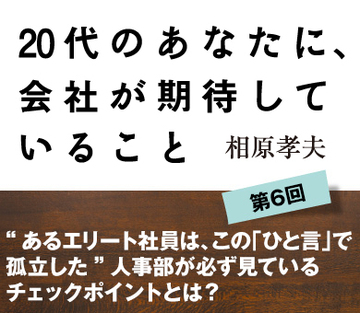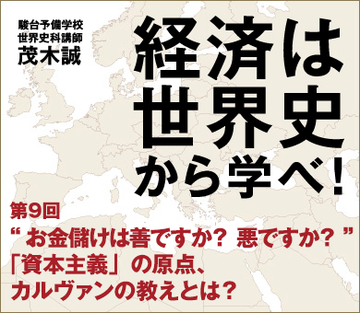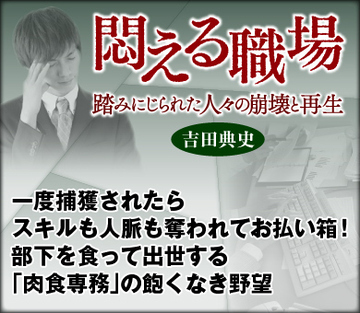大手銀行、セブン‐イレブン、楽天で、人事部長や人事担当役員を経験した渡部昭彦氏に、人事部や人事制度の裏側を教えてもらう連載の第2回。一世を風靡しながらも、結局は日本企業に根付かなかった成果主義の実態を解説してもらう。
根づかなかった成果主義
会社が社員に給料を払うのは慈善事業ではないので、当然何かの見返りを求めている。その何かを一言で言えば「労働力」だが、もう少し理念的に表現すると、「仕事を通じて創出される付加価値に対して報酬が支払われる」ということになる。
1990年代のバブル崩壊以降、人事の世界ではさかんに「成果主義」的な概念の導入が叫ばれた。過去形のニュアンスで「叫ばれた」と書いたのは、むしろここ10年は「反成果主義」「脱成果主義」の論調が目立つためだ。
まず、バブル崩壊後に成果主義が求められた背景を考えてみると、低成長経済に移行して会社が儲からなくなったというシンプルな事実に尽きる。「それまでの年功型の賃金はもはやとても支払いきれない、それなら、年齢とか関係なく働いて稼いだ仕事に見合うだけ給料を払うようにしよう」ということだ。経緯はともかくとして、結論の部分は、至極まともな考えである。では、その後になぜ「反成果主義」をはじめとして、成果主義の限界や問題点が指摘されるようになったのだろうか。
成果主義の問題点として一般的には二つのことが言われている。
一つは成果主義が結局、リストラのための方便にすぎなかったのではないかということだ。私もそのころ、金融機関の人事部に在籍して個人別の給与やボーナスの金額査定作業をしていたが、「削る」ことはあっても「増やす」ことはほとんどなかった。「業績に応じてメリハリをつけるのが成果主義だ」と頭ではわかっていても、経営の命題として人件費の大枠について抑制または削減が決まっている以上、多少成績がいい人がいても、なかなか「増やす」という判断はつきかねるのだ。減らすけれど増やさない……このような行動が日本中の企業の人事部で取られた。「成果主義はじつはリストラの方便」という世論が起きたのも仕方がないところだ。
二つ目の指摘は、成果主義が「短期・結果至上主義」になり、会社の中長期的な観点からの発展や成長のための行動が取れなくなるのではないかということだ。「日本の企業のよさが失われる」という表現もよく使われる。この点については「本当にそうかな?」という印象がある。もし企業が長期的な観点からの行動を社員に求めるのであれば、それに応じた目標なりミッションを与えればよく、その際に求める「結果」の概念を柔軟に変えて対応すればよいからだ。
いずれにせよ、結局、成果主義はほとんど日本の企業には根づかなかった。そして、その背景には根深いものがあった。成果に応じての評価や処遇を徹底した場合、当然の帰結として年齢や入社年次が逆転した報酬や昇格、人事異動が常態化する。その結果、社内の人間関係には大いなる緊張感が生じる。「昨日の部下が今日の上司」と考えてみればわかりやすい。年功概念の問題というよりは、もはや儒教の精神にまで辿りつく日本人のメンタリティの領域の話となるのだ。
「元上司が部下」となれば、使うほうはやりにくく気疲れし、使われるほうはやる気が出るわけもない。組織にとっては大いにマイナスだ。その唯一の解決策は「成績不良者」(上記の例では元上司)を解職して外に出すことだが、それは周知のとおり、日本の労働法制上は簡単ではない。となれば変に刺激してフラストレーションと疲れを社内に充満させるよりは、「日本の企業のよさ」なる解釈で伝統的な人事システムを踏襲するほうが得策となる。
率直なところ「反成果主義」の議論は、私には奇異に感じられる。なぜなら、成果主義自体がほとんど根づいていないにもかかわらず、「反」という概念は起こりようもないからだ。
では、あれだけ騒がれた「成果主義」の現状は一体どうなっているのか。「成果主義、じつは人物主義」のとおり、実際は日本企業の伝統的な人事概念である「人物主義」が何の変化もなく脈々と生き残っているのである。