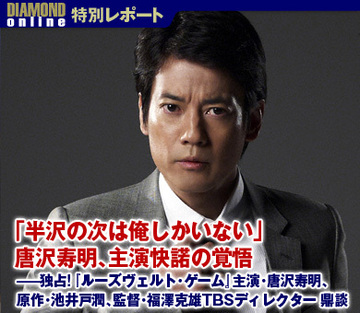左遷か―――。
会社員人生最後の転落
「おう、沢井君か。まあ、そこへかけてくれ」
深々とした椅子から身体を重たげに持ち上げた梅田社長は、手のひらで応接セットを示した。デスクを回って出てくると、自分もソファーに腰を下ろして、ふうっと大きく息をついた。180センチ近い長身で、最近一段と太った身体がいかにも重そうだ。53歳、166センチ、中肉中背の沢井は、10歳以上も年上の社長の前で、自分の若さを、チラッと感じていた。
「さっそくだが、7月1日付で、太宝工業へ社長として出向してもらいたい」
「……?」
息を飲んで、社長の顔を見た。同時に、そうか、取締役昇任はなし、か──という思いが沢井の頭をよぎった。沢井の視線に社長は一瞬とまどいのような気弱な表情を見せたが、すぐに話を続けた。
「太宝工業は、君も知ってのとおり、業績の悪い会社だ。当社の傘下におさめてから約20年、この間ほとんど赤字の連続だ。当社も、役員を退任した経営者を社長にすえて、黒字浮上に努めてきた。が、結果は少しも良くならない。親会社としていろいろな形で支援してきたが、その親会社のほうも今や自分を支えるので精一杯だ。このうえ子会社に足を引っ張られてはたまらない……」
取締役就任を期待しているであろう沢井に、子会社への出向を命ずる。こういう嫌な話は誰だってしたくない。身体が大きく豪放そうに見えるが、気の弱いところのある梅田は、しゃべっていることで救われているように、話を続けた。
──そうか。取締役はなしで、子会社出向か。それも50社を超える子会社のなかで業績最悪の万年赤字会社の社長か。それが、今まで業績を上げてきた俺に対する会社の処遇か。
社長の話の切れ目に、沢井はボソッと口を開いた。
「それで、太宝工業へ行って、私に何をやれというのですか」