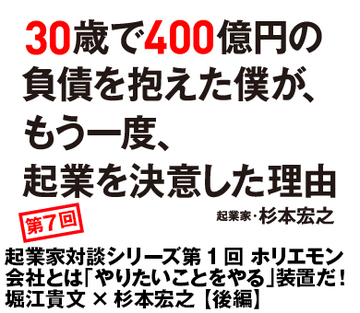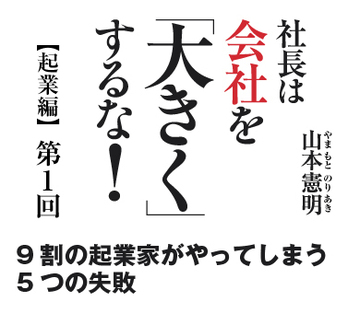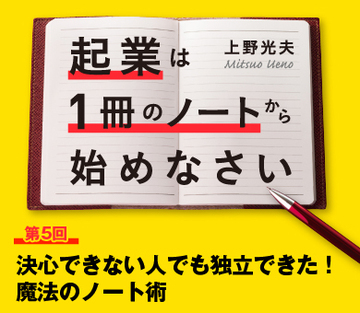本連載では、本年7月に経産省を退官してベンチャー企業を立ち上げた筆者が、経営者としての生身の体験の一部をご紹介するとともに、日本の構造的な問題や復活に向けたビジョンなどについて語っていく。
第1回『なぜ経産省を辞めて“天落”人生を選んだのか』では、国家プロジェクトでは世の中を変えられない理由について解説した。第2回の本稿では、実際に起業するまでの間に起こった筆者自身の心境の変化と、起業する過程で見えてきた周囲との関係についてご紹介したい。
起業で頼りになるのは誰か?
霞が関というのは非常に面白いところである。雑用係からスタートしたと思ったら、突然重要な判断を求められる責任者の立場に置き換わる経験をする。
入省して1年目の時は、官僚なのかアルバイトなのかが分からないくらい、たくさんの雑用をやらされた。例えば大量のコピーやコピーした資料の配布、打ち合わせのための弁当の手配、会議室の予約、公用車やタクシーの手配などだ。
しかし、5年目くらいで課長補佐を命ぜられるようになると、状況は一変する。「あなたが判断し、行動しなければ誰もやってくれませんよ」と言われかねない状況に置かれ、高度な判断や行動を求められるようになる。
企業の人たちとの接点も大幅に増える。自分の父親と変わらない年齢の大企業の部長級と付き合うことは、当たり前になっていく。当初は一回りも二回りも上の年齢の人と対等に話すことに違和感を覚えていたが、仕事上お願いされたり、お願いしたりすることが増えてくると、違和感はどこかに吹っ飛び、これも当たり前のこととなってくる。
筆者も課長補佐になって1~2年目くらいまでは違和感を持っていた。しかし、いつの間にか慣れてしまい、大企業の幹部クラスの人たちと対等に話し、時には意見することも当たり前のことになっていったように思える。
ところが、度重なる異動を経験していくと、前職で頻繁に会って話をしていた人から、パタッと連絡が途絶えることが増えていくことに気づいた。こうしたことを何度か経験していくうちに、この人は肩書で付き合っていて、あの人は肩書とは無縁に付き合ってくれる、という視点を持つようになった。今思えば、ひょっとするとこのあたりから、官僚をやり続けることに違和感を覚え始めていたのかもしれない。