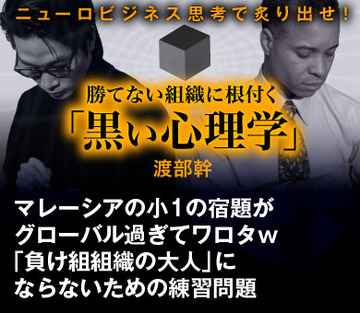前回ピケティについて取り上げた際、「GDPと言っても抽象的なGDPがあるわけではない」「1人ひとりの国民がつくり出す付加価値の全てが積み上がったものが、一国のGDPである」「経済成長の基本は、国民1人ひとりがその持てる能力を十全に発揮できるようにすることだ」とご説明した。
国民1人ひとりの能力の基本は、教育である。そこで今回は、わが国の明治以来の発展の背景にあった教育について取り上げることとしたい。
そのような問題意識から見た場合、興味深いのが、明治期のわが国の教育が今日の米国流の教育に近かったことである。それは、江戸の寺子屋教育の延長線上にあったものだった。そのような教育を、デービッド・モーレルという明治政府の教育顧問が絶賛していた。それは、1人ひとりの生徒に向き合う教育だったのである。
米国人の教育顧問に絶賛された
江戸の寺子屋教育
今日の日本の教育の問題点として画一的ということが挙げられよう。そしてそれは、もっと画一的で中央集権的だった戦前の教育を引き継いだものだと思っている人が多い。明治5年の学制(注1)発布の際の仰出書に「必ス邑(むら)ニ不學ノ戸ナク家ニ不學ノ人ナカラシメン事ヲ期ス」とある、いかにも古めかしい文書の響きがそう思わせるのであろう。
しかしながら実は、この仰出書によって設立された2万4000あまりの小学校(注2)は、画一的とか中央集権的というにはほど遠いものであった。
(注1) 明治5年の学制は、フランスにならって学区制(全国を8大学区、1大学区を32中学区、1中学区を210小学区とするもの)を定めたが、実際に設立されたのは小学校だけで、大学としては明治10年に東京に、明治30年に京都に帝国大学が創設された。中学校は設立されず、明治25年に任意制の高等小学校が設立された。
(注2)2万4000あまりの小学校が設立された背景に、幕末に全国で1万5000とも2万とも言われた寺子屋の存在があった。江戸では、「一町あたり最低二、三軒はあり、庶民の80パーセントが寺子屋へ通っていた」「近代的な小学校が寺子屋程度の小学校と同数になったのは明治40年であった」(以下、出典のない引用は、今野信雄『江戸を楽しむ』から)。
(注2)2万4000あまりの小学校が設立された背景に、幕末に全国で1万5000とも2万とも言われた寺子屋の存在があった。江戸では、「一町あたり最低二、三軒はあり、庶民の80パーセントが寺子屋へ通っていた」「近代的な小学校が寺子屋程度の小学校と同数になったのは明治40年であった」(以下、出典のない引用は、今野信雄『江戸を楽しむ』から)。