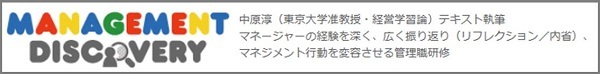どう教えるかより、どうあるか
教え方が大きく変わったのは、花緑さんが落語と共に10年以上続けている演劇の仕事の影響もありました。
「演劇の仕事を通して、演出について多くを学んだおかげで、稽古に演出を取り入れるようになりました」。
落語の稽古は、どちらかというと、文言の違いやアクセントを直すといった技術的な指導をするのが一般的で、演出をすることは少ないとのこと。
「僕は『この台詞はどういう心理で言ってるんだと思う?』『登場人物の立場を想像してみて』などと問いかけ、演出を考えさせながら稽古をしています」
このように、相手の心理を想像し、客観的にものを見る見方は、「小さんの孫」という重荷に苦しんだ20歳前後に身についたものでもあると言います。
「『よっ、お坊ちゃん』なんて言われるたび、傷ついていました。しかし相手の立場になってみると、落語協会会長の孫に対して、そんなふうに声をかけたくなる気持ちもわかりますよね」
相手の立場に立ってその気持ちを想像できるようになってからは、嫌いな人がいなくなったそうです。そして、「普段から客観的なものの見方をし、人の気持ちについて考えられないと、落語の演出を考えることはできない、と弟子にも言い聞かせています」
「今は弟子を家族のように思い、どうやって導けばいいのか、“いい噺家”になるにはどうしてあげたらいいかを考えては、それを実行に移してみる、といったことを繰り返す日々です。その中で思うのは結局、『どう教えるかよりも、どうあるかが大事だ』ということです。弟子に対して何を言うかよりも、自分がどうあるか、自分がまず実践者であるかどうかが重要なんです。祖父がそうでしたから、これは間違いないことだと確信しています」
落語家として手の内を明かしてしまうような著書、『落語家はなぜ噺を忘れないのか』を書いたのも、「自分は、この本で書いたものよりさらに上に行きたい、という思いがあったから」と話す花緑さん。そんなところにも、偉大な祖父5代目柳家小さんから受け継いだ「落語家という生き方」を、弟子へと伝えるべく、自らも常に挑戦を続ける実践者であろうとする花緑さんの覚悟を感じました。
(Reflection)
家族という社会関係の中で育まれる「守破離」
師匠や、その時々の稽古をつけてくれる先輩についてひたすら模倣を繰り返す若手時代。自分なりの芸能を模索し、煩悶する青年時代。そして、自らも弟子をとりはじめ、さらなる極みに至ろうとしている今、今回のインタビューが実現したことを、心より嬉しく思います。
今回のインタビューは私にとっても、非常に印象的でしたが、最も興味深かったのは、「落語家の師匠と弟子との関係は、先生と生徒ではなく、むしろ親子、家族に近い関係である」という言葉。そして「落語家になるというのは、落語家という生き方を選ぶ」という一言でした。
よく人材育成の言説空間では、ビジネスパーソンの熟達を表現する言葉として「守破離」が使われたりしますが、本当の守破離とは、「家族」という社会的関係、そして「生き方を選ぶ」という重さの中に存在するものだと思います。そのことを実感させていただいた取材でした。
花緑さんの著書『落語家はなぜ噺を忘れないのか』もぜひ読んでみてください。