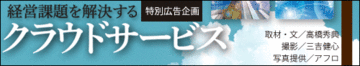ダイヤモンド・オンラインplus
電気料金の値上げや、電力需給の逼迫など、「節電」に対するプライオリティはますます高まっている。しかし節電で効果が高いのに、じつは盲点となっているのが「ポンプ」の存在だ。製造工場の現場はもちろん、事務中心のオフィスビルといった身近な場所でもポンプの恩恵にあずかっている。その効果と対策を見てみよう。

ビジネスで通用する英会話のスキルは、どのレベルまで磨き上げれば盤石なのか? かねてからその有力なモノサシと位置づけられてきたのが、TOEICなどの語学力検定である。だが、英語によるビジネス・コミュニケーション研究の第一人者である明星大学の田中宏昌教授は、冒頭からこんなショッキングな指摘をする。
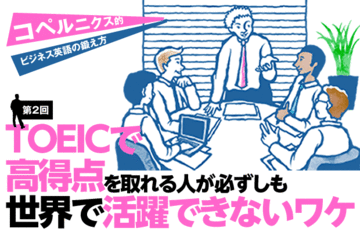
夏休みを間近に控え、旅行シーズンに突入した。震災による落ち込みから回復、円高でお得感のある海外のみならず、避暑地をはじめ国内旅行も人気を呼んでいる。夏から秋の旅の動向を探ってみた。
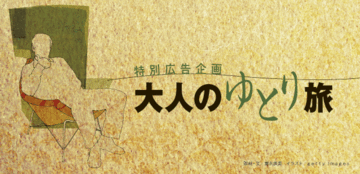
自然現象としての「地震」と、社会現象としての「震災」は別のものであると主張するのは、地震学者である島村英紀教授である。地震を防ぐことはできないが、震災の被害を小さくすることはできる。地震国である日本を生きるための知識と備えの方法を聞いた。
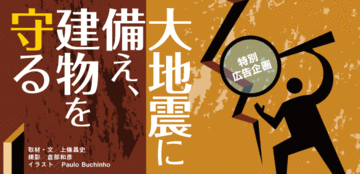
今ではあらゆる業種・職種の人が、英語を使って仕事をすることを求められる。しかも昔と今ではビジネス英語に求められるスキルが異なってきているという。明星大学の田中宏昌教授に話を聞いた。
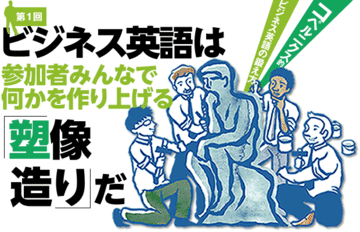
日本は、2020年に中古住宅流通・リフォームの市場規模を倍増させることを目指している。30~40代を中心に、中古住宅人気も上昇中。この勢いを加速させるには、流通改革と更なる優遇税制が必要だと提唱するが井端純一氏だ。


日本のエネルギー政策が新たな一歩を踏み出す中、太陽光発電システムへの関心が高まっている。「災害への備え、エネルギーの自給自足、エコ」といったキーワードに加え、「売電によるビジネス」という着眼点も見逃せなくなった。太陽光発電システムに関する調査、提言などを行ってきた専門家に、今後の展望と課題を聞いた。
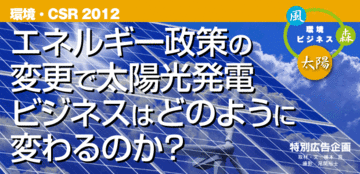
一般的に、中堅・中小企業では、経理や会計事務に精通した人材は限られている。かといって、高いリテラシーを持った人材を新たに雇用する費用対効果にも疑問が残る。そんなジレンマを抱えている企業にとって力になるのはアウトソーシングサービスの導入だ。
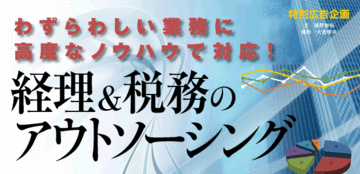
経理・会計・税務のアウトソーサーとしては、業界のパイオニア的存在なのがCSアカウンティングだ。現在は、隣接する人事・労務に関する業務も含めてオーダーメード型のワンストップサービスを提供。専門知識を持つ150人規模のプロフェッショナルスタッフが、連携を密に図りながら、顧客企業の高度なアウトソーシングニーズに応えている。

企業が持つブランドの強みを伸ばすWebコンサルティングにより、ECサイトをはじめ多くの企業サイトを成功に導いてきたネットコンシェルジェは、「ブランディング」の視点からWebサイトの課題を洗い出し、その解決を支援する。同社の手法を尼口友厚代表取締役に聞いた。

国内アフィリエイト・サービス・プロバイダの草分けであるバリューコマースは、5四半期連続増収を達成するなど着実に成長を遂げている。このほど同社が打ち出した今後の成長の道筋と、新たな海外戦略を2人の経営トップが語った。

年々拡大するEC市場だが、民間消費全体に占める割合はわずか2.46%と拡大の余地は大きい。多くの企業が参入する中で成功する秘訣は何か? ECビジネスに詳しい東京工科大学メディア学部の進藤美希准教授に聞いた。

ブランド品セレクトショップの展開で市場をリードするセキドと、国内家電ネット通販大手のストリームが、戦略的な資本業務提携を行う。狙うのは、相互補完体制の構築による売り上げ増大と利益体質の強化。また中国をはじめとするアジア地域への進出ももくろむ。

近年竣工のオフィスビルは、さまざま機能を高水準で備え、高機能化している。しかもそれは単なるインフラストラクチャーだけではなく、“快適に働ける環境”というソフト面も充実したものである。

若年人口の減少に伴って大学の競争が激化、生き残りを懸けて新たな特色を打ち出す大学が増えている。建学の理念や研究・教育姿勢の伝統を大切にしながら、時代のニーズに応えていく。そんな取り組みにまい進し、新たなブランド力を獲得している大学に注目したい。
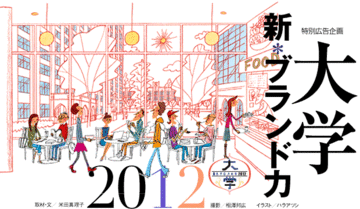
少額送金や送金頻度の高い法人企業から高い評価を受けている、楽天銀行の海外送金サービス。送金手数料は1000円、ネットで24時間いつでも送金手続きができるのが魅力だ。

円高からの脱却や新市場開拓のために海外を目指す中堅・中小企業が増えている。現地の法制度や商習慣の違いに戸惑い、思い描いていたビジネスを実現できないケースもある。頼れる専門家や支援サービスを徹底活用することが、海外ビジネスを成功させるための突破口となりそうだ。

住宅ローンの返済や子どもの教育費、場合によっては親の介護費用など、出ていくお金はやたらと増える半面、長く日本人の所得は頭打ち傾向が続いている。この状態はいつまで続くのか。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会副理事長の白根壽晴氏に聞いた。
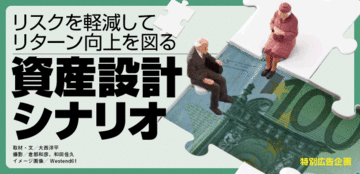
自前でサーバやストレージなどのリソースを持たずにITを活用する「パブリッククラウド」が着実に広がりを見せている。企業経営者としては、クラウドをどう理解し、どのように活用すればよいのだろうか。