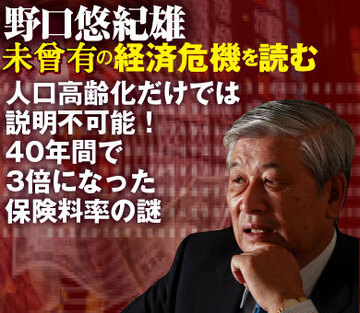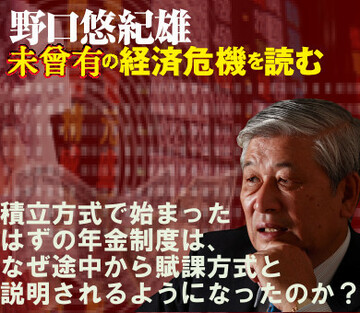経済の急激な落ち込みが続いているので、経済指標に対する関心が高まっている。
ところで、これらの指数の変化は、「対前年比」で示されているものと、「対前期(月)比」で示されているものがある。
これまでは、こうした表現法の違いをあまり意識していなかったのだが、最近のように変化が激しくなってくると、どの尺度で見るかによって、印象がかなり異なってくる。以下では、これに関する留意点を述べよう。
結論をあらかじめいえば、最近のように変化が激しいときには、「対前期比の年率換算値」を見るのが、変化率を適切にとらえるにはよいだろう。対前年比を見ていると、誤解に陥る場合がある。
そのことを示すために、まず仮想の数値例を考えてみよう(【表1】参照)。
仮に、ある指標の値が、長期間100を続けていたが、08年10月に急激に落ち込んだとする。毎月10ずつ減少し、09年3月に40になるまで落ち込みが続き、4月からは40で不変になったとする。
この場合、指標の絶対値、対前年同月比、対前月比、対前月比年率は、表のA、B、C、Dに示すように変化する。これを見ると、つぎのことがわかる。
| 【表1】変化を見るさまざまな尺度(数値例) |
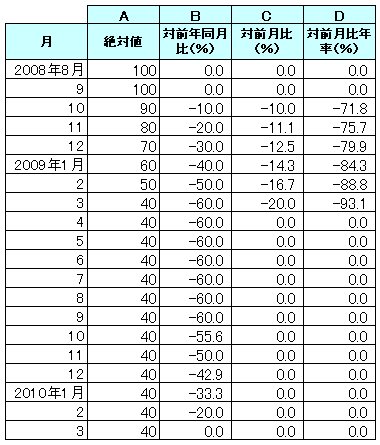 |
(1)表のB欄に示す「対前年同月比」は、08年10月以降、月がたつほど絶対値では大きな数字となってゆく。
これは、水準が次第に低まってゆくことを示しているのだが、減少率自体が高まっているような錯覚に陥ることがある。また、変化が始まった最初の段階では数字が小さいので、影響を過小評価してしまう危険もある。
また、落ち込みが終わって横ばいの状態に移行してから後も、しばらくの間は対前年比の数字がマイナスで拡大し続けることがある。表に示す数値例の場合、09年4月には落ち込みは終わっているのだが、対前年比はマイナスだ。これが09年9月まで続く。それ以降は絶対値は小さくなるものの、マイナスの数字が10年2月まで続く。したがって、減少過程が依然として続いているかのごとき錯覚に陥る。つまり、落ち込みの度合いを過大評価してしまう危険があるわけだ。