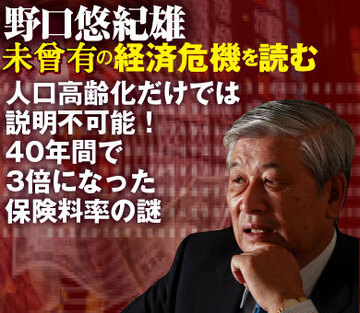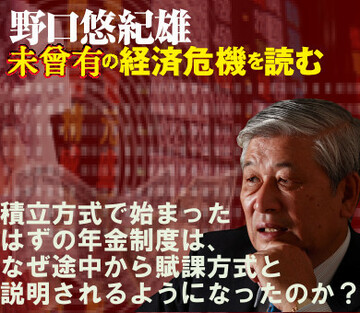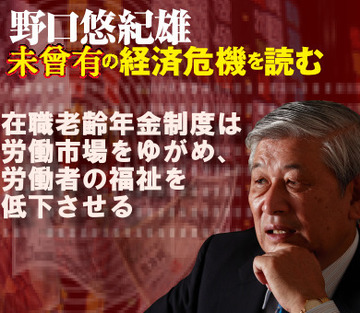給与所得だけを対象とする在職老齢年金制度は、公平の原則に反する。
前回、前々回と在職老齢年金制度の問題点について論じてきた。最大の問題は、高齢者の労働市場をゆがめることである。受給者は減額を避けるため、企業は年金保険料の企業負担を免れるため、給与を低めに調整することが行なわれるようになる。
具体的には、「年金込みでいくら」という雇用条件が一般的になる。これは、高齢者の低賃金労働を促進するだけでなく、若年者の雇用を奪う結果ともなる。そして、これは、実質的には、雇用主に対する補助を年金を用いて行なう仕組みにほかならない。
在職老齢年金制度の問題点としては、さらに、所得の種類によって大きな格差が存在することがあげられる。
年金減額の基準になるのは、給与所得だけであり、それ以外の所得はカウントされないのである。したがって、資産所得など給与所得以外の所得がいくら多くても、年金がカットされることはない。つまり、これは、給与所得に著しく不利な制度なのである。
たとえば、配当などの資産所得や貸家の家賃収入などの場合には、それがいかに多額であっても、在職老齢年金における年金カットの基準としては算入されない。したがって、これらの形態で多額の所得を得、そのうえ年金を受給するというケースは、十分ありうる。
「水平的公平」が侵される
上で述べたのは、租税論において「水平的公平」と言われる問題である。
「水平的公平」とは、「所得を基準として判断がなされる場合、同一額の所得であれば、形態のいかんにかかわらず同一の扱いを受けなければならない(所得の形態の差によって差別をしてはならない)」という原則である。この原則は、疑問の余地なく受け入れるべき原則であると考えられる。
租税制度においてこの原則から導かれるのが、「総合課税の原則」だ。すなわち、すべての所得はいったん合算され、それに対して各種の控除などがなされて課税所得が算出され、それに対して税率を適用して税額を定める(さらに、必要に応じて税額控除を行なう)、という仕組みである。
現実には資産課税におけるように分離課税の扱いがなされているし、また年金所得等に対しても、特別の控除が適用される。しかし、これらは、水平的公平の原則を侵すために、望ましくないと判断されるわけである。