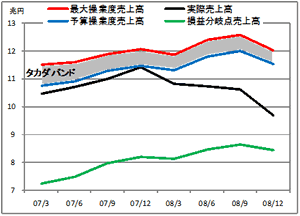高田直芳
第13回
前回はソフトバンクを取り上げ、客観的数値を用いることで、実は借金体質に悩まされているという実態を指摘した。今回はNTTグループの1つ、ドコモを取り上げる。同社は1991年8月設立なので、今年で18年目。ドイツ語で「会社」は“die Gesellschaft”という女性名詞であるから、「芳紀まさに18歳」である。ところが、そんな彼女にも深い悩みがある。今回は、その原因を探るとともに、“じゃじゃ馬娘”ソフトバンクの「隠された戦略」もあぶり出してみたい。
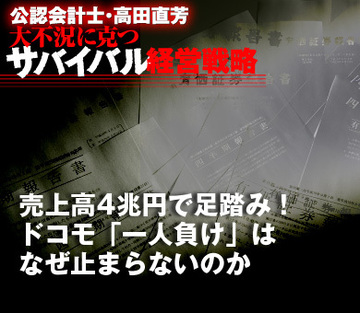
第12回
ソフトバンクとNTT間の売上高・総資産は、4倍前後にまで接近している。ソフトバンクはNTTの背中が見え始めていかのように思われるが、「借金体質」であることを見過ごしてはいけない。
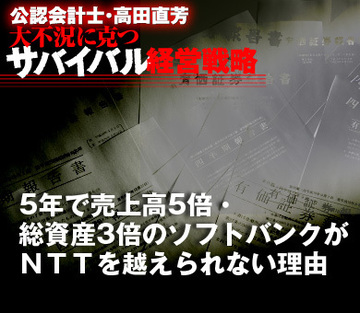
第11回
経営分析を行なっていると袋小路に陥ってしまう原因の1つに「税効果会計」がある。実はその税効果会計により“繰延税金資産”を計上することで、増資を行なうよりも手軽な資本増強策になってしまう恐れがある。
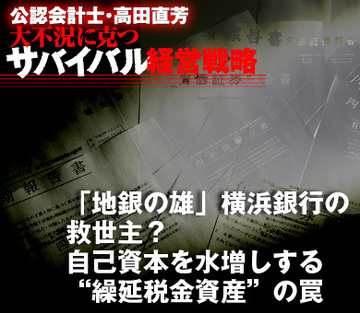
第10回
サブプライムローンやリーマンショックの影響で、惨敗を帰している銀行業界。メガバンク各社はこの夏に、数千億円の増資を行なう予定だが、過小資本状態である彼らがこの苦境から抜け出すのは難しいだろう。
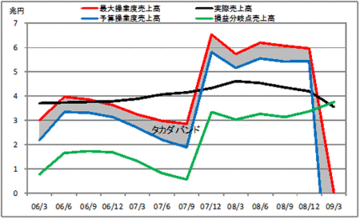
第9回
コンビニエンス業界で最も大切なのは、流通コストの最適化である。これは「商品1個当たり」の変動費として扱われるが、「複利運用の連鎖」を考慮するならば、変動費だけでなく固定費についても考える必要がある。
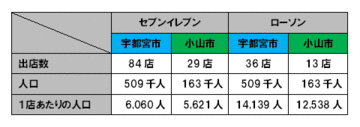
第8回
「赤字転落の原因は、売上の減少」と言っている企業は、いつまでたっても業績は回復しない。固定費と変動費を的確に分解する分析を行なわなければ、コスト削減の本質には迫ることはできないのだ。
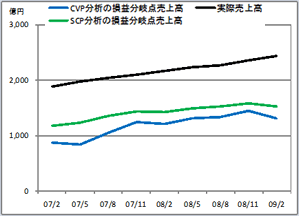
第7回
これまで不況に悩む電機や自動車各社を分析してきたが、今回は「独り勝ち」の代表格「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングを取り上げる。最高益更新中で絶好調の同社には、本当に死角がないのだろうか?
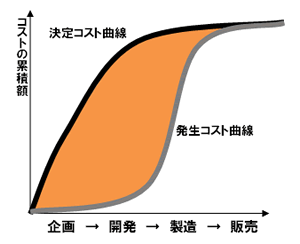
第6回
これまで数回に渡って不況に悩む電機各社を分析して来たが、今回は東芝をメインに取り上げる。東芝は4月17日に、「2009年3月期における当期純利益が3500億円の赤字になる」と発表した。3か月前に発表された2800億円の赤字予想から、さらなる業績の下方修正となった。業績悪化に伴い、自己資本比率は半分以下に目減りし、6月には5千億円規模の増資を行なう予定だという。そこで今回は、第4回コラムで掲載した東芝型の操業度率を再掲するところから話を始め、その深刻さを検証しながら、「東芝の資本構成に潜む不安」を炙り出してみよう。
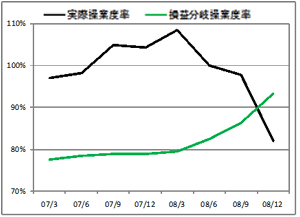
第5回
前回のコラムでは、数多くのグラフを掲載して電機メーカー各社の問題提起を行ない、シャープ型経営の“誤算”について詳述した。今回は、前回と同じくシャープ型、ソニー型、東芝型の検証をそれぞれ行ないながら、「ソニー型経営の特徴」を分析したい。なお、筆者はシャープだけでなく、ソニーや東芝の社内事情を全く知らない(このうち某社の工場見学には行ったことがあるが)。よって、これから述べる内容は筆者の勝手な解釈であり、「こうなのだろう」という推測を含んでいる点をご承知いただきたい。
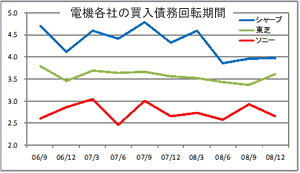
第4回
電機業界大手の2009年3月期第3四半期に係る決算短信が出揃った。これを見ると、各社がいかに不況に喘いでいるかがわかるだろう。さて、今回はそのような下衆の勘ぐりをするまでもなく、電機各社のなかでも「堅実経営」というイメージが強いシャープについて、分析することにしよう。
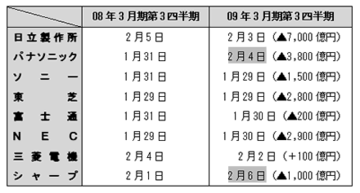
第3回
日産自動車やホンダに追撃されながらも、依然王者として揺るぎないポジションを堅持しているトヨタ自動車。だが、独自のSCP分析を用いると、外部からは死角になっている“不安の本質”が垣間見えて来る。
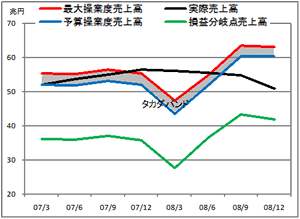
第2回
2009年3月期に対前年比で大幅な減収減益に陥る見込みのホンダは、F1からの撤退や鈴鹿8時間耐久レースへの参加見送り(マシン貸与を除く)を発表するなど、矢継ぎ早のリストラ策に取り組んでいる。トヨタ自動車や日産自動車に比べて不況への耐性が強いと言われるホンダだが、「やはり大不況の波を乗り切るのは難しいのか」といった印象を持つ人が多いだろう。しかし、何でもかんでも景気のせいにするほど、ことはそう単純ではないようである。
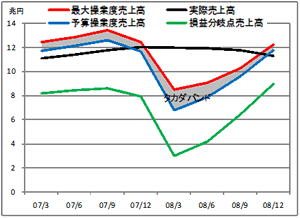
第1回
大不況の「台風の目」となっている自動車業界では、大規模なリストラが行なわれている。だが日産自動車を分析すると、「派遣切り」などの合理化策が、今後必ずしも事業の効率アップにつながらないことが予測できる。