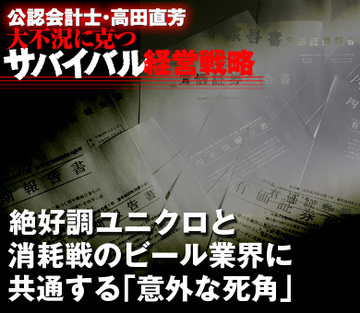高田直芳
第53回
実務の最前線で活躍する公認会計士などは全員、異口同音に「最適資本構成に、一般公式や実務解はない」という。しかし今回は、初歩的な経済学と数学を用いて、最適資本構成の一般公式を導き出していきたい。
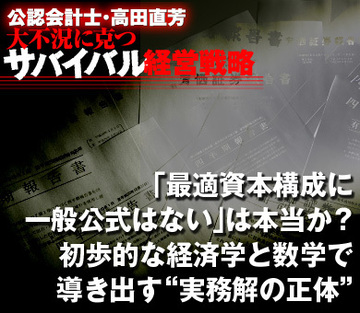
第52回
よく「完成品メーカーよりも部品メーカーのほうが収益回復力や円高耐性が強い」といった仮説を耳にする。しかしこれは本当なのだろうか。今回は完成車メーカーであるトヨタと部品メーカーのデンソー、アイシンの分析からその真実を探る。
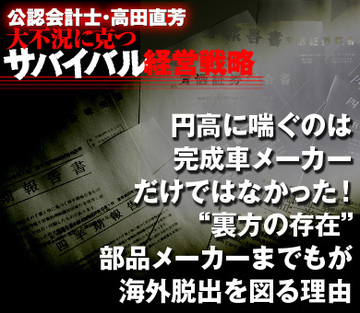
第51回
これまで大手電機メーカー5社の円高限界点を分析してきたが、今回は円高に耐性があるエレクトロニクス3社(NEC、富士通、ソニー)を分析していく。なかでも海外比率の高いソニーは円高にどこまで耐えることができるのだろうか。
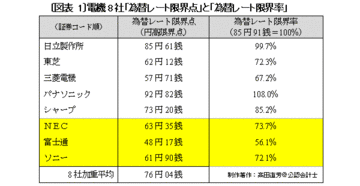
第50回
前回は電機メーカー5社の「為替レート限界点」と「最適点」の2点を導いた。今回は自動車業界の「為替レート限界点」「最適点」、さらには「ニッポン経済」というマクロ経済レベルの「為替レート限界点」「最適点」も求めてみよう。
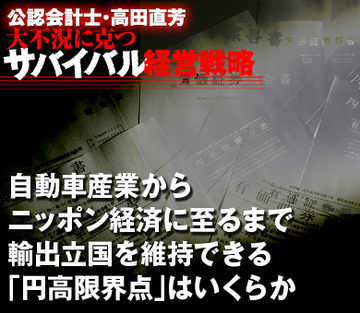
第49回
為替レートの問題に関しては、マクロ経済学の視点から様々な議論が行なわれている。しかし企業は、今日の為替相場に気を揉んでいるのではない。自社にとって、円高に耐えられる「限界点」はどのあたりまでなのか、ということを知りたいのだ。
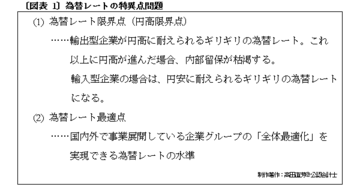
第48回
薄利多売といえば、小売・流通業界の専売特許といえるもの。しかし、製造業で該当する企業がある。それが日立製作所だ。10年3月期以降、黒字回復した同社だが、その経営戦略の実態と業績回復はホンモノなのかを探っていこう。
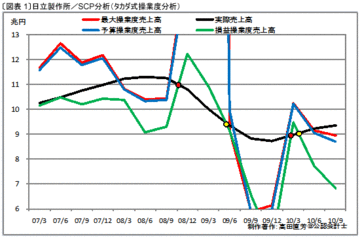
第47回
急速な円高と欧米景気の後退懸念により、先行きの見通しに不透明感を残す企業が多い。パナソニックの場合、家電エコポイントの効果もあって国内薄型テレビやエアコンの販売台数が大幅に増加したようだが、この業績回復は本物なのだろうか。
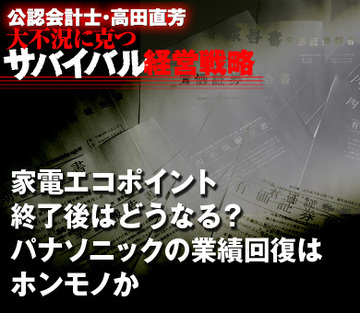
第46回
国際会計基準IFRSの適用という新たな波が押し寄せているが、その一方で「原価会計基準」は、相変わらず何ら改訂されずに仮死状態が続いている。今回は、全国100万社すべてに蔓延している「コスト管理の誤謬」をただしていきたい。
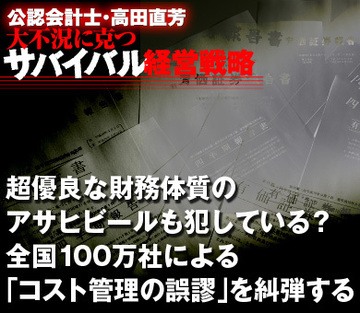
第45回
プロ野球無関心層が増加しているとはいえ、横浜ベイスターズの身売り話に驚いた人は少なくないだろう。結局身売り話は破談に終わったが、その背景には何があったのか。TBSの経営分析からその裏側を推量してみよう。
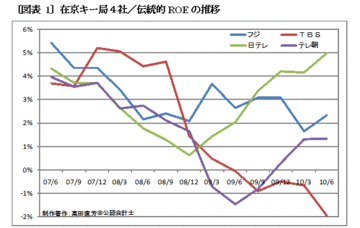
第44回
近年、ROIを社内の業績評価指標として採用している企業が多いと聞く。はたしてそれは、十分に理解された上でのことなのだろうか。そこで今回は、ROIという指標を崇める企業やマスメディアの軽挙妄動ぶりを暴いてみることにしよう。
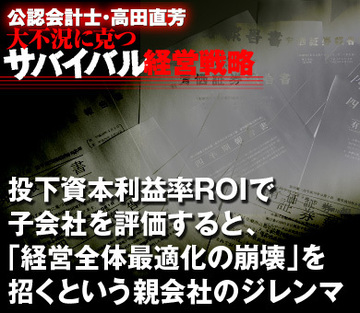
第43回
P&Gに資産規模で32倍もの差をつけられているユニ・チャームだが、その活躍には感嘆するばかりだ。しかし、もしユニ・チャームがP&Gと肩を並べる資産規模になっても、ユニ・チャームのROEが、P&Gのそれを超えることは絶対にない。
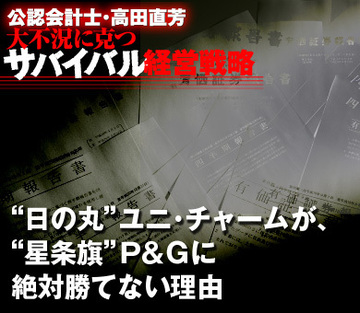
第42回
味の素を伝統的な指標で見ると、業績は不安定だ。しかし、同社への業績不安が語られることはあまりない。それは企業規模の大きさが安心感を与えるからのようだが、今回は別の視点から味の素の実像に迫りたい。
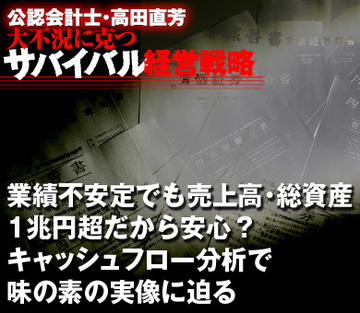
第41回
経済学というのは、「実務に役立たない」と揶揄されてきた学問という側面がある。そこで今回は、日清食品のデータを拝借して、「データ分析の裏付け」を持ったミクロ経済学の話を展開してみることにしよう。
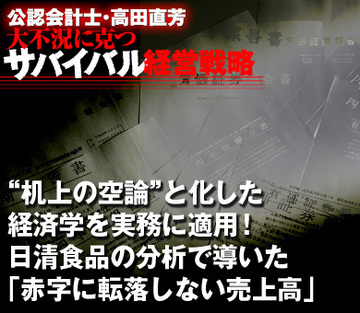
第40回
「キャッシュフロー計算書」に対して、苦手意識を持っている方は少なくない。確かに、キャッシュがどう流れているかという「事実」、すなわち「企業の意思決定過程」を読み解くのは一筋縄ではいかないが、“工夫”さえすればそれは可能だ。
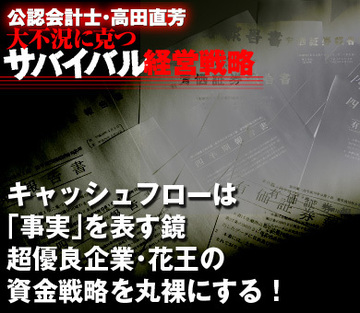
第39回
昨年は「民営化」か「民営化凍結」で揉めていた郵政問題がどう着地するかはさておいて、日本郵政という「株式会社」がどういう特徴を持っているのか、今回は決算書に現われた数値のみをつかい、筆者オリジナルの工夫を加えて解析してみよう。
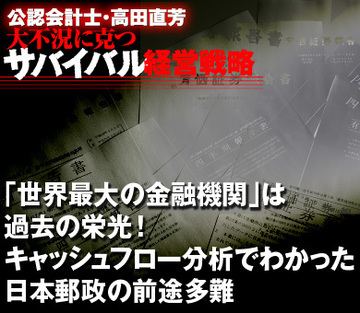
第38回
企業が行う「業績予想」は予測の精度が試される、まさに「踏み絵」だ。今回は業績予想の話を突破口にして、電機メーカー8社の決算データから「各社の特徴」を明らかにし、「電機業界内の序列化」に挑戦しよう。
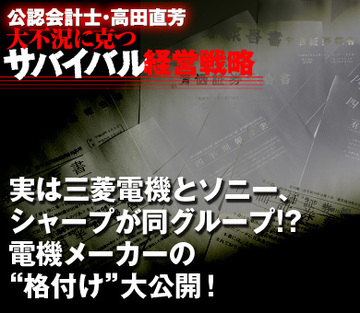
第37回
ニッポンの情報通信市場は「ガラパゴス化」し、国内市場は飽和状態にあるとよく言われる。したがって、ソフトバンク・ドコモ・KDDIの業績は、長期低落傾向をたどり凪の状態で推移すると思われたが、この1年間は惨敗続きだった。
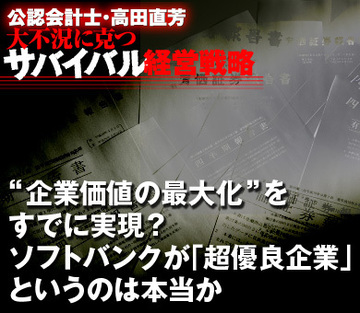
第36回
参院選が近づき、消費税増税に関する議論が高まっている。今回は、この不況のなかで地方の中小企業が直面している悲哀に、著者の理論と経営指標を加味しながら、消費税増税がいか憂鬱の種になるか、説明していきたい。
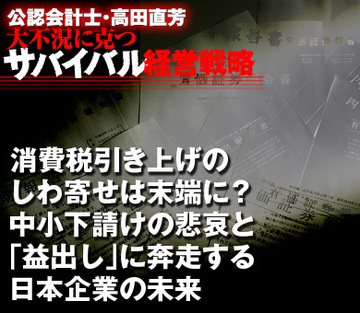
第35回
国際会計基準IFRSの適用が検討されているなか、日本基準とIFRSの間に大きな軋轢が生じている。2006年まで実質的に鎖国状態にあった日本基準はIFRSと歩調を合わせきれず、「無用の長物」が生まれているというのだ。
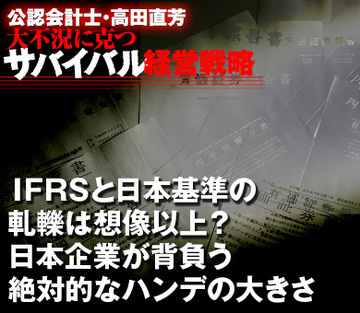
第34回
企業が成長する過程には、「季節的な変動」と「一過性のブーム」が襲いかかり、成長の阻害要因ともなる。今回は、これらの現象をユニクロ、アサヒビール、キリンビールの決算データを使って検証してみよう。