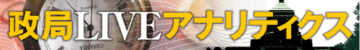上久保誠人
第20回
政策立案過程から「官僚支配」を排除することは日本政治の長年の課題である。今回は、それに対する回答である自民党の「首相官邸主導体制」と民主党の「政治任用制」を批判的に紹介し、私の代替案を提示したい。
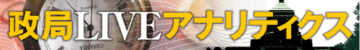
第19回
鳩山一郎元首相の没後50年祭が開かれた。孫の鳩山由紀夫民主党幹事長と鳩山邦夫総務相は将来の連携の可能性を示唆したという。今回は、本年度予算成立後の政局の焦点として、鳩山兄弟に注目したい。
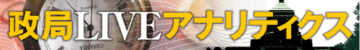
第18回
麻生太郎首相がサハリンを訪問し日露首脳会談が行われた。日本は本来ロシアに対して強い交渉力を持っているはずだが、今回の首脳会談ではそれを生かせなかった、というのが私の主張である。
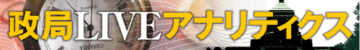
第17回
政府・与党内で「一院制導入論」が浮上している。小泉元首相がこれを自民党の選挙公約とすべしと主張し、麻生首相も国会制度見直しの必要性に言及した。しかし私は、参院は不要ではないと考える。
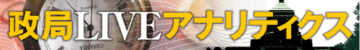
第16回
麻生太郎首相は、税制改革関連法案での「11年度の消費税率引き上げの明示」にこだわった。景気対策を最重要視している麻生首相が、なぜ次期衆院選にも悪影響が懸念される「増税時期の明示」に固執したのか。
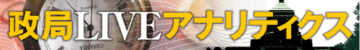
第15回
「オバマ人事」の特徴は、議会や行政トップ経験者を多数入閣させた実務重視の即戦力政権だということだ。多少の意見の相違には拘らず、強い個性と能力、そして既に高い実績を持つ人物を閣僚に起用した。
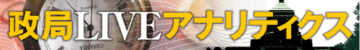
第14回
「政界再編」という言葉が政治家の口から発せられるようになった。今年は20年に渡る日本政治の対立「政界再編(による保守政権の存続)」VS「政権交代(のある民主主義の実現)」が決着する重要な1年となる。
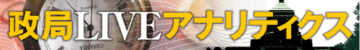
第13回
今回はまず、なぜ麻生首相が苦境に陥ったのかについて論じる。それは単に失言や政策の迷走というより、麻生首相の就任直後の初動の誤りにあると考える。次に、「反麻生」の鍵を握る政治家についても書いてみたい。
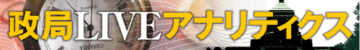
第12回
私は英国に住んでいた頃、保守派の主張の是非はともかく、その態度に違和感があった。なぜなら今回の作文のような「歴史認識問題」について、保守派の「声高な主張」と欧米での認識が全く異なっていたからだ。
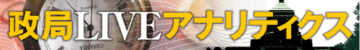
第11回
麻生首相がG20の「首脳外交の場」で存在感がなかった理由は、「資金援助」が強い外交カードとなるのは、それを与える直前までで、そのカードは援助を与えた瞬間に消滅するものだからだ。
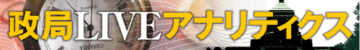
第10回
日米関係というのは、日米2ヵ国だけではなく、その他の国々も加わった国際社会のパワーゲームに影響される。従って、今回は日米2ヵ国関係の分析は他の識者に任せて、米国以外の日本外交の課題を考えてみたい。
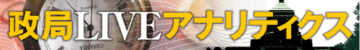
第9回
麻生首相の景気・金融危機対策は、今後の政局の新たな対立構図を浮き上がらせたように思う。そこで、解散・総選挙の時期ばかりが焦点となっている世の中の空気をあえて読まず、その対立構図を明らかにしてみたい。
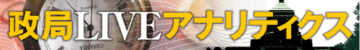
第8回
麻生首相が「自分の手で経済問題を解決したい」という強い意志を持つことは悪くない。ただ、強い意志を持っている割には、麻生首相の行動は稚拙で戦略性がない。
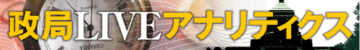
第7回
私は、総理・総裁への就任は麻生さんにとって「茨の道」と書いてきた。来るべき総選挙後、自民党、公明党、民主党が獲得した議席数によってどのような行動を取るかを通じて、麻生さんの「茨の道」を考えてみたい。
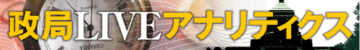
第6回
福田首相が辞任した時、多くのジャーナリスト・評論家が厳しく批判した。しかし私は少し福田首相が可哀そうな気がした。なぜなら政権誕生時、同じ人たちが首相の「経験」と「安定感」を評価していたからだ。
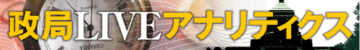
第5回
北京五輪が終了し、よくも悪くも中国の「大国化」を強烈に意識させられた。日本はこの隣国とどう付き合っていくべきなのかを考えさせられた日々であった。今日は、日中関係について思うことを書いてみたい。
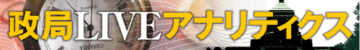
第4回
民主党に対する評価が的外れなのは、衆議院ばかりを見ているからだ。マスコミが取り上げるのは衆院議員の話ばかりである。「衆参ねじれ国会」では民主党がウンと言わないと、なにも決められないからだ。
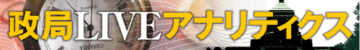
第3回
福田首相が内閣改造と自民党執行部人事を断行した。福田首相は、この人事を政権浮揚につなげたい考えだが、思惑通りにいくかどうか評価してみたい。
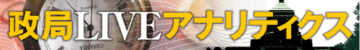
第2回
日本が援助した国に対して「日本への支持」を求めた時、「まだまだ援助が足りないので」と渋られたらどうだろう。それに日本が怒っても、その国は困らない。既にお金を貰っているからだ。
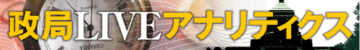
第1回
米国が北朝鮮の「テロ支援国家指定解除」の手続きに入ることを決めた。これによって日本人拉致問題の解決が遠のくと懸念されている。しかし私はむしろ「拉致問題」は解決に向けて進展する可能性があると思う。