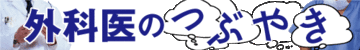柴田 高
第36回・最終回
2009年は弱毒性新型インフルエンザのパンデミックが発生し、2011年には3.11東日本大震災が発生した。その派生による大津波や原発事故に対しては、幾度となく“想定外”という言葉が使われていたので記憶に新しい。
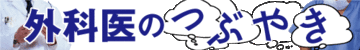
第35回
数ヶ月前、ある証券会社の担当者の方が数名で私の会社を尋ねてこられた。「このたび我が社と監査法人が主催する経営セミナーで、外科医でもあった社長にご講演をいただけないかと思いまして」といきなりの講演依頼の申し出であった。
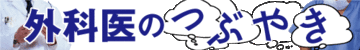
第34回
部門間の壁がなくなり、一元化した診療工程により医師の指示も統一されミスやロスが低減した。医療にかかわらず、組織活性のレシピーは業務工程の可視化と課題の共有なのかもしれない。
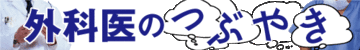
第33回
翌日、北京で下痢止め薬、日本市場シェアトップの『正露丸 糖衣A』の新発売セミナーをひかえた私は東京駅から成田エキスプレスに飛び乗り車窓を眺めていた…。
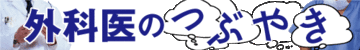
第32回
先日、宮城県のある大学で、産学協同の震災支援センター立ち上げの開所式に私は参加した。式典が終わると同時にサイレンが大学構内で鳴り響く。
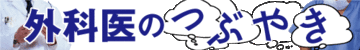
第31回
私の博士論文をご指導いただいたO先生が大阪の病院へ戻ってこられたので、先日、第二外科、酵素化学研究室の同窓会が開かれた。
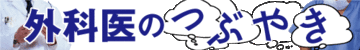
第30回
東京・五反田にある会社ビルの一室で、来期の事業計画策定のため、熱い議論を交わしていた。思いのたけを伝えた瞬間、めまいを覚えたかのような今までにない大きなふらつきを感じた。しかし、そのふらつきは、体全体に広がり、会議に参加していた私を含めた3名ともが「地震だ」と叫んだ。
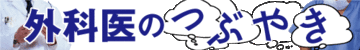
第29回
医療界の“大変”といえばルールや方法が変わることでもよく起こる。最近のルール変更といえば新臨床研修医制度である。
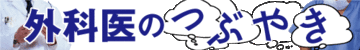
第25回
先月、私は数年ぶりに学会のワークショップの発表者演壇に立った。いままでは外科学会であったが、今回は感染症学会であった。
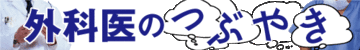
第24回
ペットを飼うこと、会社を経営すること、国を動かすことはいずれも、命を託される医者の感覚に似ていると思う。人の命や人の人生を託される仕事は責任重大で大変なことが多い。
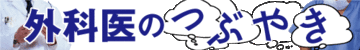
第23回
“診断はサイエンス、治療はアート”。この言葉は職場の先輩の先生の受け売りだ。最近、治療がうまくいかなかったことを理由に訴訟で争われることが多い。しかし、現代医療における治療、特に手術はアートの域をいまだ脱していない。
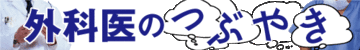
第22回
外科医が登場するドラマや映画は好んでよく見ていたが、近頃は“現実はこんなもんじゃない”と思うことも多くあった。堤真一主演の映画「孤高のメス」を観た後は、感動と外科医としての思いの乖離が心に引っかかっていた。
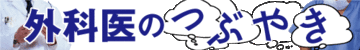
第21回
医者は患者を選べないが、患者は医者を選ぶことができる。医療の結果はなかなか予測できるものではないが、医者の“ご縁”で決まることが多い。
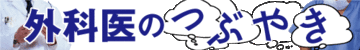
第20回
2010年春、宮崎県で広がった口蹄疫は人には感染しないというものの、日本の畜産業界に大打撃をもたらし、その経済的損失は計りしれない。さまざまな感染性微生物がわれわれのすぐそばまでやってきて、われわれ人間を脅かしながら共存していることに気づかされる。
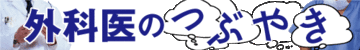
第19回
新築前の旧T病院は鉄道沿いにあり、本当に古く、暗い病院であった。ある日、ふと新聞の夕刊を見ると、「私はこんな病院で死にたい。産科のある病院で」というエッセイが掲載されていた。
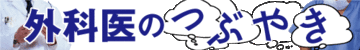
第18回
外科医が一番やられるのが首と腰だが、知り合いの話を聞いて外科医だけでなくパソコンをよく使う経営者の方々も外科医と同じような悩みがあることに気づかされた。
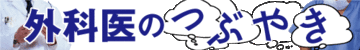
第17回
「150年前までの外科は暗黒の時代でした。手術は耐え難い痛みが伴うもの、傷は化膿しなければ治らない。おなかの腹膜を開ければ必ず死ぬ。たかが虫垂炎でもほとんどの方は死亡しました。それが医学の常識でした」。医療の暗黒時代を知るだけで、今の世に感謝すると同時に幸福を感じる。
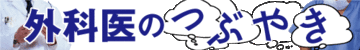
第16回
中学生だった頃、父の「人間が社会をつくる」という言葉の本当の意味が理解できなかった。しかし、最近はよく理解できる。ビジネスで成功をおさめなくとも、コツコツと徳を積むだけでも人々が集まり、人間社会が形成されることを実感させられる。
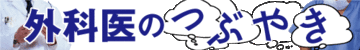
第15回
手術は人間がやるもので絶対ではない。「安全第一」に取り憑かれて誤った療法を選んでしまう患者さんもいるだろうが、医療従事者だけは取り憑かれた判断をしてはいけないと思う。
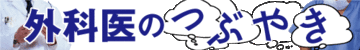
第14回
ある肝ガンの研究会で、簡単で出血がなく、画期的な治療が発表され感激した。その後消化器外科に異動した私は、ある日肉屋で大きなレバーに目が留まった…。