伊東眞幸
最終回である本稿では、DXの元来の目的である顧客への新たな価値創出について、議論を展開したい。地方銀行がコロナ禍における中小企業の事業継続支援に加え、デジタル化支援によって生産性向上に寄与することは極めて重要である。そのとき、地銀は対応できるだろうか。

今回はDX人材の確保について議論を展開したい。DXは、企業が自ら変革を主導して初めて達成されるものであり、DXを推進するための人材についても、外部のベンダー等に任せるのではなく、企業が自ら主体的に確保するべきである。

今回は、DX推進上必須のシステム開発手法である「アジャイル」と、DX推進を阻害する恐れのある既存システムの「技術的負債」について議論を展開したい。
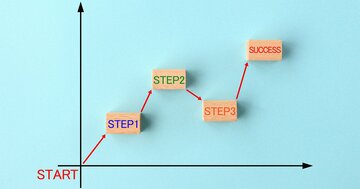
地銀がDXに取り組む際に必要なのは、これまでのビジネスを顧客指向のマーケットインの発送で変えていくことだ。そのためには、データドリブンであること大前提。しかし、地銀は顧客のフィードバックデータの把握・検証について十分に行えているかというと、必ずしもそうではない。

多くの地銀で、矢継ぎ早にデジタルトランスフォーメーション(DX)推進策を打ち出している。そんな中で、2020年12月に経済産業省の研究会が「DXレポート2」 をとりまとめた。これは「DX推進の必読の書」と言っても過言ではない。
