峰尾洋一
トランプ政権の組織運営は「米国第一」のビジョン実現など、変化に対応する「リード」が先行し、計画立案や組織構築などの複雑さに対応する「マネジメント」が追い付かない状況だ。関税政策の二転三転や移民送還などの実績が上がっていないのは、その「欠落」を如実に示す。

トランプ政権発足から3週間が経過したが、不法移民送還や環境政策転換は事前に周到に練られた形跡がある一方で、関税引き上げなどでは政権内部やトランプ氏の考えにも振幅があるようだ。トランプ政策は当面、世界の最大の不安定要因だが、侮れないのは「常識による革命」を掲げた国民目線の路線は米国内の支持を得やすいことだ。

#13
2025年の世界経済を左右するのは米国の新トランプ政権の政策だ。減税や新エネルギー政策、関税、不法移民規制といったドナルド・トランプ氏が掲げた政策は米国経済にどんな影響を与えるのか。トランプ政策はどこまで実現し、立ち止まる要素はないのか。日本はどう対処すべきなのか。25年の米国経済の先行きを展望する。
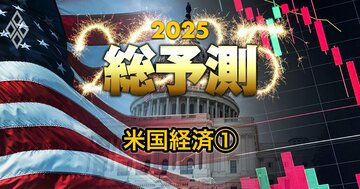
米大統領選挙で勝利したトランプ前大統領だが、公約や主張をどう具体化していくかは曖昧だ。第2期政権は1期目と経済環境が違い、民主党政権への攻撃材料にしたインフレ問題への対応を迫られ、官僚組織の“従順化”を狙う公務員制度改革では大混乱が懸念される。

米大統領選で民主党の大統領候補になったハリス副大統領は若い世代や女性、マイノリティーの支持を得やすい強みがあるが、勝敗の鍵となる激戦州での白人労働者の認知度は高くない。選挙戦では高齢・白人のトランプ氏と若手で非白人・女性という二人の属性の違いが影響する要素が強まった。

大統領選テレビ討論会で高齢不安が露呈したバイデン大統領だが、より深刻なのは民主党の伝統的支持基盤の若年層や黒人層の離反だ。社会福祉後退など期待した経済政策の未実現やガザ侵攻のイスラエル支援への反発、さらには若者層の支持を得る党内左派との確執が再選へのネックになっている。
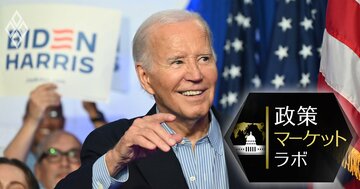
米大統領選挙は「バイデンVSトランプ」の再戦になり、外交や移民、気候変動問題などでの政策の違いは大きいが、バイデン氏は高齢問題、トランプ氏は刑事訴追問題という不安要素を抱え、また自党内のまとまりが弱いという類似点がある。これらの問題克服がお互い勝利の鍵になる戦いだ。

米国の個人消費の動向を占う11月第4金曜日の大規模セール「ブラックフライデー」の結果は、ネット通販の消費額が前年比2.3%増の91億2000万ドル(約1兆2700億円)で、伸び率は事前予想の1%を上回った(米アドビ調査)。在庫増による値引き拡大が、物価高を警戒していた消費者の消費意欲を刺激したという。これにとどまらず、米国在住の筆者は、「アメリカ国民は値上げに怒っているものの、買い物を減らすほどではなく、むしろ買い物し続けることによって更なるインフレを招いているのではないか」と説く。いったいどういうことか、この仮説を、複数のデータを見つつ明らかにしていこう。
