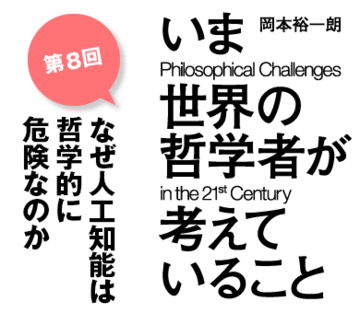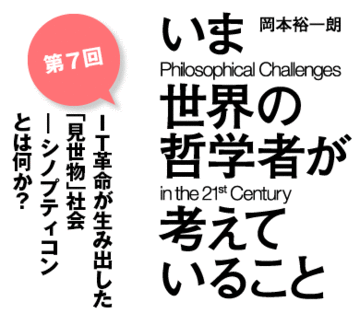世界の哲学者はいま何を考えているのか――21世紀において進行するIT革命、バイオテクノロジーの進展、宗教への回帰などに現代の哲学者がいかに応答しているのかを解説する哲学者・岡本裕一朗氏による新連載です。いま世界が直面する課題から人類の未来の姿を哲学から考えます。9/9発売からたちまち重版出来の新刊『いま世界の哲学者が考えていること』よりそのエッセンスを紹介していきます。第9回はバイオテクノロジーの発展がもたらす人体改変の衝撃とその思想的意義を解説します。
「ポスト・ヒューマン」の衝撃
今回は、現代におけるバイオテクノロジーの発展が、私たち「人間」をどこへ導くのか、考えてみましょう。1950年代に、ワトソンとクリックがDNAの「二重らせん」構造を解明して以来、生命科学と遺伝子工学が飛躍的に発展しました。現在では、自然界に存在しなかった生物でさえ、人為的に作製できるようになったのです。こうして、BT(バイオテクノロジー)革命と呼ばれる時代が到来しました。
今まで、バイオテクノロジーの向かう先は人間以外の生物でした。遺伝子組み換えやクローン動物の作製にしても、基本的には人間以外の生物が対象とされてきました。人間を例外としたうえで、人間のために他の生物種を遺伝子工学的に操作するわけです。こうしたバイオテクノロジーを人間に応用したとき、何が生じるのでしょうか。

あらためて言うまでもありませんが、人間もまた生物種の一つ、すなわち哺乳類に属していますから、人間に対する遺伝子操作は原理的には可能でしょう。1970年代には、いわゆる「試験管ベビー」が誕生することで、受精卵に対する操作も可能になっています。また、20世紀末から「ヒトゲノム計画」が始まりましたが、21世紀の初めには予想よりも早く完了し、今では人間のDNA情報がすっかり解読されています。とすれば、人間に対する遺伝子操作が日程に上るのも、それほど遠くないと思われます。
実際に2015年、中国で人間の受精卵に「ゲノム編集」を行なった、という報告が発表されました。テクノロジーの論理からすれば当然のことですが、これはいったい何を意味するのでしょうか。また、このテクノロジーは、私たち人間をどこへ連れていくのでしょうか。こうした事態を、私たちはどう考えたらいいのでしょうか。
今日において、バイオテクノロジーが「人間」にとって、どんな意味をもつかを考えるために、21世紀初め、アメリカで展開された論争を取り上げることにしましょう。人間の遺伝子組み換えが、もはやSFの世界ではなくなり、その是非が本格的に議論されるようになったのです。
発端となったのは、ほぼ同時期に発売された二つの著作です。その一つは、政治学者フランシス・フクヤマが書いた『人間の終わり―バイオテクノロジーはなぜ危険か』(2002年)です。その中でフクヤマは、「ポストヒューマン(人間以後)」という言葉を使いながら、バイオテクノロジー革命について、次のように展望しています。
本書の目的は、(中略)現代のバイオテクノロジーが重要な脅威となるのは、それが人間の性質を変え、私たちが歴史上「ポストヒューマン(人間以後)」の段階に入るかもしれないからだ、と論じることである。これが重要なのは、人間の本性(自然)が存在し、しかも意味ある概念として存在し、そのおかげで一つの種としての私たちの経験が安定的に続いてきたからである。
こう述べるとき、フクヤマが展開する論拠は、必ずしも明快とは言えません。というのも、人間の遺伝子組み換えがなぜ悪いのか、はっきりしないからです。けれども、彼がバイオテクノロジーの未来を「ポストヒューマン」と表現したのは適切だと思います。フクヤマは、この「ポストヒューマン」に反対して人間の尊厳を擁護するのですが、残念ながら、その議論は成功していません。フクヤマとは逆に、遺伝子組み換えが人間の改良につながる、と考えることもできるはずです。
この視点から議論を展開したのが、科学者のグレゴリー・ストックです。彼は、フクヤマの本とほぼ同時に、『それでもヒトは人体を改変する―遺伝子工学の最前線から―』(2002年)を出版しました。フクヤマとストックでは、バイオテクノロジーに対する態度がまったく違っています。ストックは、バイオテクノロジーの成果を積極的に取り入れ、「費用、安全性、有効性」の条件がクリアされるならば、人間に対する遺伝子組み換えも賛成すべきだと主張します。