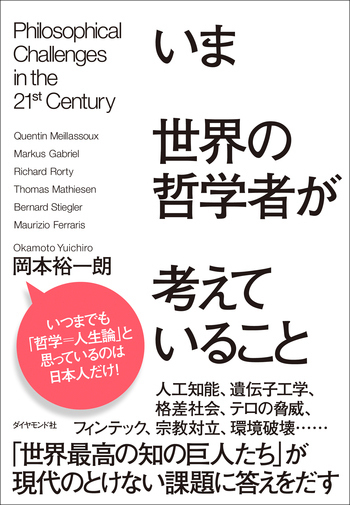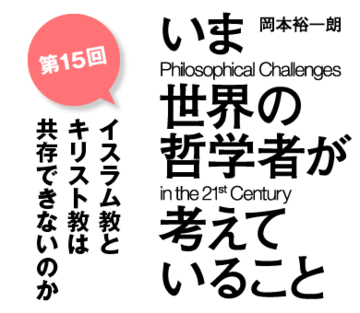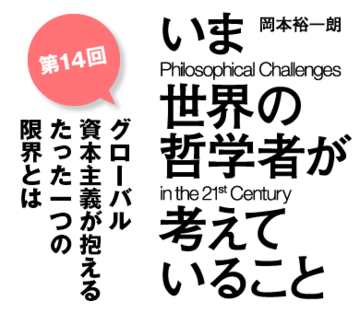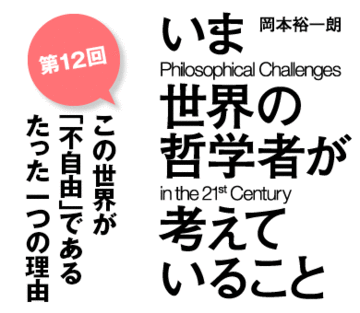無神論者ドーキンスの宗教批判
ドーキンスによると、宗教が主張していることは、二つに大別することができます。一つは神が存在するという「神仮説」であり、もう一つは道徳の根拠は宗教にあるという「道徳仮説」(この表現は筆者)です。そこでまず、「神仮説」と、それに対するドーキンスの結論を見てみましょう。
私は神仮説をもっと弁護のしようがある形で定義したいと思う。すなわち、宇宙と人間を含めてその内部にあるすべてのものを意識的に設計し、創造した超人間的、超自然的な知性が存在するという仮説である。(中略)宗教の事実上の根拠─神がいるという仮説─はもちこたえることができない。神はほぼまちがいなく存在しない。これが、本書のこれまでのところの結論である。
このように、神が存在するという宗教の原理的な仮説を科学的に反論した後、ドーキンスは「道徳仮説」について検討していきます。というのも、神が存在しないとしても、宗教は道徳にとって重要である、と主張できるからです。じっさい、グールドのNOMA原理でも、「道徳的な価値」の領域は宗教のマジステリウムとされていました。
ところが、ドーキンスによると、非道徳的で残虐な行為が宗教にもとづいて繰り返されてきたのです。ドーキンスは、聖書やコーランなどを具体的に引用しながら、宗教にもとづく非道徳的な行為を数多く提示し、そこから宗教が道徳的であることを強く否定するのです。それに反して、宗教がなくても、人間は道徳的な行動をするとドーキンスは考えています。
こうしたドーキンスの宗教批判が、キリスト教やイスラム教の原理主義的活動に触発されたことは、ドーキンス自身も明言しています。その意味では、ドーキンスの宗教批判は、「ポスト世俗化」する現代社会において、世俗化の意義をあらためて復権しようとする運動だと理解できるでしょう。彼の宗教批判がどこまで影響力をもつのか分かりませんが、『神は妄想である』が世界中で150万部も売れたことから考えると、科学と宗教の問題が、現代でさえも重要なテーマであることは間違いありません。
ドーキンスの『神は妄想である』と同じ年、世界的にも著名なアメリカの哲学者ダニエル・デネットが『解明される宗教』を出版しました。ドーキンスが、宗教と科学を対立させて、科学の立場から宗教を批判・解体したとすれば、デネットのやり方はまったく異なっています。デネットは、ドーキンスのように宗教を非難することはありません。
しかし、宗教が重要であると明言するにもかかわらず、デネットの書物は、ある意味でドーキンス以上に宗教批判の本である、と言えます。原題(Breaking the Spell)の中に登場する「呪縛(spell)」は、音楽などに熱狂したり、麻薬中毒やアルコール中毒、児童ポルノ中毒になった人が、はまり込んでいる陶酔感をも意味しています。したがって、「呪縛を解く」は「陶酔をさます」でもあるわけです。宗教に陶酔している人々に対して、酔いをさますように解き放つことが、デネットのねらいです。
では、どうすれば「宗教の陶酔からさます」ことができるのでしょうか。この書でデネットがとった方法は、宗教を多くの自然現象の一つと考えて、それを科学的に探究することにあります。つまり、宗教と科学を対立させるのではなく、宗教という「自然現象」を科学によって解明するわけです。デネットは、彼のやり方を次のように表現しています。
気をつけてほしいのは、たとえ神が現実に存在し、神が私たちの愛すべき創造者であり、知的で意識的な創造者であることが、たとえ真実であったとしても、それでもやはり、宗教それ自体は、諸現象の複雑な集合体として、完全に自然的な現象であるということである。
たしかに、宗教が自然現象であるとすれば、デネットの言うように、自然科学の方法にもとづいて完全に解明できるかもしれません。こうした解明を行なうために、デネットは進化生物学的視点に立ち、ドーキンスが提唱した文化的複製子「ミーム」という概念を利用しています。
しかしながら、こうした方法によって、キリスト教やイスラム教の原理主義者が、じっさいに宗教の呪縛(陶酔)を解く(さます)かどうかは疑問が残ります。というのも、宗教を自然現象として科学的に解明することができるのか、それ自体が問題だからです。デネットの意図は理解できるとしても、はたして宗教を自然科学的に解明できるのでしょうか。