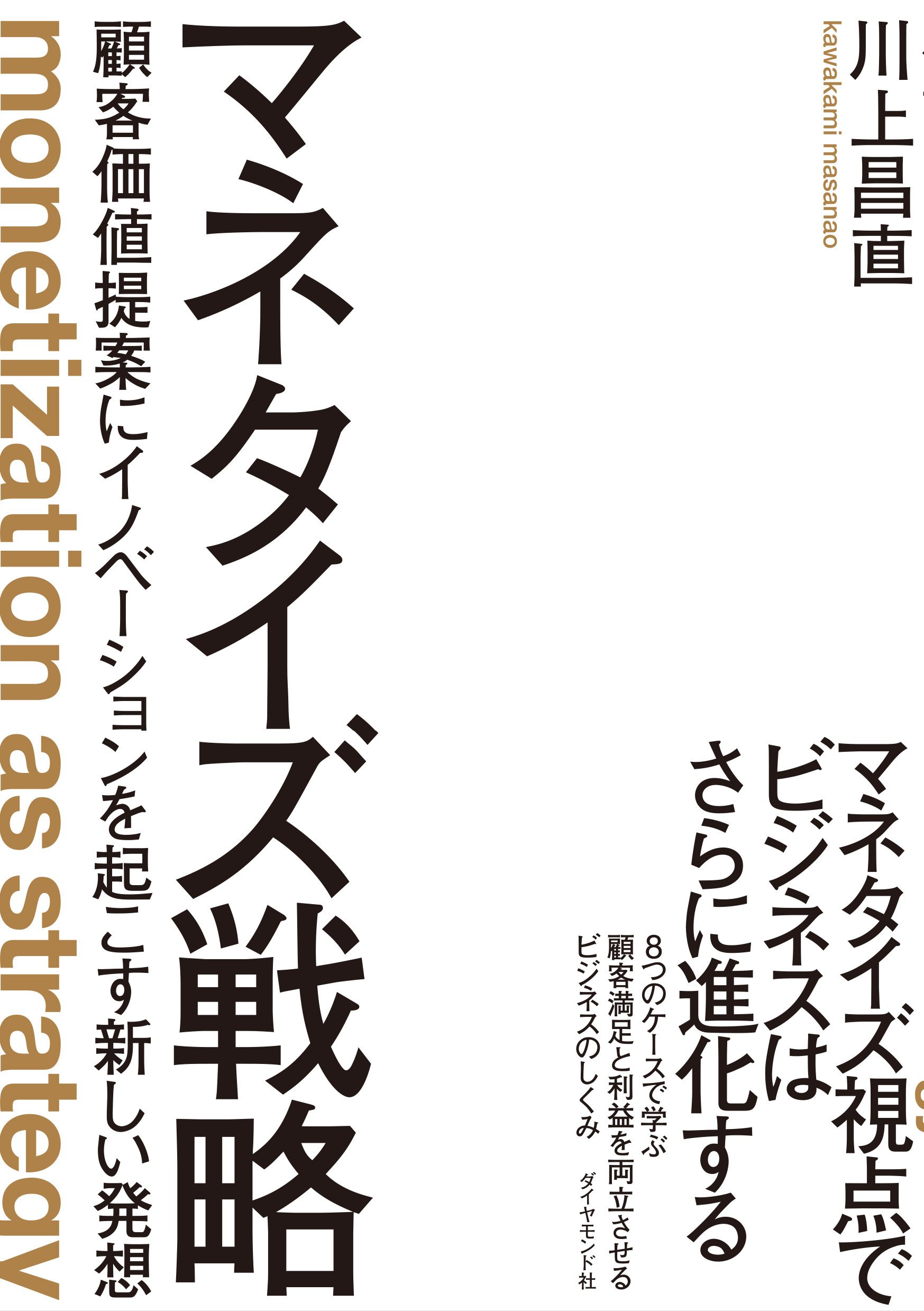ビジネスモデルとは、顧客を喜ばせながら、同時に企業が利益を得る仕組みのこと。経営学者の川上昌直氏は、最新刊『マネタイズ戦略』で、マネタイズの視点を取り入れることで、顧客価値提案に画期的なブレークスルーを起こせることを解説しています。今回から登場するのは、放送作家の樋口卓治さん。かつて『森田一義アワー 笑っていいとも!』『ココリコミラクルタイプ』『学校へ行こう!MAX』など数々の番組に携わり、現在も、『ぴったんこカン・カン』『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』など多数の人気番組を手掛ける超売れっ子放送作家です。そのマネタイズ戦略とは?
 樋口卓治さんと川上昌直さん。樋口さんのオフィスにて。
樋口卓治さんと川上昌直さん。樋口さんのオフィスにて。
「街歩き」的な、気楽に見られる番組が増えた
川上 樋口さんは、人気バラエティ番組を数多く抱える放送作家として活躍されていますが、何十人ものスタッフがかかわるテレビ番組で放送作家が具体的にどんな仕事をしているのか、知らない人は多いと思います。実際の仕事はどういうものなのか、まずはそこから教えていただけますか。
樋口 放送作家というのは、番組の企画や構成を考えたり、出演者のセリフやナレーションを書いて台本を作ったりということをやっています。各番組には、最終決定権のあるプロデューサーや総合演出と呼ばれる人がいて、彼らから、例えば「今度、金曜20時の番組を任されることになりました。樋口さん、手伝ってもらえませんか?」などと声がかかって初めてメンバーに加わります。
川上 注文がくるわけですね。
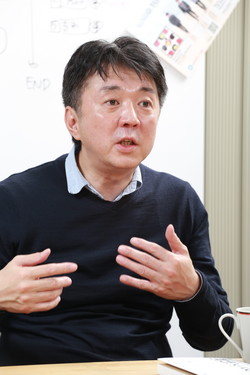 樋口卓治(ひぐち・たくじ) 1964年、北海道生まれ。放送作家。24歳のとき古舘プロジェクトに入社。放送作家のトップクラスであり、現在も十数本のレギュラー番組を抱える。これまでに手がけた主な番組に「フルタチさん」「トーキングフルーツ」「笑っていいとも!」「ヨルタモリ」「金スマ」「ぴったんこカンカン」「Qさま!!」「池上彰そうだったのかニュース」「お願いランキング」などがある。TBSとフジテレビの番組を多数手がける。素人を生かす構成や日常的なシチュエーションが得意。2012年『ボクの妻と結婚してください。』で小説家デビュー。
樋口卓治(ひぐち・たくじ) 1964年、北海道生まれ。放送作家。24歳のとき古舘プロジェクトに入社。放送作家のトップクラスであり、現在も十数本のレギュラー番組を抱える。これまでに手がけた主な番組に「フルタチさん」「トーキングフルーツ」「笑っていいとも!」「ヨルタモリ」「金スマ」「ぴったんこカンカン」「Qさま!!」「池上彰そうだったのかニュース」「お願いランキング」などがある。TBSとフジテレビの番組を多数手がける。素人を生かす構成や日常的なシチュエーションが得意。2012年『ボクの妻と結婚してください。』で小説家デビュー。
樋口 そうですね。それで金曜20時台の時間帯を、もし商店街に見立てるとしたら、どんな人たち(視聴者)が商店街を行き来しているのかなと考えます。それで、その人たちがどんなお店なら立ち止まるのか、好んで入ろうとするのかは、これまでの30年の経験値という“土地勘”があるので、だいたいわかります。それをもとにあれこれ考えて、会議の場で意見を言ったり、より面白くするためのアイデアを出すなどして番組が出来上がっていきます。
川上 なるほど。ネットをはじめ、多様なコンテンツを見ることができる今、放送作家の立場から見て、テレビ番組の作り方に、何か変化を感じることはありますか。
樋口 ありますね。テレビが元気で視聴者が品揃えを求めていた時代は、企画性のある尖った番組が受け入れられました。そのときは、僕のほうから企画を売り込んだこともありました。企画性のある番組ということでいうと、15年ぐらい前の雑学を紹介する『トリビアの泉~素晴らしきムダ知識~』(フジテレビ系)じゃないでしょうか。僕がやったわけではないですが。
川上 人気の番組でしたよね。
樋口 でも、ご存じのとおり、ネットが普及して以降は、10人が1つのチームになってクイズに答えるとか、ひな壇に多くの芸能人が座るなどの構えずに気楽に見ることができる番組が増えてきました。
川上 環境や状況が変わり、それに伴い視聴者が求める内容も変化したということですね。
樋口 そうですね。今の視聴者は求めてはいないと思うので、見やすい番組、途中からでも見られる番組が見やすい。つまり、“イヤじゃない番組”なんです。今って、どのチャンネルを回してもそういう番組が多いと思いませんか?
川上 言われてみると、確かに。誰もがほどほどに楽しめて“ながら見”できる番組が多いのかも……。でも、そうなると、台本の作り方も昔とは変わってきますよね?
樋口 そうですね。昔のバラエティやコント番組は、作り込んだ台本をもとに芸人さんと会議を重ねてブラッシュアップして尖らせたものを完成させました。でも、今は、ある街のA、B、Cのお店に行くという筋書きが多くなりますから、最終目的地に到着するまでの緻密な台本ではなく、ポイントを箇条書きする方が出演者もやりやすいんです。
川上 じゃあ、台本書くのもラクになったということですね(笑)。
樋口 そうかもしれないですね。ということは、その台本は、僕が書いても若手にメモらせても大差のないものだということです。だから、番組によっては、いわゆる台本は書かないこともありますね。でも、ラクになった分、他のことに時間を割きます。完成したVTRの試写をして直し部分を決めるとか、何を撮り足そうか決めるとか……。
視聴率は、もはや正しいものさしではない
 川上昌直(かわかみ・まさなお)博士(経営学)兵庫県立大学 経営学部 教授 ビジネスブレークスルー大学 客員教授「現場で使えるビジネスモデル」を体系づけ、実際の企業で「臨床」までを行う実践派の経営学者。初の単独著書『ビジネスモデルのグランドデザイン』(中央経済社)は、経営コンサルティングの規範的研究であるとして第41回日本公認会計士協会・学術賞(MCS賞)を受賞。ビジネスの全体像を俯瞰する「ナインセルメソッド」は、さまざまな企業で新規事業立案に用いられ、自身もアドバイザーとして関与している。また、メディアを通じてビジネスの面白さを発信している。その他の著書に『儲ける仕組みをつくるフレームワークの教科書』(かんき出版)、『ビジネスモデル思考法』(ダイヤモンド社)、『そのビジネスから「儲け」を生み出す9つの質問』(日経BP社)など。 http://masanaokawakami.com
川上昌直(かわかみ・まさなお)博士(経営学)兵庫県立大学 経営学部 教授 ビジネスブレークスルー大学 客員教授「現場で使えるビジネスモデル」を体系づけ、実際の企業で「臨床」までを行う実践派の経営学者。初の単独著書『ビジネスモデルのグランドデザイン』(中央経済社)は、経営コンサルティングの規範的研究であるとして第41回日本公認会計士協会・学術賞(MCS賞)を受賞。ビジネスの全体像を俯瞰する「ナインセルメソッド」は、さまざまな企業で新規事業立案に用いられ、自身もアドバイザーとして関与している。また、メディアを通じてビジネスの面白さを発信している。その他の著書に『儲ける仕組みをつくるフレームワークの教科書』(かんき出版)、『ビジネスモデル思考法』(ダイヤモンド社)、『そのビジネスから「儲け」を生み出す9つの質問』(日経BP社)など。 http://masanaokawakami.com
川上 ところで、テレビと言えば、視聴率という指標が欠かせませんよね。この業界の長い樋口さんにとっては常識的な話だと思いますが、無料視聴できる地上波のテレビ放送のマネタイズは、視聴者からは課金せずに、テレビCMを提供するスポンサー企業という第三者から儲けています。
樋口 そうですね。
川上 テレビは、視聴者が支払う金銭の全部をスポンサー企業が肩代わりしてくれる、三者間市場と言われるマネタイズで成り立っています。そうなると、当然ながらCM料を支払うスポンサー企業は、番組の人気度を計る視聴率を重視しますよね。あの数字は、リアルタイムで観てはいない録画された数はカウントされないのですか?
樋口 ええ、視聴率は、オンエアのみの調査ですので、録画は入ってないです。僕の中では、視聴率という指標は正しいものさしとは必ずしも言えなくなってきています。でも、視聴率は分析します。1分ごとの推移をグラフで見たりしています。その中で若い人たちは少ないですね。そういう意味で正しいものさしとは言えなくなっています。
川上 僕が今回書いた『マネタイズ戦略』で取り上げている事例の一つに、2013年に創刊された『LDK』という雑誌があります。30~40代の女性に向けて、家電や調理器具などの生活用品の使用感や品質などをテストした結果を誌面で紹介しているのですが、最も大きな特徴は、評価の公平性を高めるために一切の広告を排除したことです。業界慣行のマネタイズに風穴を開けたことになりますが、テレビの場合は、制約条件がある中で面白くしなければならないので大変だと思います。
樋口 そうですね。現状、テレビに魅力を感じてくれるのは主に年配の方ですから、今の番組の多くは、「お茶の間にいる年配のお客さん」に向けて作っている時代なのかもしれないですね。私自身は、30代の頃から、おばちゃんの気持ちになって、「これ見たいかな?」と考えて番組を作っていましたけど。
川上 面白いですね。
樋口 でも僕は、「すでに、お茶の間にいる人」ではなく、その番組を見たくて「わざわざ、お茶の間にやって来る人」に向けて番組を作りたい気持ちがあります。ここ数年で言うと、2013年に放映して最終回に視聴率42.2%を叩き出した『半沢直樹』(TBS系)なんかそうですよね。あれはドラマなので僕の関わるバラエティのジャンルとは異なりますが、「世の中に、こんなに視聴者っていたんだ!?」っていうぐらいの驚きがありましたよね。
川上 あのドラマは、日曜日の21時に「わざわざ、お茶の間に人を来させた」ことになるんですね。テレビの前に座らせる。そのために必要なのは、どんなことですか?
樋口 “噛み応え”があるかどうかが求められると思います。昨年、古舘伊知郎さんが忠臣蔵の討ち入りを実況する『古舘トーキングヒストリー~忠臣蔵、吉良邸討ち入り完全実況~』(テレビ朝日系)という特番作りに参加したのですが、時代劇のパートの脚本家と何度も細かくやりとりをするなど、今の効率重視のテレビの作り方とは真逆の進め方で大変でした。
でも、「古舘さんが歴史を実況する」というコンセプトも面白かったし、作り込んだ脚本を古舘さんの実況が軽々と越えていくのもわくわくしました。手間はかかるけど噛み応えのある番組作りは、「わざわざ、お茶の間に来させる」ことにつながっていくように思います。
噛み応えのある番組が求められている
川上 樋口さんは、これまでの視聴者のニーズや意見をくみ取りながら作るマーケットインから、作りたいモノを基準に番組作りを行うプロダクトアウトにシフトしているのかもしれませんね。視聴率という制約がある中でも、「こちらから、視聴者を引っ張っていく」。それが、顧客への価値提案につながっていくんですね。
樋口 そうですね。今まで、視聴者がどうやったら喜ぶか、面白がってくれるか。それだけを考えて番組を作っていました。視聴者の1人は自分で、「自宅でこんな番組を見たら面白いだろうな」というのを基準にしていたんです。でも、残念ながら、効率重視で作り手の心意気を感じられない番組が少しずつ増えてきて、僕自身も前ほどテレビを見なくなってしまった事実があります。
川上 そうだったんですね。
樋口 それでも見たいと思わせる番組があるとしたら、噛み応えのあるものなのかなと。あと、放送作家として、あと何年できるか分からないから、自分が本当に作りたい番組を作って総仕上げにしたい気持ちもどこかにあるのかもしれません。40歳ぐらいで放送作家は卒業するものだと思っていたのに、50歳を過ぎてもまだ現役ですからね。
川上 とはいえ、視聴者層が樋口さんと同世代ですからね。まだまだ引っ張りだこなんだろうなと僕は思っていますけど。
(文・三浦たまみ、撮影・宇佐見利明)
(第2回につづく)
※次回は、12月22日(金)に掲載します。