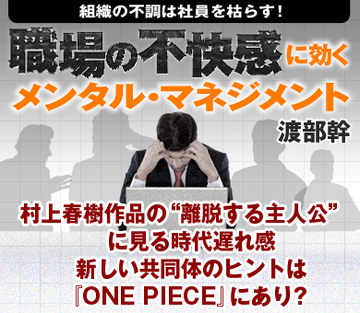『Haruki Murakamiを読んでいるときに我々が読んでいる者たち』
『Haruki Murakamiを読んでいるときに我々が読んでいる者たち』辛島デイヴィッド著
(みすず書房/3200円)
本書は、村上春樹の小説で描かれた世界の謎解きを行う、いわゆる「ハルキ本」ではない。いかに村上春樹の作品が、世界の市場に受け入れられていったのかを関係者への丹念なインタビューに基づいて綴(つづ)った一種のドキュメンタリーである。
1980年代後半から90年代半ばにかけて、国際的には無名だった村上春樹の初期作品をボヘミアン的なライフスタイルの米国人翻訳家が英語に訳した。それを日系出版社の編集者が熱心に売り込みをかけたことで、米雑誌「ニューヨーカー」に幾つかの短編が掲載される。さらに、文芸の分野では定評のある米クノップフから英語による翻訳本が出版された。その間、翻訳者は、新たなメンバーに代わり、やがて村上春樹の小説は世界中で読まれるようになった。
あらすじを言えばそれだけだが、そこには翻訳者、編集者、エージェント、書評家、書店員、さらには書籍の装丁家まで登場する“人間くさい物語”となっている。
本書は、文学というコンテンツのグローバル化という観点でも極めて興味深い。例えば、「ニューヨーカー」という雑誌の存在である。ここに掲載されること自体が一つの名誉であり、英語圏での出版を後押しすることになる。まるで、理科系の論文が、米「サイエンス」や英「ネイチャー」に掲載されるがごとく、権威があるのだ。
次に、エージェントの存在も無視できない。昨今、プロスポーツの世界でその存在は認知されてきたが、小説家にとってもエージェントは貴重な存在である。出版社との契約交渉など、面倒なこと一切を引き受けて、小説家が創作のみに打ち込める環境を提供する。
また、日本では同じ小説家でも、複数の出版社から出版することは珍しくないが、米国では同じ出版社との継続的な関係を重視する。ハードカバー版の出版前にぺーパーバック版の出版権が競売されるのは、ハードカバーの売れ行きにも好影響を与えるからだという。
何よりも驚くことは、翻訳に際して、翻訳者が大胆なコンテンツの“改変”を行っていることだ。海外での文化的背景になじむような改変もあれば、全体的なボリュームを見直すための改変もある。
同じコンテンツの輸出といえども、音楽、映像などとは違って、文学の輸出には必ず“翻訳”という作業が発生する。それがコンテンツのグローバル化のハードルにもなっている一方で、関係する人々の間で新たなドラマを生む。
村上春樹のファンはもちろん、グローバルなコンテンツビジネスに携わる人にとっても得るところが多い書籍である。
(選・評/A.T.カーニー株式会社 パートナー 吉川尚宏)