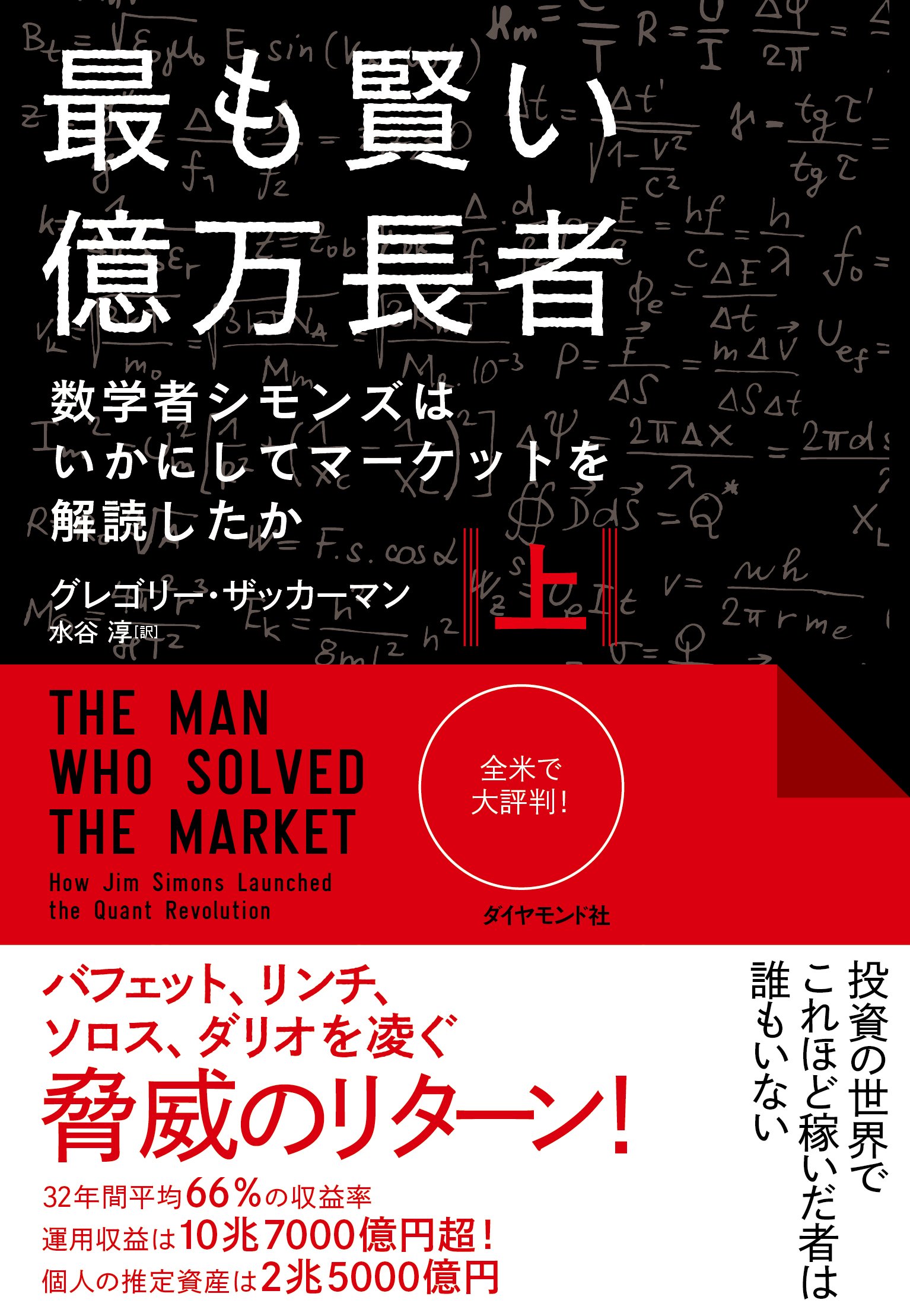コロナショックで進んだ超金融緩和、超低金利といった構造変化によって、いったい何が起こるのだろうか? バブルは起こるのか? インフレは起こるのか?『ファイナンス理論全史』などの著書がある田渕直也氏の寄稿後編をお送りする。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
金融の構造変化が招く「バブルの常態化」
(前編では)金融における近年の大きな潮流で、コロナショックでさらに金融を前人未到の領域に押し流すものとして、金余り、超金融緩和、超低金利をあげてきた。ではこれらの構造変化は結局何をもたらすのだろうか。
先述の通り、金利の低下は株価の押し上げ要因となる。金利がかつてない水準にまで下がれば、株式相場も今までの基準からすれば“かなり割高”といえるレベルまで上昇してもおかしくない。それに加え、株式ポピュリズムによって、株式市場が大きく崩れそうになれば、何らの政策支援が行われる可能性が高くなっている。
もちろん、超低金利は本当にいつまでも続けられるのか、また、危機を迎えるたびに新たな政策対応を打てる余力がいつまでも保てるのか、といった疑問は残る。だが逆に言えば、超低金利が続き、何かあったときの政策対応への信頼感が続く限りは、株式投資のリスクは今までよりもずっと小さなものに感じられ、割高な株価も許容されるようになるだろう。
それはバブルなのだろうか。今までの基準からは考えられないほどに株価が上がってしまうことをバブルと言うならそうだろうし、すぐに弾け飛んでしまう相場をバブルとするなら、そうではないかもしれない。この辺りは、単なる言葉遊びに過ぎないかもしれないが、個人的には「バブルの常態化」と呼ぶのがもっとも適切な表現ではないかと思う。
簡単には起きそうにないが、インフレが最大のリスク要因に
それでは、「(最終的に)弾けないバブルはない」といわれるが、この常態化したバブルもまたいつか弾けることになるのだろうか。
残念ながらはっきりしたことは分からないが、何ごとも永遠には続かない。おそらく最も恐れるべきはインフレの再燃であろう。
近年インフレに対する懸念は著しく低下している。日銀も含めて主要先進国の中央銀行は、軒並み年率2%程度のインフレを目標としているが、結局のところ何をやってもインフレ率は上がらず、どの国もその目標達成の目途は全く立っていない。過去20~30年で金融の世界の構図が大きく変わってきたことを述べてきたが、それは同時に“インフレの死”という経済的トレンドとも連動しているのだ。
したがって、どうしたらインフレになるのか具体的にイメージしづらいところなのだが、コロナ対策による大盤振る舞いの金融財政政策や、米中対立などを起因とするグローバルなサプライチェーンの見直しが、いずれはインフレの復活につながるという見方をする識者は決して少なくない。
いずれにしても、いつになるか定かではないが、例えば米国で想定を大きく超えるようなインフレが現実のものとなれば、超低金利政策は維持できなくなり、今消滅しかかっている金利もまた大きく跳ね上がることになる。そうなれば、株式市場の“常態化したバブル”は崩れ、すべては逆回転し始めるかもしれない。
そもそも現在、中央銀行が2%のインフレ目標を置いている理由の一部は、膨れ上がった国家債務の返済を容易にするためである。インフレは、お金の価値を減ずることだから、インフレになれば借金の実質価値も減少する。金利を低く抑えたままインフレが緩やかに進めば、債務負担は時間とともに減っていくのだ。
だが、そのインフレ目標を達成できぬままに金融緩和を次々と進めた結果、金利はほぼ消滅し、財政はますます借入に依存するようになる。そうした状況で、もしインフレ率が目標を超えて上振れし、金利が大きく跳ね上がることになれば、利払い負担の増加で一気に財政危機に陥ることにもなりかねない。
インフレを惹起するために続けられる超低金利を前提とした経済構造がいったんでき上がると、結果としてインフレの再燃が引き起こす金利上昇に耐えられなくなってしまうのだ。もちろんインフレにならなければ問題は生じない。そして、インフレになる可能性は今のところそんなに高くはない。だが、永遠にインフレにならないという保証もない。
その”もしも”のときにいったい何が起きるのか。
前例のないことであるだけに、本当のところは誰にもわからない。したがって、誰もが納得する万能の処方箋もない。リスクを見極め、臨機応変に対処していくしかないのだ。それが、コロナショックによって金融は出口の見えない新しい領域に足を踏み入れた、ということなのである。