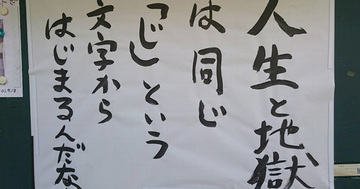仏教に手を焼いた武士たち
イエ制度と寺請制度は、人びとの考え方を大きく変えた。寺請制度は、仏教原理主義に手を焼いた武家政権が、採用した仕組みだ。
人びとはイエごとに、どれかの宗派の、寺に登録させられる。生まれたら宗派が決まってしまうので、選択の余地がない。宗派から「信」の要素が抜けていく。この結果、何年か経つと、どの宗派も似たりよったりになる。
どの寺も、法事や葬儀のほかは、おおぜい人を集めてはいけない。また、誰かが宗派を変わってもいけない。つまり布教をしてはいけないのだ。代わりに、葬式だけしていなさい。寺は収入が保証された。
イエごとに宗派が違うので、親戚の葬儀や法事に参加するたび、違った宗派になる。その結果、読経、焼香、戒名のつけ方など、細かな違いがあっても、似たようなセレモニーになる。盆や彼岸などの年中行事も、各宗派に共通である。
この結果、宗派の違いは丸められ、ありがちな常識ができあがる。まとめると、つぎのようだ。
a 人間は死ぬと、仏の弟子になる。いや、もう仏である
b 仏の弟子なので、俗名のほかに、戒名をお寺につけてもらう
c 死んだあと、三途(さんず)の川を渡って、あの世に行く
d 戒名を記した位牌を仏壇に祀って、お祈りする
e お盆には、死者はあの世からもどってくる
死ぬと人間がどうなるのか、誰に聞いてもだいたいこう答える。これは、仏教の見かけをしているが、実は、仏教と関係がない。
まずaだが、死んだら仏弟子になるわけでも、まして仏になるわけでもない。bの戒名は、出家者の名前である法名が変形したもの。仏典に根拠のない日本ローカルな習慣だ。これが奇妙このうえないことは、『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』(サンガ新書、二〇一二年)でのべておいた。cも俗信である。dの位牌は、もともと儒教・道教のもので、それが転用され、仏壇(イエ制度のアイテム)と結びついた。eは、起源の不明な、仏教以前の風習である。
鎌倉時代の仏教の、切羽詰まったとんがったところはどこにもない。みごとに丸くなってしまっている。死の意識がぼんやりし、自己意識もぼんやりしたということだ。
死んだらどうなる?
死者は、戒名をつけられて、決まったスケジュールで死後を歩んでいく。これを「成仏する」という。死者は、怨霊にも悪霊にもならない、のである。
日本人は伝統的に死を恐れ、死を穢れだと考えてきた。そのマイナスの感情にフタをしたのが、a~eである。
日本人は、霊を信じているのか。日本には、幽霊というものがある。死者は幽霊となって、死亡の現場に出没したり、関係者のもとに現れたりする。幽霊は妄念(恨み)が強すぎ、成仏できないのだとされる。読経して供養すると、スケジュール通りの死後の歩みに戻り、幽霊として迷って出てこなくなる。
幽霊になるのは例外で、ふつうは決まったスケジュールで成仏へと歩む、と考えられていることがわかる。
死後は、三回忌、七回忌、…など、一定の間隔を置いて故人をしのぶ法要(年忌法要)を営む。故人を覚える関係者が死亡するか高齢になるころに「弔(とむら)い上(あ)げ」をして、以後、年忌法要は行なわなくなる。このころまでに死者はありありとした実体を失って、祖先と融合していく。(過去帳に命日が記されている場合は、記録が残るが、直近の死者のように生々しい感覚ではない。)
念仏宗の場合、死者は極楽浄土に往生しているはずで、年忌法要を行なうのは妙だ。けれども、そうした原則論は言わない。とんがるのはやめて、丸くなったのだから。
仏教はどの宗派もだいたい、このように共通している。仏教のほかに少数、神道の人びともいる。神道は、五年祭、十年祭など時間の刻みこそ違うけれども、考え方のよく似た祖先祭祀を行なう。
日本人は、人間が死んだら、どうなると考えているのか。
人びとの最大公約数は、a~eのようである。これは、仏教か。仏教のように思っている人びとが多い。けれども、それはみかけにすぎない。日本の古くからの慣習が、イエ制度と寺請制度のなかに入り込み、江戸時代に定着したものだ。そのなかみは、仏教とほぼ関係がない。「年忌法要を行なうなどの習慣は、仏教と関係ない古い伝統である」。
(本原稿は『死の講義』からの抜粋です)