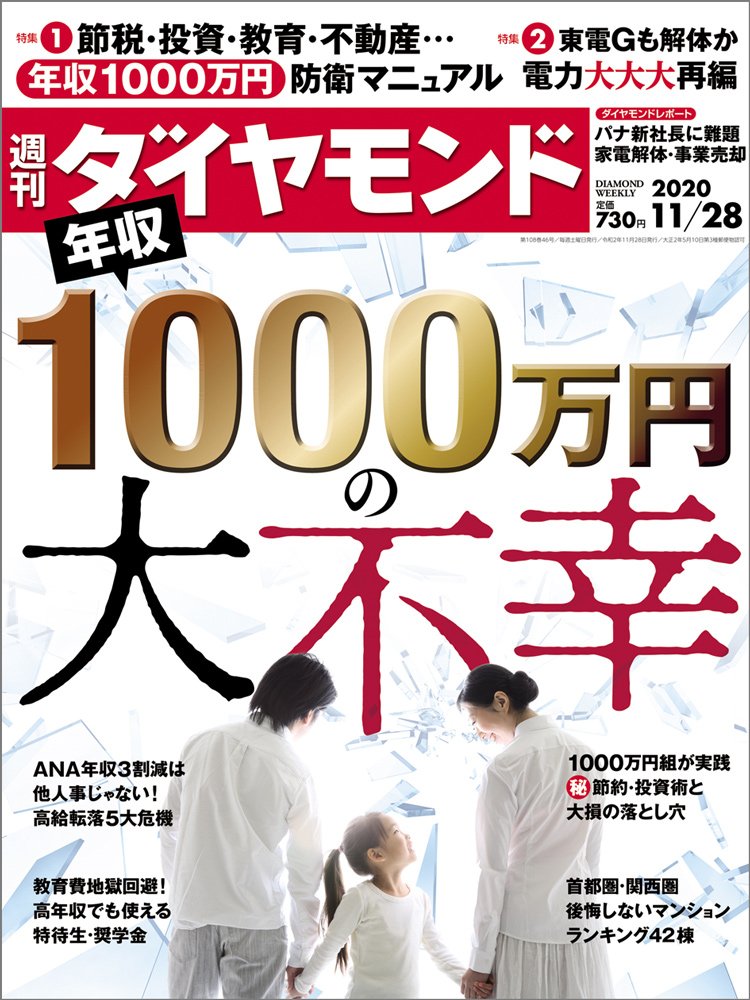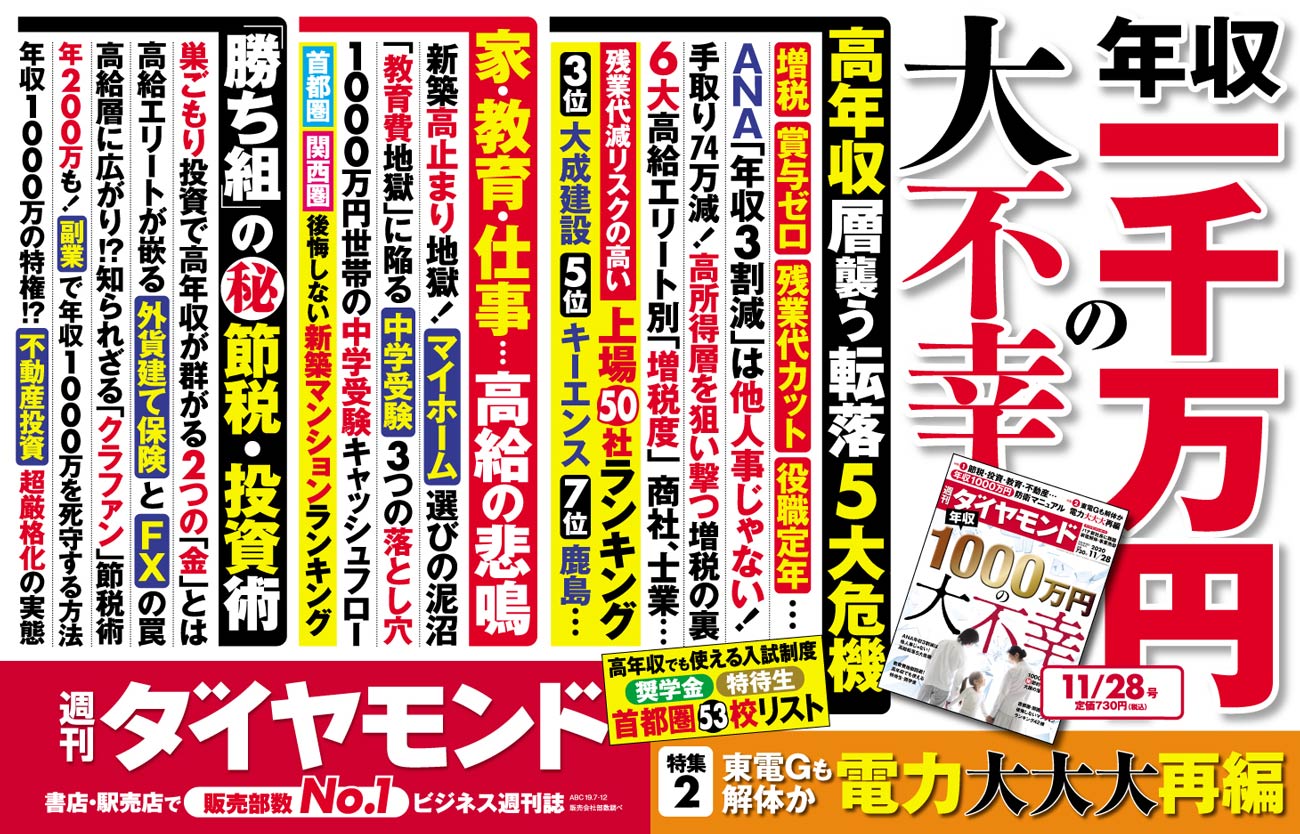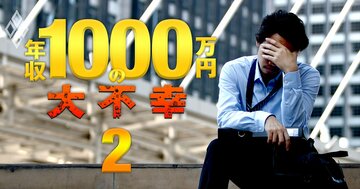家計を巡る構造問題として、高年収世帯を中心とした「増税」や「役職定年」というこれまで陰に隠れがちだった家計の危機をも顕在化させ始めている。
「ANAのニュースはちょっと冷めた目で見ていましたね。今どき年金保険料を7割も負担してくれていたなんて、本当に恵まれていますよ」
そう話すのは、IT系のベンチャー企業に勤める40代の男性だ。今春まで不動産会社で働いており、新規事業の立ち上げを担っていた。しかし、コロナ禍の影響で事業にストップがかかり、業務上全く身動きが取れない状態が続いたことで、転職を決意したという。
昨年の年収は900万円超。1000万円プレーヤーまであと一歩のところまできていたが、新天地に移るまでに空白期間ができ、今年は3割以上年収が下がってしまう見通しだという。
そうした中で、この男性がANAの福利厚生に敏感に反応したのは、仕事の面においてコロナ禍の影響を同じように大きく受けたからでは決してない。
それは、社会保険料の負担増や増税、経済成長の停滞といったしわ寄せが、世代としても世帯年収の面でも最も生じるかたちになり、割を食ってきたという背景があるからだ。
定率減税の廃止といった増税策によって、年収1000万円の会社員の実際の手取り額は、1割近くも減っている計算になるという。さらに、年収1000万円(片働き世帯)前後を境目にして、国や自治体からの各種手当や支援が所得制限によって、受けにくくなるという現実もある。