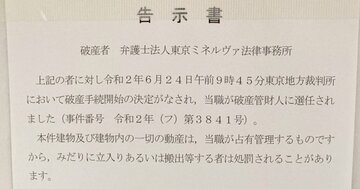コロナで全店舗閉店し会社を清算することに決めた経営者、年の瀬に何を思うか(写真はイメージです) Photo:PIXTA
コロナで全店舗閉店し会社を清算することに決めた経営者、年の瀬に何を思うか(写真はイメージです) Photo:PIXTA
オリンピック・パラリンピックイヤーとなるはずだった2020年は、新型コロナウイルス感染拡大により誰もが想定していなかった一年となった。日本経済も大きな打撃を受け、コロナ関連の倒産件数も増え続けている。今回は、経営している飲食店を閉店し、会社を畳む選択をした経営者に、廃業を決めた経緯や率直な思いを聞いた。(聞き手/ダイヤモンド編集部 笠原里穂)
飲食店の倒産が相次いだ
コロナ禍の2020年
帝国データバンクによると、12月24日時点で新型コロナウイルス関連の倒産件数は累計841件に上った。業種別に見ると最も多いのが、飲食店(132件)だ。外出自粛などの影響で客数が大幅に減少し、特に緊急事態宣言中は休業せざるを得ない店も多かった。
30代にして青森県を中心に東北地方で5店舗の飲食店を経営していた福井寿和さんは、コロナ禍での経営状況悪化をきっかけに会社を畳む決断をした。年商は1.5億円に達していたが、3月からコロナの影響で客足が遠のき、売り上げが昨年対比で30%を切るまでになっていたという。そして4月下旬、経営する全店を閉店し、会社を清算することを決めた。福井さんに当時の決断の背景や、今の思いを聞いた。