アメリカ陸軍の人間冬眠実験の被験者に選ばれた平凡な青年ジョーは、期間1年のはずが、さまざまなトラブルで実験そのものが忘れ去られ、500年後に目覚めることになる。そこは人類の知能が大きく低下した世界で、ジョーは唯一のインテリとなり、内務長官に任命されて世界の危機に立ち向かう……というのが映画“Idiocracy(イデオクラシー)”で、Idiot(愚か者)とDemocracy(民主政)をかけているから「愚民政」とでも訳せるだろうか。日本では『26世紀青年』のタイトルでDVD発売された(Amazonプライムビデオで視聴可)。
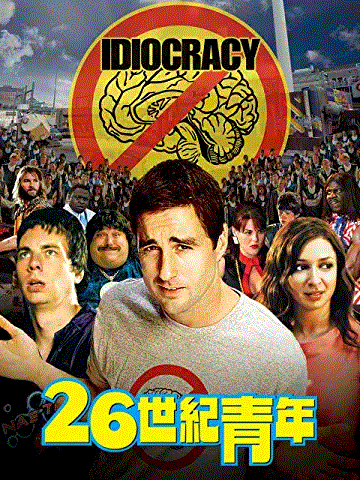 映画『26世紀青年』は2006年公開のコメディ映画
映画『26世紀青年』は2006年公開のコメディ映画
アメリカでは2006年に劇場公開されたもののほとんど話題にならなかったが、2016年にドナルド・トランプが大統領に当選すると注目が集まり、その後、暴徒と化した群衆がホワイトハウスを襲撃する映画のシーンが2021年の連邦議会議事堂占拠事件と重ね合わされた。トランプ時代のアメリカは「イデオクラシー」だというのだ。
この映画では人類の知能が低下した理由は、知能の高い男女が独身のまま過ごすか、結婚しても子どもを1人しかつくらない一方、知能の低い男女が次々と子作りするからだとされていた。これを20世代ほど繰り返すと、知能指数100(偏差値50)の平均的な若者がアインシュタインのように見なされる世界が到来するのだ。
「低い知能のほうが、高い知能よりも多くの子供を持つようになった」
“Idiocracy”はコメディ映画だが、「人類(ヨーロッパ人)の知能が低下しつつある」と考えるひとたちが実際にいる。そんな彼らは、現在の欧米で一定の(あるいはかなりの)影響力をもつようになっている。エドワード・ダットン、マイケル・A・ウドリー・オブ・メニーの『知能低下の人類史 忍び寄る現代文明クライシス』(蔵研也訳、春秋社)が翻訳出版されたことで、この「危険な思想」がようやく日本にも紹介された。
原題は“At Our Wit’s End; Why we’re becoming less intelligent and what it means for the future(われわれの機知の終わりに われわれが愚かになりつつある理由と、それが未来に意味すること)。
著者たちはいずれも40代の白人男性で、ダットンは1980年イギリス生まれ。大学ではキリスト教神学を専攻した。スウェーデンの大学の客員研究員、サウジアラビアの大学の研究チームのコンサルタントなどを経てフリーランスの研究者・著述家となり、現在はフィンランド在住。
ウドリー・オブ・メニーは1984年イギリス生まれで、コロンビア大学で進化・生態と環境生物学の学位を取得、ロンドン大学の博士課程で植物の分子生物学的な特徴について研究したのち、研究対象をヒトの進化的な行動生態学に変え、「平均的な知能は低下している」と主張するようになる。これは「ウドリー効果」と呼ばれているという。
著者たちは、「1400年代から19世紀中盤まで、(ヨーロッパでは)すべての世代において、より豊かな50%は、貧しい50%よりも多くの子供を育ててきた」という。その結果、この400年あまりで世代ごとの知能は上昇し、「例外的な超天才」たちが増えつづけ、彼らがもたらした技術革新によって産業革命が実現した。
だがこのプロセスは、その後、急速に逆転しはじめた。産業革命による医療と衛生の改善や、貧困の悪影響を緩和する社会政策によって、「将来のことをあまり考えられない人々が、その後の結果を想像せずに衝動的にセックスする」ようになったからだ。こうして、「低い知能のほうが、高い知能よりも多くの子供を持つようになった」とする。
本書の特徴は、知能の低下をローマ帝国の没落と重ね合わせていることだ。著者たちによれば、ローマは自然選択によって知能がピークに達したあと、高知能と出生率の負の相関が生じて、その後の衰退と崩壊に至ったのだ。
こうした主張は興味深いものの、これは白人至上主義者の「グレート・リプレイスメント」論とよく似ている。ヨーロッパ系白人がつくりあげた文明(市民社会)が、有色人種(ヨーロッパではムスリム、アメリカではヒスパニックなどの移民)によって「リプレイス(置き換え)」されつつあるとするもので、レイシズム(人種主義)の典型として見なされている。これが「危険な思想」であることを最初に指摘したうえで、より具体的に本書の内容を見ていこう。


![ウクライナの独立に奔走した「赤い大公・ヴィリー」の生涯[後編]ハプスブルク家と神聖ローマ帝国](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/360wm/img_a86e8e3fe945d2b8a100cbd51e3a2bde36959.jpg)




