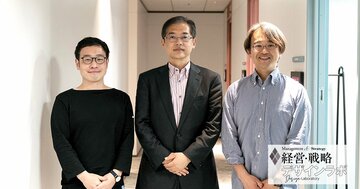協調領域と競争領域は
「縦割り」から「横割り」へ
白坂 しかしこれが、System of Systemsによって、異なる産業間で各カテゴリーがつながり始めると、モビリティはモビリティ、医療機関は医療機関、ではなくなります。モビリティと医療機関をつなげるのか、モビリティと別のものをつなげるのか、医療機関と別のものをつなげるのか、どういった組み合わせで価値を提供するのかが競争になります。協調領域と競争領域がまったく違うところになってくるんです。
つまり、人に対する価値提供のジャーニーがガラリと変わります。これまで「縦割り」で協調と競争をしてきたのが、「横割り」の協調と競争が生まれてくるんです。社会構造と産業構造が大きく変わってきているんですね。
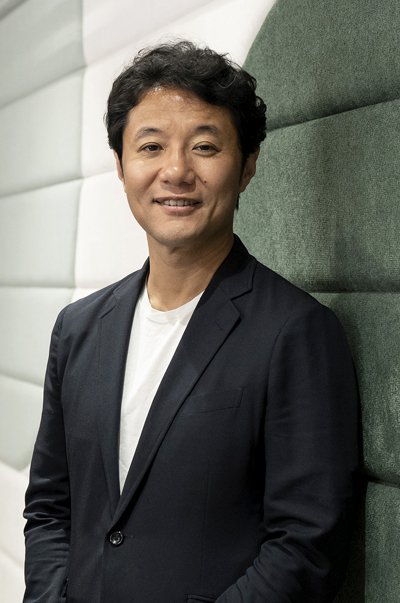 入山 章栄(いりやま・あきえ)
入山 章栄(いりやま・あきえ)早稲田大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)教授。慶応義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所で主に自動車メーカー・国内外政府機関への調査・コンサルティング業務に従事した後、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.を取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクールアシスタントプロフェッサー。2013年より早稲田大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)准教授。2019年から現職。Strategic Management Journal, Journal of International Business Studiesなど国際的な主要経営学術誌に論文を発表している。著書に『世界の経営学者はいま何を考えているのか』(英治出版)、『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』(日経BP社)、『世界標準の経営理論』(ダイヤモンド社)など。
入山章栄(以下、入山) 先日、グーグル・クラウド・ジャパンの平手智行代表とお話ししたところ、まさにこの世界観を持っていらして、クラウドにいろいろなプレイヤーがデータを上げて、瞬時に結合する。そこのインフラをグーグルはつくりたいと、こうおっしゃっていたんですね。
アマゾンの「AWS」(Amazon Web Services)もそうだと思いますが、白坂先生の今のお話のような世界が当たり前になっていくのだと思います。
途中で撤退しましたが、Google関連会社が、カナダのトロントでスマートシティをつくろうとしていましたよね。GAFAのようなOS(オペレーティングシステム) レイヤーやクラウドレイヤーは、そういったあたりを急いで整備しようとしています。
それに乗るのか、競合するのかはわかりませんが、そのような世界になっていっていることを認識した上で、日本企業としてどうやっていくのか、全体感を見てやっていかないとまずいですよね。
白坂 その通りだと思います。この「横割り」を、米国を中心としたGAFAが1社でどれだけ取り込めるか、ということが始まっています。この協調領域を、1社が持つのではなくて、インターオペラブルにすることによって分散化する、という手もあるはずです。
また、日本にはフィジカルな領域における強みがあります。サイバーとフィジカルが融合していくと、今度はフィジカル側の情報が必要になります。そのフィジカルな領域で、日本の強みを活かしながら、入山先生がご指摘のように、GAFAなどに協調するのか、競争するのか、これからの焦点です。
このように、もうすでにこうしたことは起き始めていて、いろいろなパターンの協調の切り方や、競争の切り方がある。まさにこれが、新しい協調・競争時代の考え方だと思います。
コロナ禍もしかり、ロシアのウクライナ侵攻もしかりですが、今は誰も想定していなかった変化が次々と起こっています。これで終わるわけでは決してなく、これから先もこういったことは必ず起こっていくでしょう。次に、お話したかったことの2点めが、そのような変化への対応を、企業などの組織はどう考えていくべきか、です。