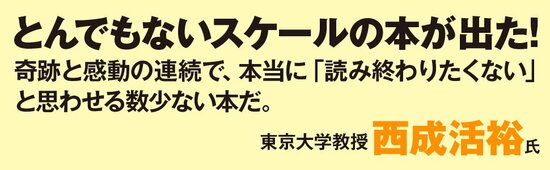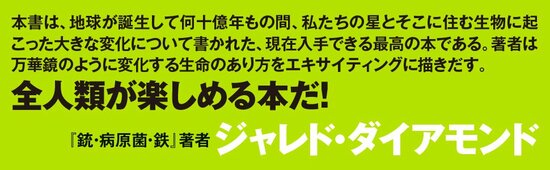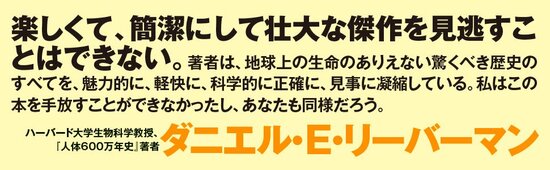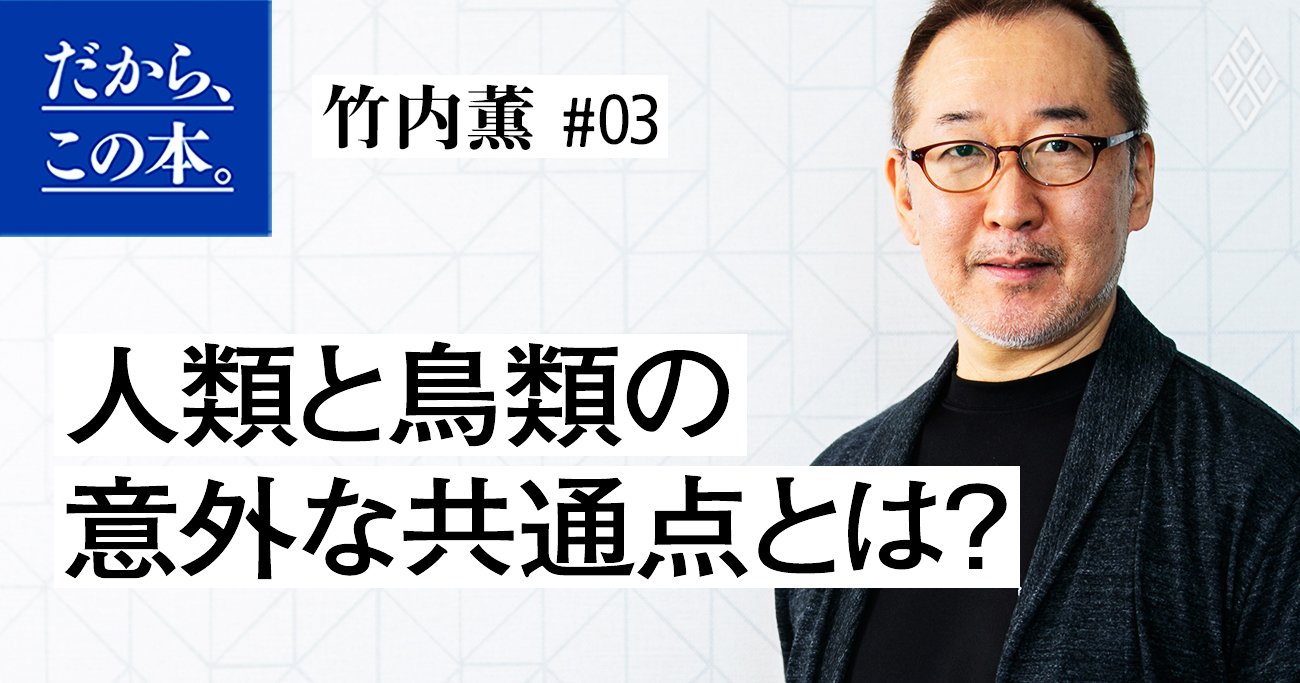
地球を30億年以上も支配している微細な生物。宇宙でもっとも危険な物質だった酸素。カンブリア紀に開花した生命の神秘。1度でも途切れたら人類は存在しなかったしぶとい生命の連鎖。地球が丸ごと凍結した絶滅から何度も繰り返されてきた大量絶滅。そして、確実に絶滅する我々人類の行方……。
その奇跡の物語をダイナミックに描きだした『超圧縮 地球生物全史』(ヘンリー・ジー著、竹内薫訳)を読むと世界の見方が変わる。読んでいて興奮が止まらないこの画期的な生物史を翻訳したのは、サイエンス作家の竹内薫さんだ。
そこで、「まるでタイムマシンで46億年を一気に駆け抜けたような新鮮な驚きと感動が残った」とあとがきにも書いている竹内さんに、本書の魅力について語ってもらった。今回は、生物学的に考えるとヒトはもともと不倫する生き物だという衝撃の内容についてお伝えする。
(取材・構成/樺山美夏、撮影/梅沢香織)
ヒトは生物学的には乱交型
――『超圧縮 地球生物全史』を読んで一番びっくりしたのは、ヒトには交尾期がない代わりに常に発情していて、それを隠しながら「一般に考えられているよりずっと不倫に耽っている」という話です。
いきなり答えにくい質問ですみませんが竹内さんはどう思われましたか?
竹内薫(以下、竹内):ヒトのオスの生殖器が体に占める割合は、ほかの類人猿に比べてかなり大きくて、それは常に性的アピールをするためだと著者は述べています。
ヒトのメスも、授乳するしないにかかわらず成人になると乳房は常に膨らんで目立つようになっています。ヒトのオスもメスも、そういう体つきをして常にセックスアピールしているのに、子孫を養育するために「つがいの絆」を育む傾向があるから、隠れて不倫するようになる、と。
つまり、ヒトはもともと乱交型なのに、一夫一婦制を徹底しているから、不倫すると吊し上げられるような事態が起きてしまうわけですよね。
生物学的に考えると、不倫で生まれた子どもでも家族や仲間で協力して育てほうが望ましいという著者の見解は、社会的な動物のヒトの子孫繁栄を考えると一理あるようにも思います。
人類と鳥類の意外な共通点
――「ヒトの社会的道徳観や性的習慣は、ほかの霊長類よりも鳥類との共通点が多い」という話も意外でした。ゴリラより鳥に似ているんだ!と思って。
竹内:私はよく野鳥観察をしているので「なるほどな」と思いましたけど、鳥類は縄張り意識が強くて、積極的に性的誇示をする鳥が多いんですよね。
基本的にはヒトと同じ一夫一婦制ですけど、本にも書いてあるように、オスが狩りに出ている間、メスがほかのオスと平気で交尾することもままあります。
ですからオスは、どの子が本当に自分の子で、どの子がほかのオスの子どもかわかりません。
それでも家族で生活して、親も子もみんなで協力しながら子育てしている。つまり、種としての結束力が強いと言えるでしょう。
「一夫一婦制」が続いている理由
――本来、ヒトの子どもは家族間で協力しながら地域で育てるものだと著者も述べています。この本を読んで生物学的視点を持てば、不倫や婚外子に寛容な人が増えるかもしれません。
竹内:あとはやっぱりお国柄によっても不倫のとらえ方が違いますよね。
たとえばフランスは、政治家が不倫しても個人の問題なのでほとんどスルーされます。
メディアに暴露されたとしても謝罪会見などめったに開きませんから。

――そういえば、ミッテラン元大統領も、夫人以外の女性と家庭を持っていることについて取材されても「それで?」のひと言で終わりです。
不倫略奪愛のマクロン夫妻はむしろ女性たちの共感を得ていました。
竹内:そういう意味で言うと、個人の恋愛を尊重するフランスは生物学的には正しい国です(笑)。
逆にアメリカは非常に厳しくて、不倫がバレるとすぐ訴訟に発展します。
日本はどちらかというと、アメリカの影響を受けて不倫に厳しくなっているんじゃないかという気がします。
――そもそも人間は本能より理性が勝っているから、一夫一婦制を守り続けることができたんでしょうね。
竹内:一夫一婦制が長い人類史の中でなくならなかったのも、おそらく進化論的に大きな意味があるから続いてきたわけです。
だから子孫が繁栄したのでしょう。乱交型のままで子育てしてもおそらくうまくいかないんでしょうね。
でも一夫一婦制は進化するための形式的なシステムですから、ヒトの本能としてはどうしても不倫する方向に行ってしまう。だからもし隠れて不倫する人がいても、生物学的には否定できないよねっていう状況が、本当は正常な社会なのかもしれません。
とはいえ、今のように不倫した人を徹底的に吊し上げる社会では、到底ありえないと思いますけど。
日本の会社の妙なシステム
――交尾期がないヒトのオスとメスは、生殖器の大きさや乳房のふくらみで常に性的アピールをする体つきになっているので、余計なトラブルを招かないためには性差を意識させない工夫も必要ですよね。
竹内:それに関して言うと、会社で仕事するときは、女性は女性らしく、男性は男性らしくといった性別的な考えをする必要はまったくありません。
ところが日本の会社は長い間、女性の従業員にはスカートの制服を着せてお茶出しをさせたり、オスとメスを区別するようなシステムを持ち込んできたから、役員が男ばかりになったり女性を差別したりする文化が根強く残ってしまったのでしょう。
――最近になってようやく、銀行やデパートでも女性制服を廃止するところが出てきています。学校でも、女子の制服をスカートかスラックスか選べるところもあります。
竹内:大前提として職場や学校で、オスとメスを区別する必要はまったくなくて、生物学的観点から性別を意識する必要がある場所と、必要ない場所の区別をしなければいけないんですね。
そうすれば、保守的な企業や学校の、女性はスカートの制服を着るもの、といった偏った固定観念は自然となくなるはずです。
核家族化する社会
――逆に、恋人とデートする際は、性別を意識したファッションでも何でも自由に楽しめばいいんですよね。
竹内:そうです。そこをごっちゃにしないで、分けて考えることが大事ですよね。
あとはやっぱり、明治、大正時代のように子どもが7~10人いて祖父母も同居していた大家族時代と違って、今は核家族社会ですから、一夫一婦制により厳しくなっているんじゃないでしょうか。
僕が子どもの頃は、遠い親戚のきょうだいに髪の毛の色が違う子がいて、明らかにお父さんが違うよねと周りから見てもわかりましたけど、他のきょうだいと一緒に普通に育てていましたからね。
子どもの数が多かった時代は、親戚に預けて育ててもらう子も普通にいましたし、父親が誰かわからない子もいたはずです。でもそのくらいゆるい繋がりで、みんなで協力して子どもを育てていったほうが、子孫繁栄にはつながるんでしょうね。
【大好評連載】
第1回 【東大卒サイエンス作家が教える】生物史は大量絶滅の連続…人類が絶滅する決定的な理由とは?
第2回 【東大卒サイエンス作家が教える】生物の進化に革命を起こした臓器ベスト6
一九六〇年東京生まれ。理学博士、サイエンス作家。東京大学教養学部、理学部卒業、マギル大学大学院博士課程修了。小説、エッセイ、翻訳など幅広い分野で活躍している。主な訳書に『宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか』(ロジャー・ペンローズ著、新潮社)、『WHOLE BRAIN 心が軽くなる「脳」の動かし方』(ジル・ボルト・テイラー著、NHK出版)、『WHAT IS LIFE? 生命とは何か』(ポール・ナース著、ダイヤモンド社)などがある。
著者略歴:ヘンリー・ジー
「ネイチャー」シニアエディター
元カリフォルニア大学指導教授。一九六二年ロンドン生まれ。ケンブリッジ大学にて博士号取得。専門は古生物学および進化生物学。一九八七年より科学雑誌「ネイチャー」の編集に参加し、現在は生物学シニアエディター。ただし、仕事のスタイルは監督というより参加者の立場に近く、羽毛恐竜や最初期の魚類など多数の古生物学的発見に貢献している。テレビやラジオなどに専門家として登場、BBC World Science Serviceという番組も制作。このたび『超圧縮 地球生物全史』(ダイヤモンド社)を発刊した。