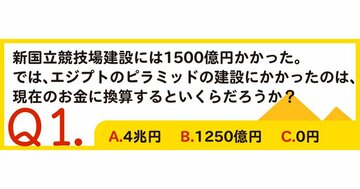企業の育休制度の「ひずみ」と
納得の少子化解決法
 田内学(たうち・まなぶ)
田内学(たうち・まなぶ)1978年生まれ。東京大学入学後、プログラミングにはまり、国際大学対抗プログラミングコンテストアジア大会入賞。同大学院情報理工学系研究科修士課程修了。2003年、ゴールドマン・サックス証券株式会社入社。以後16年間、日本国債、円金利デリバティブ、長期為替などのトレーディングに従事。日銀による金利指標改革にも携わる。2019年退職。中央省庁、自民党や議員連盟の各種会議では、財政、年金、少子化問題について提言を続ける一方、学校等でお金の教育についての講演を行っている。インターネット番組「経世済民オイコノミア」の司会。著書に『お金のむこうに人がいる』。
Photo by H.K.
田内 というのも、少子化の話になるとなぜか必ず、親が子どもを「産む」話ばかりです。過去にもある政治家が「女性は産む機械」と発言して炎上したこともありましたが、社会で子育てを「支える」という話になりません。
年金問題では1人の高齢者を現役世代の何人が「支える」という言い方をするのに、子育てになると、1人の子どもを現役世代の何人が「支える」とは言いませんよね。子どもが欲しくても育てることの大変さから躊躇(ちゅうちょ)している人が多いのが現状です。
「育てるのが大変」というのは、子育てにはお金がかかるという経済的な理由と、生活において子育てへの風当たりが強いという社会的な理由、この2つがあるのだと思います。「社会全体で子どもを育てる」ことを考えなければならないし、それが社会を作り、未来を作ることになるはずです。
田原 欧米では「社会全体で子どもを育てる」という風潮があり、夫婦間でも育児は五分五分が当たり前という意識のある人が多い。そしてそれを支援する仕組みは公費からまかなわれている。一方、日本では育児はいまだに妻が担当しているケースが多く、しかも公費によるサポートが少ない。ここがまったく違いますね。
田内 本当にそのとおりで、日本政府は子育てへの支援にもっとお金を使ったほうがいい。実際、子育てを誰がするかという話もあるし、男女が平等に育児を行うということもできていない。政府や地方自治体はもちろんのこと、個人の意識を変える必要があると思います。
田原 企業でも女性の管理職が非常に少ないですね。課長はいるが役員クラスというのは本当にごくわずかです。上場企業の役員に聞くと、「女性は子育てが忙しくて、会社の仕事がなかなかできない」ということを言うんですよ。
田内 子育ての分担や支援が進まないから女性が働きにくいのに、会社では、子育てが忙しいから女性が働いてくれないと言っている。
このような話を聞いたことがあります。共働きの夫婦がいて、その夫を雇っている会社、その妻を雇っている会社、実は両方ともそれなりにきちんとした育休制度自体はある。でも、妻だけが育休を取るので、妻を雇っている会社だけが労働力をそがれることになる。夫を雇っている会社は、妻を雇っている会社にいわば「フリーライド」していることになる。結果的に男女を比べたときに、女性側を雇う会社が割を食う形になってしまう。
田原 どうすればいいのでしょうか?
田内 解決方法はふたつあると思います。ひとつは、時間が経てば、古い考えの人たちがいなくなっていき、男性側も育休を取るべきだと、社内そして社会の意識も否応なく変わります。
もうひとつは、「子育てに値付けする」ことです。先ほどからお話ししているように、経済の問題を話すときに、みんな「貨幣経済」しか考えていません。経済となると、お金でカウントできるものしか考えていないんです。「自分が金銭的に損するか得するか」という尺度でしか考えなくなると、自分の行動がそこで決まってしまいます。すると、子育てのような貨幣経済に含まれない活動は、優先順位が低くなる。自分の中でも社会でも。
だからもう、子育てに値付けするしかないと思うんです。行政が制度を設けて、社員が育休を取っている会社に対して、法人税の税率を下げるなど金銭的に優遇する。
田原 なるほど、そうすれば社員が育休をとっても、企業は平気なんだ。なぜ政府はそれをしないんでしょうか。
田内 ここでまた「財源をどうするんだ」という話になるからです。でも、社員が育休を取る会社を優遇する代わりに、社員が育休を取らない会社からは税金を多めに取ればいいんです。そうでもしなければ、企業も個人の考えも簡単に変わらないと思います。