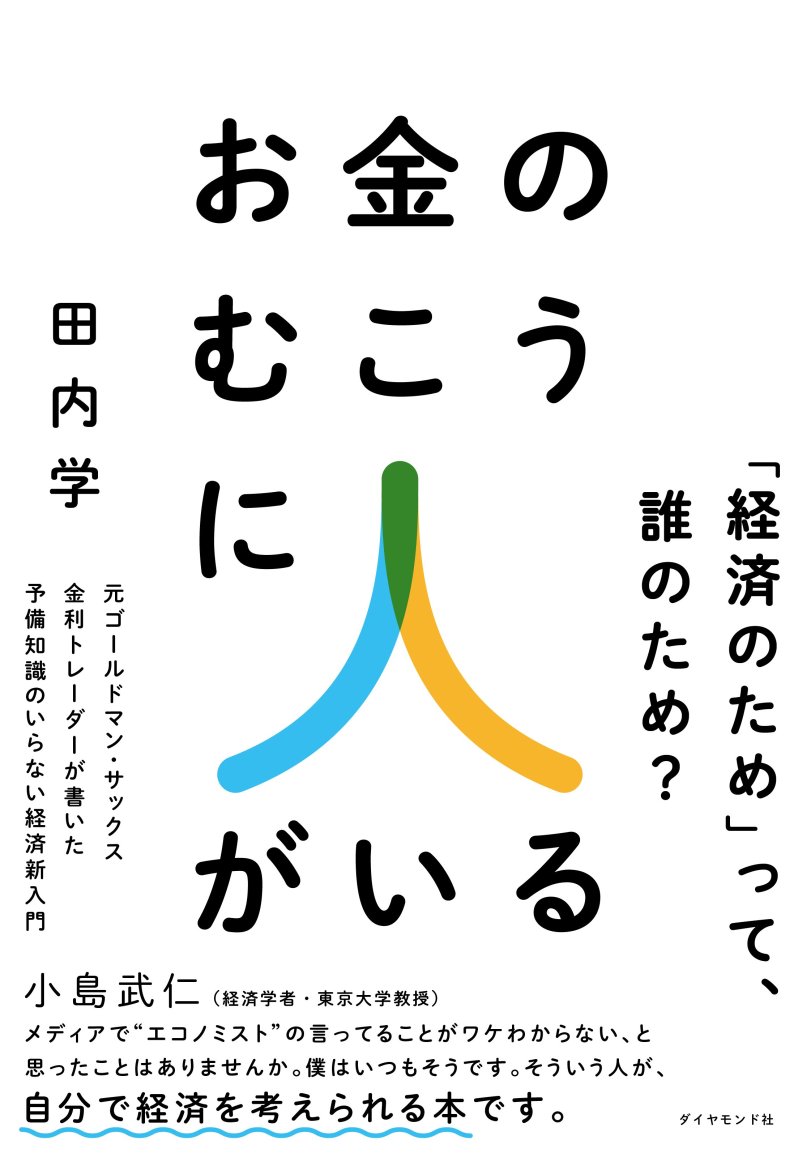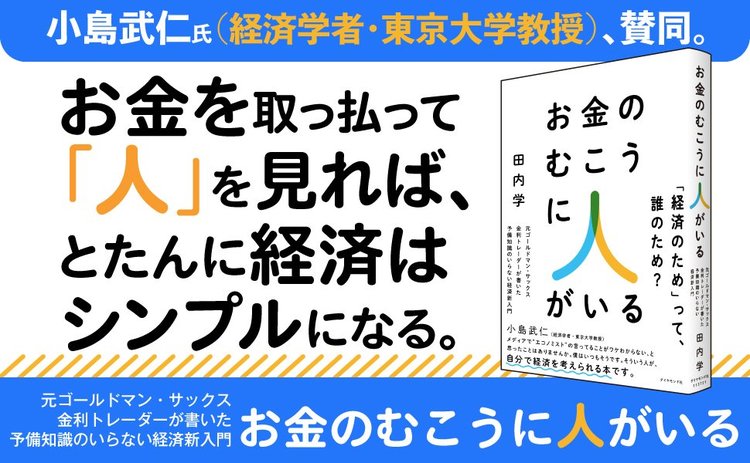東京のど真ん中、オフィス街の赤坂駅周辺から書店が消滅しようとしている。「金」ではなく「人」を中心に経済を考える入門書『お金のむこうに人がいる』の著者であり、金融教育家である田内学氏は、書店が次々に閉店していくのは社会全体の問題であり、根っこでは「女性の労働問題」にもつながっていると言う。どういうことなのか。(構成:編集部/今野良介)
 “書店という業態は世の中に街に必要とされなくなっているのだろうか? 皆様に愛される書店を目指した文教堂赤坂店。志半ばで去らなくてはいけなくなりました。またこの地に戻ってくる。この気持ちを新たに日々精進いたします。”
“書店という業態は世の中に街に必要とされなくなっているのだろうか? 皆様に愛される書店を目指した文教堂赤坂店。志半ばで去らなくてはいけなくなりました。またこの地に戻ってくる。この気持ちを新たに日々精進いたします。”
“書店という業態は世の中に街に必要とされなくなっているのだろうか?”
いつもの書店に入ろうとしたら、張り紙に気づいた。
そこには、6月に閉店することを余儀なくされた書店員の無念さが込められていた。
中に入ると、テニスコート2面ほどの店内には、サラリーマンや学生たち、親と一緒に絵本を選んでいる小さなこどもたちもいた。昔から地元の人たちに愛されているはずの書店だ。
書店消滅の裏にある2つの問題
ここは、赤坂駅徒歩0分にある文教堂赤坂店。
目の前にはTBSがあり、多くのオフィスビルも立ち並ぶ。国会議事堂からも徒歩圏内で、まさに東京のど真ん中という立地だ。
都会の書店がただ閉店するという話だけにとどまらない。このお店の閉店によって、赤坂駅周辺から書店が消えてしまう。
コロナ禍にみまわれた2年ほどの間に赤坂駅周辺の書店が相次いで閉店しており、ここが最後に残っていた書店だったのだ。

“コロナ憎し”という話をしたいわけではない。コロナ禍以前から書店の数は全国的に減っている。
文教堂赤坂店の書店員が訴えるように、「書店という業態を必要とする人がいなくなっている」かというと、そうではなさそうだ。書店は現代でも街のオアシス的存在であり、街からその書店が消えたら悲しむ人たちは数多くいる。
では、どうして書店が消えていくのか?
「そんなの簡単だ。ネットで本を買う時代だからだ」
そう思う人は多いだろうし、たしかにその通りでもある。
しかし、ここにはもっと根源的な問題が2つ隠れている。この問題こそが、今の日本の危機的な状況を作り出しているといっても過言ではない。
その問題の一つは、自分の財布のことばかり考える人が増えたことだ。
「どうすれば節約できるのか?」「どうすればお金を増やせるのか?」そんな情報が巷にはあふれている。
たとえば、商品を買うときは、なるべく安く買いたい。そして、価格が同じなら、どこで買っても同じだと思う。自分の財布の中だけを気にするなら、たしかにその通りだ。
ところが、経済は自分一人の問題ではない。財布から出ていくお金を渡す相手をどう選ぶかで、社会は変わる。
「お金を渡す」という意思表示
「何か面白い新刊は出てないかな?」と思いながら、近所の書店にふらっと入る。「こんな本が売れてんの?」という半信半疑の気持ちで、話題の本を手に取ってみる。ページをめくると意外に面白い。家でゆっくり読んでみたい。
こういう出会いが書店にはある。その本をレジに持っていって購入する。
ところが現代では、「書店で買わない」という選択肢もある。Kindleで少し安く売られている電子書籍を買うこともできるし、メルカリで中古品を安く買うこともできる。同じ価格でも、家まで無料で迅速に配送してくれるアマゾンで購入することもあるだろう。
どの選択肢を選ぶかによって、使う金額は変わる。そして同時に、お金を渡す相手も変わるのだ。
近所の書店で購入すれば、お金はその書店に流れる。他の選択肢を選べば、そのサイトを運営する会社に流れていく。
日用品でも洋服でもなんでも、インターネットで購入したほうが安くて便利なことは多い。しかし、使ったお金は自分の暮らす地域には流れずに、外に流れていく。人口減で苦しんでいる地方経済はますます不景気になり、シャッター街が増えていく。自分自身の収入が減ることにつながるかもしれない。
もっと視点を広げて、日本という国を眺めてみても、お金を渡す相手を考えることは重要だ。
価格が安いという理由だけで食料品を外国から買っているうちに、日本の食料自給率(カロリーベース)は40%を割ってしまった。
「賃金の安い海外で自動車を生産した方が安く作れる」という理由で、国内の工場の多くが海外に移された。
日本の雇用は減り、設備投資も減り、技術も海外に流出した。お金を渡す相手を気にしなかった結果、日本は貿易赤字国になり、全体の経済力も低下してしまった。
わたしは、「インターネットで購入するな」ということを言いたいわけではない。仕事が忙しくて、子どもが小さくて、高齢で、いろいろな理由で外で買い物できない人にとっては、ワンクリックのショッピングに助けられることも多いだろう。
ただ、自分の財布の中だけを気にしていると、気づかないうちに地域経済や国内経済が思いもよらぬ方向に動いていく。
「お金を誰に渡すのか?」を決めることは、どの人に、どの地域に繁栄してほしいかの意思表示でもあることを忘れてはならない。
子育ての価値はゼロ?
もう一つ問題がある。
お金ばかり気にしているうちに、タダ(無料)の価値を認識しなくなっていることだ。
先ほどの書店の例で問題だったのは、書店で立ち読みするだけして、ネットで購入することだとも言える。リアルな店舗には、ショールーム的な価値がある。しかし、それはタダで提供されるから、価値を感じてもらえないのだ。
ビックカメラなどの家電量販店などもそうだ。さんざん見本を見せて商品の説明をしても、とくに感謝されることもなく、価格比較サイトで調べて最安値で買われてしまう。
この、「タダの価値を認識できない」という問題は深刻で、じつは、そのせいで女性の負担も増えている。
現在の日本の喫緊の課題は、少子化対策だ。現在は1.9人の現役世代が1人の高齢者を支えているが、30年後には1.3人が1人を支える計算になると言われている。この問題を解決するためには、社会全体で子育て支援をすべきなのは明らかだ。
ところが、「子育て」は、GDPに反映されないタダの活動だ。
そのため、おかしな話がはじまる。「たしかに、高齢者を支える現役世代の割合は減りますよ。だけど、女性の労働参加率を高めれば大丈夫ですよ」と主張する有識者が現れるのだ。
「ちょっと待ってくださいよ。これは人口問題の話ですよ」とツッコミたくなる。子どもを産み育てている主婦は、人口問題の解決に大いに寄与しているはずのに「働いていない」とみなされる。
もちろん、「女性の労働参加率を高めよう」という意味が、「活躍したくてもできない女性が活躍できる環境を作ろう」という話ならば、全く異論はない。しかし、子育てを頑張っている主婦に「労働参加してくださいね」と言っているのであれば、見当違いな話だ。
そして、子育てがGDPに反映されないために、子育て支援には政府のお金が回らない。GDPで測定している経済成長に結びつかないから、後回しにされる。
拙著『お金のむこうに人がいる』で伝えたかったのは、道徳の話ではない。お金だけを見て経済を捉えることに慣れてしまったせいで、経済の本質的な問題が見えなくなり、このように事実として自分達が生きにくい社会になり始めているのではないかという危機感があった。
街の書店が消えていく状況は、単にインターネットが発達したという話ではない。お金のことしか考えなくなった現代の私たちに警鐘を鳴らしている。
根本的な問題の存在に気づかなければ、他の店も消え、街から子どもたちの姿が消えることになるかもしれない。
お金と経済について、私たちはみんなで考え直すときに来ているのではないだろうか。