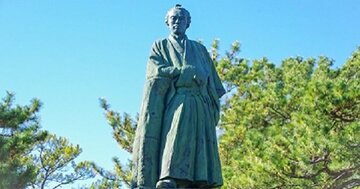東京・大手町にある「平将門の首塚」 Photo:PIXTA
東京・大手町にある「平将門の首塚」 Photo:PIXTA
かつて「新皇」を名乗って勢力を拡大し、短期間ながら関東を支配した平将門。武士が台頭し始めたばかりの時代に、なぜ将門は関東を「スピード制圧」できたのか。筆者は今回、将門ゆかりの地である茨城県八千代町を訪れ、遺跡や歴史・地理を丹念に調べた。そこからは、将門の急成長を支えた「2つの強み」が見えてきた。その実態とは――。(作家 黒田 涼)
「新皇」こと平将門が
関東を「スピード制圧」できた理由とは
平将門(903年頃~940年)は、時代によって評価が乱高下する稀有な武将だ。
東国に拠点を置く江戸幕府は将門を尊重し、将門を祀る神田明神を江戸の鎮守としてきた。だが、明治維新以降は「朝廷に楯突いた謀反人」としてさげすまれてきた。
そして、近年は「源頼朝に先駆けて東国武士政権の端緒を作った」という評価も出てきている。江戸時代は高評化されていたのだから、まあ昔の評価に戻っただけともいえる。
それにしても、まだ武士が台頭し始めたばかりの時代、なぜ将門はあれほどのスピードで関東を席巻し、「新皇」を名乗ることができたのだろうか。
また、それ以降も東国から強い武士が生まれたのはなぜだろうか。
平将門ゆかりの地・茨城県八千代町の近くには、将門の力の秘密をうかがわせる“謎の遺跡”がある。
筆者は今回、遺跡周辺を探訪しながら、これらの疑問への答えを探った。