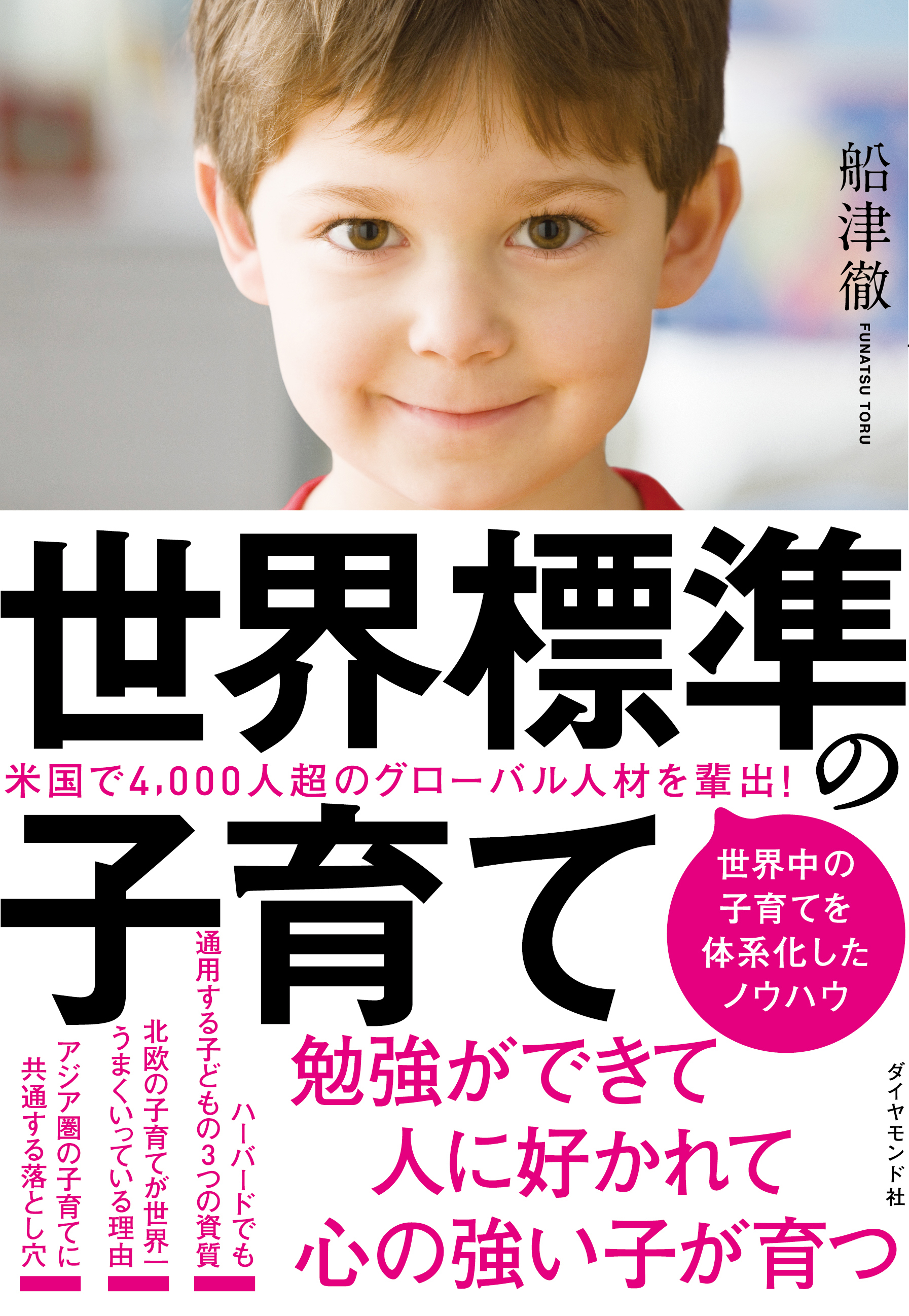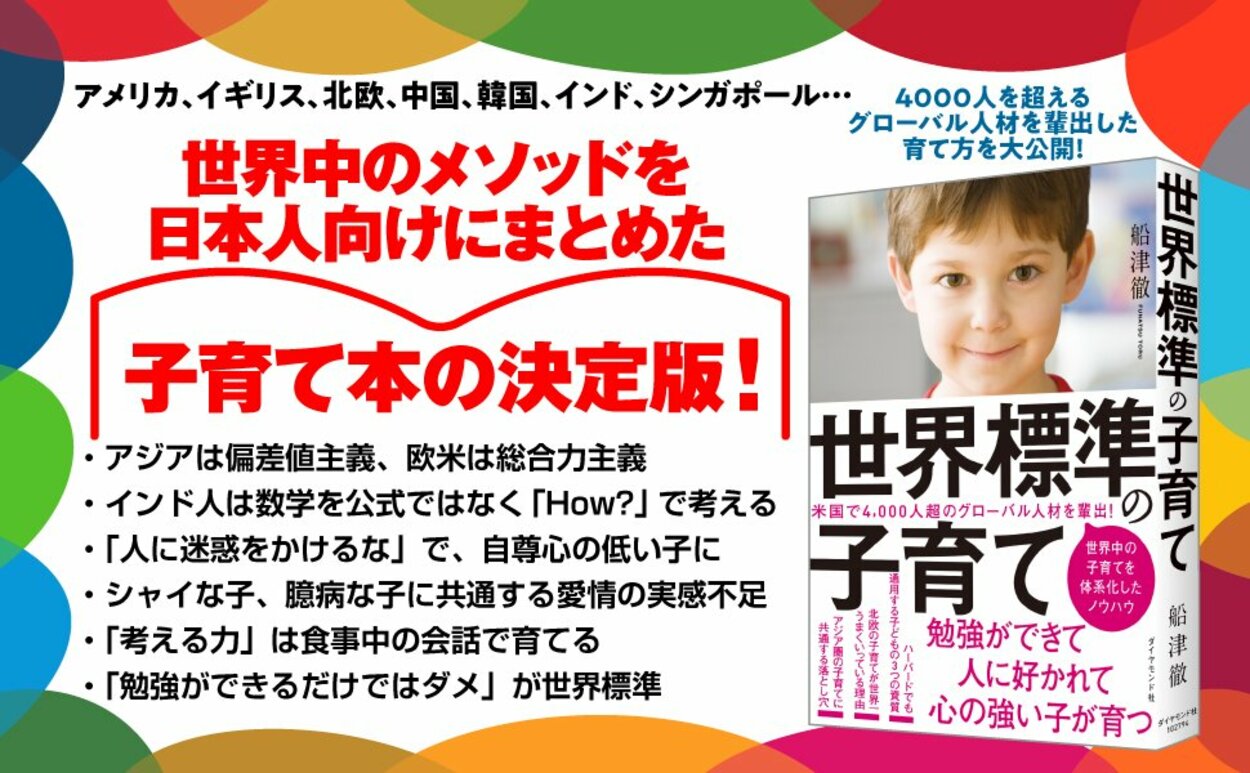子どもたちが生きる数十年後は、いったいどんな未来になっているのでしょうか。それを予想するのは難しいですが「劇的な変化が次々と起きる社会」であることは間違いないでしょう。そんな未来を生き抜くには、どんな力が必要なのでしょうか? そこでお薦めなのが、『世界標準の子育て』です。本書は4000人を超えるグローバル人材を輩出してきた船津徹氏が、世界中の子育ての事例や理論をもとに「未来の子育てのスタンダード」を解説しています。本連載では本書の内容から、これからの時代の子育てに必要な知識をお伝えしていきます。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
習い事はコミュニケーション力を育ててくれる場
日本人は、気の合う限られた集団の中でしかコミュニケーションをとらない傾向があります。
興味や関心、世代の違いを超えてコミュニケーションをとることを苦手と感じ、見知らぬ人との交流をできるだけ避けようとします。
将来子どもがそうならないようにするには、「集団活動」に参加させることが一番です。
特に、球技、ダンス、演劇など、身体を動かすものが重要です(大人もコミュニケーション力が飛躍的に伸びます)。
他の子どもと一緒に身体を動かす活動を通して意思疎通したり、共感したり、伝え合う力を伸ばすことができます。
また、身体を動かすことでストレスを発散させることができるのです。
日本人は子どもの習い事に、水泳、バレエ、ピアノなど、個人競技や一人で練習するものを選ぶ傾向があります。
もちろん、「自信をつけるための習い事」としてはいいのですが、コミュニケーション力を伸ばすことも考えたら、「集団で行なう活動」に参加させてください。
欧米では小学生になると、いくつかの異なる習い事に子どもを参加させます。
スポーツであれば、サッカーとテニスという具合です。身体発達の偏りを減らすこと、同じ集団との交流に子どもの人間関係を偏らせないための配慮です。
また、スポーツと文化活動の両方を経験させるケースも多いです。
サッカーとダンス、バスケットボールと演劇、野球と合唱といったように、これも子どもの人間関係を特定の仲間に偏らせないためです。
複数の習い事を経験することによって、子どもは学校の友だち、スポーツの友だち、音楽の友だちなど、異なる雰囲気を持つ集団と交流することができます。
学校だけでなく、習い事を通して培う幅広い人間関係が、将来の子どものコミュニケーション力に大きな影響を与えます。
消極的な子どもには、まずは家庭で自信を大きくさせる
とはいえ、知らない集団の中に飛び込むことが苦手な子どももたくさんいます。
特に最近は子どもの友だちづくりについての相談が多くなりました。兄弟姉妹が減り、祖父母や親戚との関わりが減り、対人関係を構築する力が弱くなっているのです。
「小学2年生になるのに、誰も友だちがいないんです」という相談もあります。
そういう子どもに対して、無理やり習い事をさせても、友だちづくりはうまくいきません。
「一緒に遊ぼうって言ったらいいでしょ!」と子どもをけしかけるのはさらにNG。
もしも友だちから「イヤだ!」と拒絶されてしまったら、子どもの心は深く傷つき、より人間関係を後ろ向きなものにしてしまいます。
人間関係に消極的な子どもは、まだ外に出るための自信が身についていないので、まずは家庭で子どもの自信を大きくしてあげましょう。
自信がついたら、習い事へ。この際も、あらかじめ家庭で練習して一通りのことができるようになってからにしてください。
何の準備もなく習い事に入れると、また自信を喪失します。家庭で練習させて「人並み以上」にしてから参加させるのが理想です。
親のサポートを子どもが実感できると、子どもはあきらめずに努力を継続するようになります。努力を継続すれば技能は向上し、さらなる自信の強化につながっていくのです。