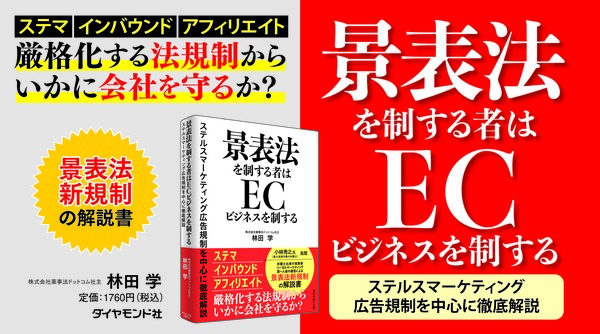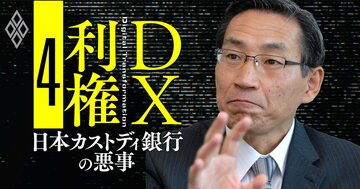photo AC
photo AC
個人、法人の電子商取引(EC)が拡大する一方で、景品表示法(景表法)など、関連法の厳格化も進んでいる。事業者のネット通販の広告表現が思いもよらない違反につながり、課徴金を負うケースも増えている。2023年10月1日からは、景表法に基づき、いわゆるステルスマーケティング規制など、事業者の広告表示に対する規制もさらに強化される。書籍『景表法を制する者はECビジネスを制する』では、景表法を中心に、健康増進法や特定商取引法などの関連法も含め、EC事業者が広告活動を行う際、法律上注意すべきポイントについて解説している。
何が規制されるのか?
まずはステルスマーケティング(ステマ)規制の基本を理解しましょう。
ステマ規制には、各国いろいろな手法がありますが、日本の景品表示法(景表法)が規制するステマとは、簡単にいうと、「真のメッセージ主体の偽り」といえます。
たとえば、A社がライバル社B社の口コミ欄に、A社の従業員Cに「田中太郎」という名前で、B社にとってネガティブな書き込みをさせる。この場合、表面上のメッセージ主体は「田中太郎」ですが、真のメッセージ主体はA社なのでステマになります(なりすまし型)。
A社が、たくさんのフォロワーを持つインスタグラマーDに依頼して、A社を「ヨイショ」する投稿をしてもらう。この場合、表面上のメッセージ主体は「インスタグラマーD」ですが、真のメッセージ主体はA社なので、これもステマになります(第三者発信型)。
ステマの定義は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」。より詳しくいえば「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」となります。
規制のポイントは以下の通りです。
(1)本当は、ほかの人のメッセージ(表示)なのに、それを自分のメッセージ(表示)のように見せる
(2)物販や役務提供に限る
たとえば、私がメディアなどに持ちかけられ、100万円を支払って、メディアから取材を受けたという体裁で登場した場合、これは、(2)の物販や役務提供に関するものではないので対象外となります。
ステマ規制対応の要点とは?
ステマ規制の注意点は以下の通りです。
(1)偽りのメッセージを仕掛けた人(インスタグラムならインスタグラマーに依頼した人)に措置命令(公表される)
(2)(場合により)そのメッセージ(投稿)の削除
(3)(もしかすると)インフルエンサーに損害賠償責任の追及
(4)メディアは、自ら物販・役務提供しない限り責任なし
この規制は2023年10月1日から始まります。対象となるのは、それ以降に行われたものではなく、その時点でウェブサイトにあり、消費者が見ることができるものすべてになります。
SNSマーケティングは、「認知拡大型」から「購入獲得型」に移行しつつあります。そのため、企業としてはステマ(景品表示法3号)だけでなく、インスタグラム兼アフィリエイトの優良誤認(同1号)、有利誤認(同2号)、さらには薬事法も合わせて対応する必要があります。
対応の要点をまとめると、次のようになります。
(1)PR表記をしていればステマになることはないので、広告代理店やアフィリエイトサービスプロバイダー(ASP)を介して大量にインスタグラマーを動かすという場合は、『べからず集』(対応マニュアル)に「すべての投稿にPR表記をせよ」と記載し、それを広告代理店やASPを介して周知させるようにする。
(2)インスタグラム兼アフィリエイトの優良誤認や有利誤認の責任を企業が回避するのも『べからず集』がカギ。商品ごとに優良誤認や有利誤認(さらには薬事法違反)の表現、すなわちNG表現を記載した対応マニュアルを作成し、それを広告代理店やASPを介して周知させるようにする。
(3)薬事法違反を避けるため、成分コンテンツと商品コンテンツを分けた展開をする場合には、東京都の例など、既存の事例を基に考える。