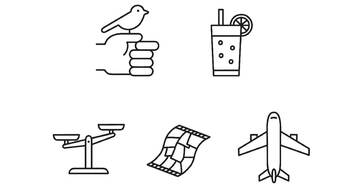2001年に経営学分野で最高峰の学術雑誌『アカデミー・オブ・マネジメントレビュー』上で発表されて以来、アントレプレナーシップや価値創造など幅広い領域に大きなインパクトを与えてきた「エフェクチュエーション」についての日本初の入門書、『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』が発売されました。多くの人にとっては耳慣れない「エフェクチュエーション』という概念について知っていただくため、本連載では同書の一部を紹介していきます。
第6回は、「5つの原則」のうちの1つである「手中の鳥の原則」で説明されるように、「手持ちの手段」を活用することで、大きな事業創造を成し遂げた日本企業の事例を紹介します。
 Photo: Adobe Stoc
Photo: Adobe Stoc
日本のハーブ市場はどのように生み出されたのか
手持ちの手段を活用することで、最適なアプローチが特定できない高い不確実性のなかでも、いかに新たな行動が可能になるかを理解するために、ここでは一人の起業家の例を取り上げたいと思います。それは、40年以上も前の市場の黎明期からハーブを事業化し、川上から川下までの幅広い事業を通じて日本にハーブのある生活(ハーバルライフ)を提案し続けてきた企業、株式会社生活の木の創業経営者、重永忠さんです。
現在では、ハーブやアロマテラピーをまったく知らないという人のほうが珍しいかもしれませんが、重永さんが1977年に事業を開始した当時の日本では、「ハーブ」という言葉さえ聞いたことがない人がほとんどでした。生活の木は、そこから使用シーン開発や商品開発を行い、楽しみ方を提案することによって、それまで日本になかった新規のビジネスと、日本におけるハーブやアロマテラピーの文化を創造してきた企業であるといえます。
ここで着目したいのは、そうした時代に重永さんがいち早くハーブ事業に着手をした背景には、彼自身の手持ちの手段の活用があったという点です。原宿・神宮前交差点からすぐの、人通りの賑やかな表参道沿いに、全国約100店舗の直営店を運営する「生活の木」の本店ビルがあります。重永さんは、この場所で商売を営む家の三代目として生まれ育ちました。
祖父は写真館、父は西洋陶器の製造販売という、いずれも当時まだ珍しかった事業を起こし、全て自前主義で経営していました。重永さん自身も、「誰もやらないことを極めることで優位に立つ」という主義を父親から受け継いでいると自覚しており、それは「私は誰か」の要素であったといえます。
また、「何を知っているか」には、少年時代の個人的な体験が関わっていました。それは、重永さん自身が小学校6年生の時に重い腎臓病を患ったことでした。病気のために野球が大好きだったスポーツ少年がまったく運動できない状態になったばかりでなく、ついには、西洋医学の治療を受けていたお医者さんから一生治らないことを宣告されてしまいます。しかし、その後、母親が紹介を受けた漢方医に通うようになり、処方された漢方薬を服用し続けていると、不治といわれた腎臓病が中学2年生の時に完治したのでした。この漢方、つまり植物の恵みで病気が治った体験があったからこそ、アメリカの視察旅行のお土産として父親が持ち帰ったハーブやポプリに強い可能性を感じ、父親の西洋陶器のお店の一角で、輸入したポプリを販売する事業に着手したのでした。
ただし、その後の展開は順調とはほど遠いものでした。当時のハーブは、蛇の“ハブ”と聞き間違えられるほど日本人にとって認知度が低く、社員からですら、「そんなただの葉っぱが売れるわけない」と、店頭に置くことを拒否される状況だったのです。そうしたなかでも、重永さんたちは試行錯誤を続けていました。人通りの多い立地と、文字通り売るほどあった西洋陶器を活用して、ハーブティーを提供する喫茶店事業を営んだ時期もありましたが、多くの人々にハーブのよさを実感してもらうには至りませんでした。
転機となったのは、1980年に、主人公がストーリーに沿ったポプリづくりをする少女漫画、『あこがれ♥二重奏』(佐藤まり子)がヒットし、全国の小・中学生の間にポプリブームが起きたことでした。実はこの漫画は、当時生活の木でアルバイトをしていた漫画家志望の大学生に依頼し、重永さんたちが出版社に持ち込んで実現した企画でした。
毎回の漫画のなかではポプリのレシピも掲載され、また生活の木とのタイアップ企画として「オリジナルポプリコンテスト」を開催したところ、20万件を超える応募が殺到し、1979年に開始した通信販売の会員も急増することになりました。こうした展開は、まさに手持ちの資源のなかの、「誰を知っているか」から「何ができるか」を発想し、行動したことの成果であるといえるでしょう。
手持ちの手段(資源)を考えるうえでのポイント
重永さんの事例からは、手持ちの手段(資源)の活用を考えるうえでの、いくつかのポイントを確認することができます。
まず、「私は誰か(Who I am)」には、起業家自身のアイデンティティ(自分はどのような人間か)に関わるものであれば、どのような要素を含んでもよいといえます。他の人たちと比べてユニークな客観的な特性以外にも、起業家自身が「自分をどのような人間だと信じているのか」、あるいは「自分はどのような存在でありたいと考えるのか」といった、主観的な自己認識もまた、「何ができるか」に影響を及ぼす、極めて重要なアイデンティティの構成要素であるといえます。
経営思想家のピーター・ドラッカーは、著書のなかで次のようなエピソードを紹介しながら、「自分は何によって覚えられたいのか」を問うことの重要性を語っています。「私が13歳のとき、宗教の先生が『何によって憶えられたいかね』と聞いた。誰も答えられなかった。すると、『答えられると思って聞いたわけではない。でも50になっても答えられなければ、人生を無駄に過ごしたことになるよ』といった。
ここで、「自分は何によって覚えられたいのか」というのは、いま自分が何をなすべきかに関する問いであり、自己刷新を促すための具体的な行動を導くものである、とドラッカーは説明しています。「私は何か」が、不確実性のなかで具体的な行動指針となることが説得的に理解できる指摘であると思います。
手持ちの手段(資源)の第2のカテゴリである、「何を知っているか(What I know)」に関しても、広く解釈すべきであることが理解できます。それは専門的な知識やスキルに限定されるわけでもなければ、多くの人が信じている客観的事実である必要もありません。仮に、ほとんどの人々の賛同を得られなかったとしても、起業家が自らの体験に基づいて正しいと認識していること、信念を持っていることが、具体的な行動を生み出す強力な基盤になりうることが、重永さんの事例からわかります。
このように、手持ちの手段(資源)のうち、起業家自身のユニークな特性や価値観、さまざまな人生経験に基づく知識から、「何ができるか」を発想して行動に着手することにより、他の人では生み出すことのできないような独自の方向性に道が拓かれます。実際に、サラスバシーの意思決定実験に参加した27名のエキスパートの起業家は、実験開始時点ではまったく同じ条件設定が与えられていたにもかかわらず、それぞれに固有の手持ちの手段を活用して意思決定を繰り返した結果、まったく異なる市場機会に到達したのです。
第3のカテゴリである「誰を知っているか(Who I know)」に関しても、より広い視点で捉えることが有効です。このカテゴリは、起業家が頼ることのできる社会的ネットワークを指しますので、たとえば親しい友人や家族、同僚といった、直接的にアプローチが可能で、相談しやすい人々を、真っ先に思い浮かべるかもしれません。一方で、ハーブ事業の売り上げ拡大にとって、たまたま漫画を描ける大学生のアルバイトがいたことが重要であったように、偶然に知り合った人々や、必ずしも関係性は強くなくともアプローチ自体は可能な人たちを、「誰を知っているか」に含めて考えることも重要です。
スタンフォード大学の社会学の教授であるマーク・グラノヴェッターの有名な論文に、「弱い紐帯の強み(The strength of weak ties)」という研究があります。この研究では、アメリカの転職経験者をランダムに抽出し、彼らの転職につながった仕事の重要な情報をもたらした人との接触頻度を尋ねた結果、8割以上が「時々」あるいは「まれに」しか会わない人々であることが明らかにされました。
つまり、頻繁に接触する相手(強い紐帯)よりも、たまにしか会うことのない知人(弱い紐帯)のほうが、仕事上の重要な情報の提供者として役立ったという結果だったのです。これは、親密な関係性をすでに築いている人たちというのは、自分と同じ情報を持っている可能性が高い一方で、つながりの弱い人々は異なる社会的ネットワークに属しているため、自分にとって新しい情報をもたらしてくれる可能性が高いことを示唆します。「誰を知っているか」を考える際にも、必ずしもつながりが強くない人たちを含めることで、新しい行動の可能性が拓かれることがあるでしょう。
また、あなた自身の直接的な知り合いではなくとも、別の誰かを介してつながることができる人もまたアプローチ可能な人々であり、やはり「誰を知っているか」に含むことができると考えられます。6回知り合いをたどることによって、世界中の任意の人物の誰とでもつながることができることは、イェール大学の心理学の教授スタンレー・ミルグラムによる実験を通じて証明され、「6次の隔たり(Six Degrees of Separation)」として知られています。こうした事実を踏まえれば、仮にあなたが直接接触可能な人々のなかには、パートナー候補が見つからなかったとしても、そうした人々を介してつながることのできる「知り合いの知り合い」に、重要な役割を果たすパートナーが潜在している可能性は高いと考えられます。