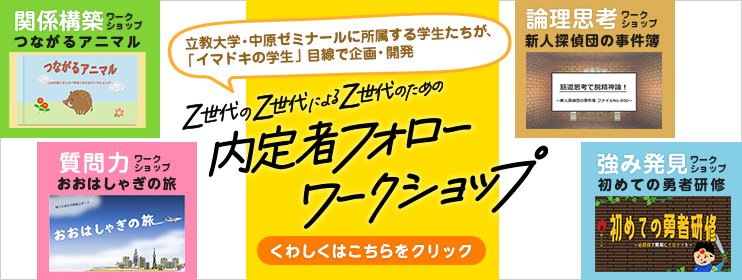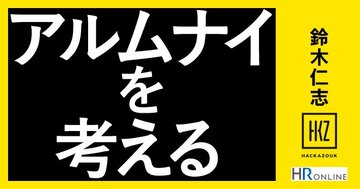自律的で能動的な学びを意識することが大切
先日、冒頭で紹介した授業「社会教育計画論」に関わっている教員3名が、「社会教育の魅力」をめぐって対談を行(おこな)った。社会教育の基礎知識について講義し、学生の関心と社会教育との距離を縮め、教員がそれぞれに取り組んでいる社会教育実践について語った後の対談で、私たち教員の関心の背景や思いに焦点を当てたものだった。
この対談を聞いた1年生の学生が、次のようなコメントを寄せてくれた。
“「教育」という言葉には、一方的に押し付けられる、マイナスなイメージを持っていましたが、「社会教育」は相互に学び合う面が強いことがわかりました。社会教育は「自由」なところがおもしろいと先生がおっしゃっていたのが印象的でした。それは私がいままで抱いていた「教育」という言葉のイメージと真逆だったからだと思います。確かに学ぶのは自分のためであり、自分の好きな時に好きなことを学ぶべきだから「自由」ということは大切であり、そこが学校教育との大きな違いだと思いました”
自律的で能動的な学びを意識し、自分たちの学びの実践につなげていくことが、大学教育の出発点だと、私は思う。その学びの集大成が卒業論文ということになる。
本稿を書いている1月は、そうした卒業論文の締め切りのシーズンである。1年生からの積み重ねが、正直に論文に表現される。私のゼミでは、自分なりの観点で問いを立て、その問いに答えていくスタイルを大切にしている。まず、自分なりのこだわりが問いに表れてこなければならない。自分が大切にできる問いであれば、学生たちは論文を書くという作業に楽しさややりがいを感じる。人から与えられたテーマでは、学生たちの力は発揮されにくい。
「やる気にならないけど、卒業するために仕方なく取り組む」卒論ではなく、「おもしろいテーマがみつかったから、夢中になって取り組む」卒論へと学生たちを導くためには、それなりの月日がかかる。学生たちが4年間も大学に在学するのには理由があるのだ。「学びほぐし」をして、「変容的学習」を経験することで、自分なりの夢中になれるテーマをみつけ、そのテーマに即した学びを重ねることは一朝一夕にはできない。
本稿では、大学で行われている教育の一部にスポットを当てたが、自律的で能動的な学びは、生き生きとした人生、活力のある社会を形づくるために不可欠なことなのだと、私は強く思う。自律的で能動的な学びは、子どもから高齢者まですべての人の生活に根づくべきだと考える。学校教育は変わっていく必要があり、企業には従業員の学びに注目してもらいたい。若い従業員に対して、自社の伝統や文化に合わせることを求める場合、雇用側は少し立ち止まってもらいたいと思う。周囲の視線に過敏な若者たちは、自分を見失うリスクに囲まれているのだから、若者自身の内側から生まれてくる言葉や行為に注目してほしい。
例えば、「礼儀正しい挨拶は、顧客や取引相手との良好な関係を築くうえで欠かすことができない」というのが企業の常識だ。だから、「正しい挨拶の仕方」を身につけることは、社会人の初歩的な学びになっている。けれども、そもそも、挨拶は、感謝の気持ちや親愛の気持ちを伝えたいという個々人の内面の動きが外に表現されたものである。まずは自分の気持ちが動いているかが大切であり、その気持ちの伝え方は個々人によって異なってもよいはずだ。もちろん、「正しい挨拶の形」を身につけておいたほうが、気持ちが動いていない場合でも対処できるし、相手を嫌な気持ちにさせるリスクも低い。その意味で、「正しい挨拶の形」を覚えることも大切だ。相手との距離を適切に保つために、あえて「正しい挨拶の形」でよそよそしさを醸し出すこともあるかもしれない。しかし、手段としての挨拶よりも大切なのは、相手に自分の気持ちをしっかり伝えること、また、それ以前に、相手に対する感謝や親愛の情を育てることではないだろうか。
感謝や親愛の情というものは、教えられて身につくようなものではない。お互いに人として尊重される関係性の中で、自分自身を大切にし、他者を大切に思うところから生まれてくるものだ。だから、企業の中で従業員個々人が大切に扱われ、従業員の間にあたたかい雰囲気があるかどうかという、日々の職場のありようが鍵を握る。
自律的で能動的な学びは、身近で些細なことの積み重ねによって、生活や仕事の中に芽生え、根づいていくものだと思う。企業の経営層や人事・総務部門のみなさんには、従業員の心が動く経験に注目して、その心の動きに即した表現や行動を支える工夫をしていただきたい。心が動き、内側から出てきた言葉や行為にこそ、主体性の実体がある。従業員に「主体的に働いてほしい」と考えるのであれば、従業員の心を動かすことが大切だ。
挿画/ソノダナオミ