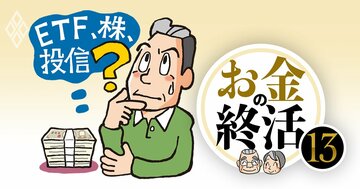私も事故調査などを通じてたくさんの失敗当事者から話を聞いてきたので、この感覚はよくわかります。世の中の人たちにわかりやすい形で広く伝えるためには、第三者の視点で客観視し、知り得たことをきちんと整理する必要があります。これにもなるべく当事者の視点を盛り込みながら行ってきたつもりですが、すべてを取り込むことはできません。そもそも私は失敗当事者ではなく、第三者の立場で話を聞いているので、把握できない点や理解が及ばない点が出てくるのは当然なのです。
たとえば、私が失敗の当事者と同じ経験をしていたら、理解はより深まるでしょう。彼らが主観視に基づいて語ったことのうち、どれが大事で、どれが本質に結びつくかの判断もより正確にできたことでしょう。長谷川さんが感じたのはそういうことではないかと思いました。実際にそんなことはできませんが、例えるなら「此岸」という現実世界にいる私たちが死んだ後の世界(彼岸)を正しく理解するのは難しく、正確に知るには実際に「彼岸」に渡った人から話を聞くのが一番ということです。
長谷川さんの話を聞いていると、客観視することは玉子の殻を外から見ることで、殻の内側から見ること、感じることは主観視することだと気づきました。
畑村がなんだかおかしなことを言っていると思われたかもしれません。しかし、死後の世界はともかく、失敗や老いのことなら、じつは当事者の主観視に触れるのはそれほど難しくありません。経験者は世の中にあふれるほどいるので、その気になればいくらでも話を聞くことができます。それなのにあまり行われていないのは、主観視の価値が認められていないからにほかなりません。
もちろんその背景には、そもそも人になにかを伝えたり、相手の言いたいことを正確に受け取るのは難しく、話し手が価値のある話をうまく伝えることができない、聞き手は傾聴すべき話を上手に引き出すことができないという、コミュニケーション力の問題があるように思います。これはどこの世界でも起こることですが、老いに関する問題ではとくに深刻な状況を招きやすいようです。
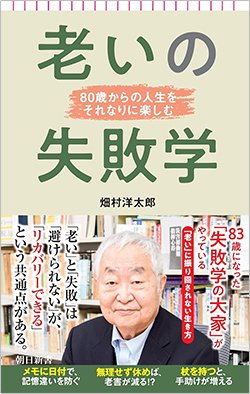 『老いの失敗学』(朝日新聞出版)
『老いの失敗学』(朝日新聞出版)畑村洋太郎 著
いずれにしても、ある問題の研究なり対策を客観視だけをベースに行うのは適切ではありません。多くの人の主観視を取り込むのは面倒でたいへんなことですが、少しずつでも行ったほうが中身をより充実したものにできます。いまの世の中は「客観的でなければならない」という価値観で動いていますが、本当は「客観的なものに加えて、主観的なものも必要」なのです。どちらか一方だけだと不十分で、両方を取り込むことが大事です。
失敗学では、後者を積極的に取り込むことを心がけてきました。その成果をこの目で見てきたので、老いの問題の研究や対策も後者をもっと取り込んでいけばいいのにと考えています。そうすることでより充実したものにできるのだから、やらないのはじつにもったいないと思います。