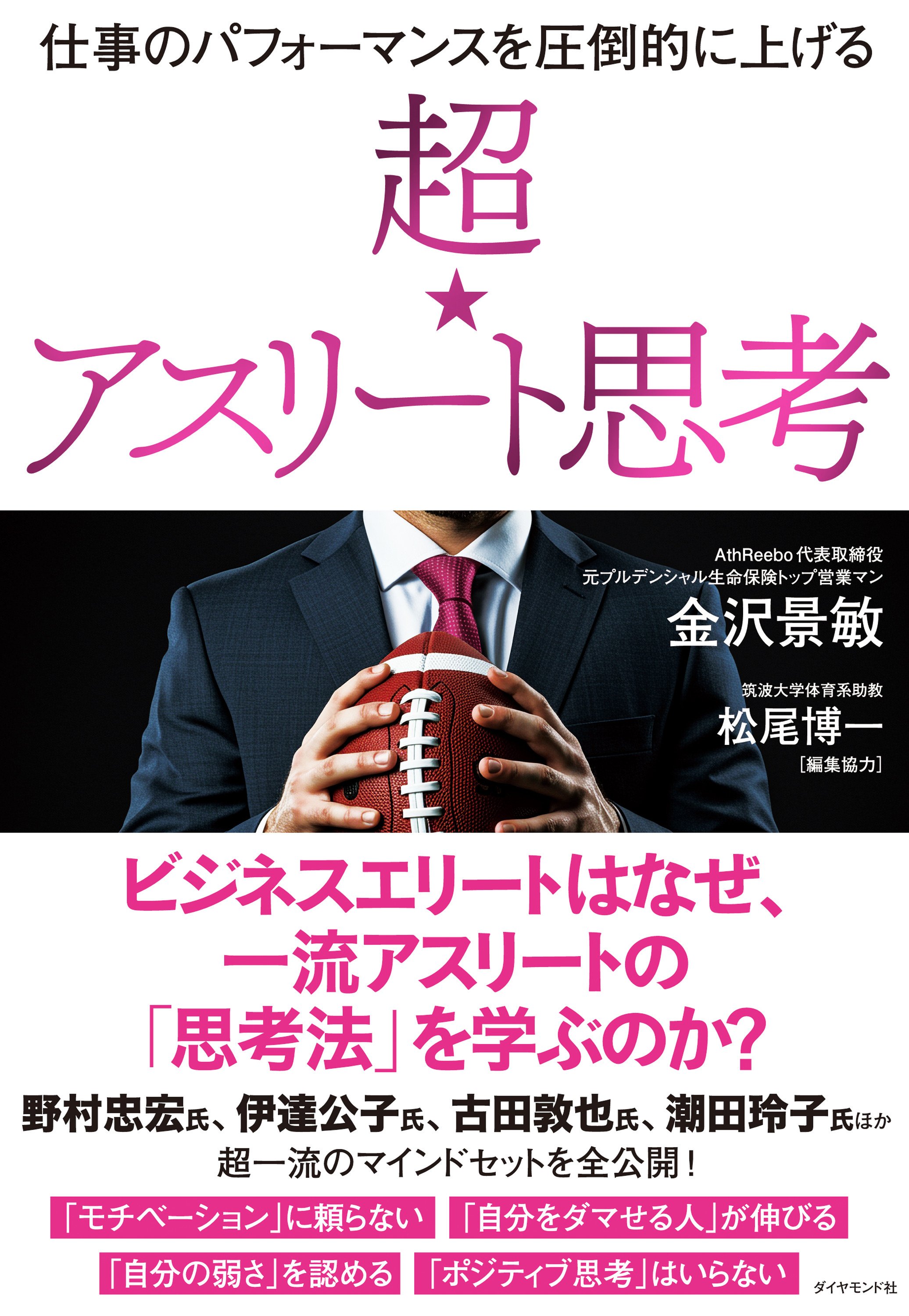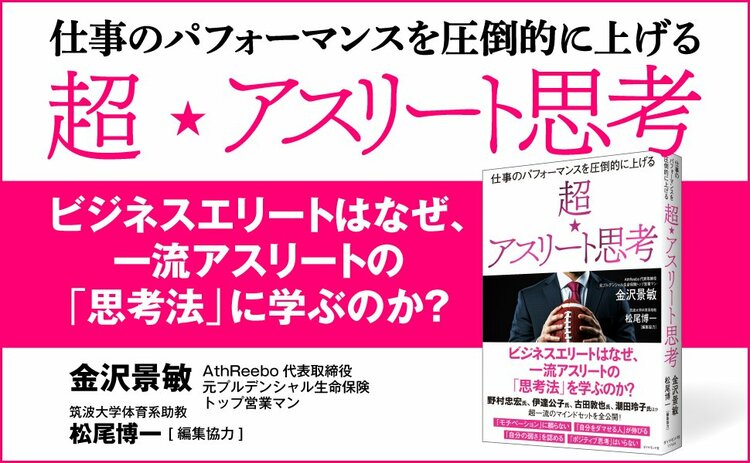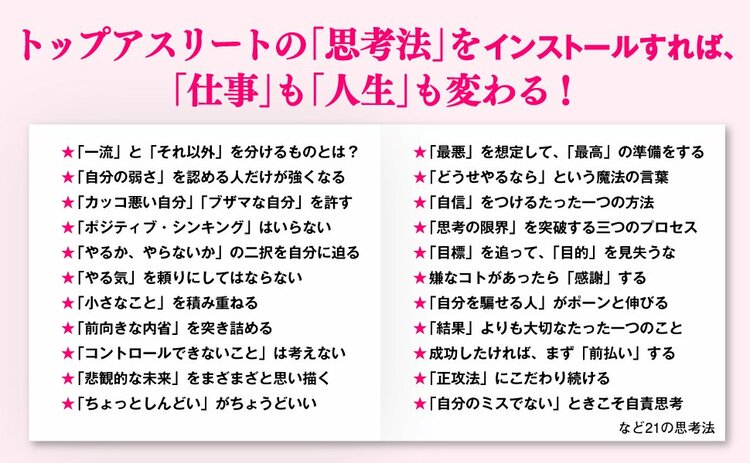「結果を出す人」は、何を考えているのか? それを明らかにしたのが、プルデンシャル生命で伝説的な成績を残したビジネスアスリート・金沢景敏さんの最新刊『超☆アスリート思考』です。同書で金沢さんは、五輪柔道3連覇・野村忠宏さん、女子テニス元世界ランキング最高4位・伊達公子さん、元プロ野球選手・古田敦也さん、元女子バドミントン日本代表・潮田玲子さんほか多数のレジェンドアスリートへの取材を通して、パフォーマンスを最大化して、結果を出し続ける人に共通する「思考法」を抽出。「自分の弱さを認める」「前向きに内省する」「コントロールできないことは考えない」「やる気に頼らない」など、ビジネスパーソンもすぐに取り入れることができるように、噛み砕いて解説をしています。本連載では、同書を抜粋しながら、そのエッセンスをお伝えしてまいります。
 写真はイメージです Photo: Adobe Stock
写真はイメージです Photo: Adobe Stock
「目標」を追い求めるのが危険なワケ
「練習のための練習をしてはいけない」
伊達公子さんはいつも、ジュニアの選手たちにそう伝えているそうです。
優秀な選手であればあるほど、日々の練習メニューはハードなものになりますが、それゆえに、その練習メニューをこなすだけで精一杯になってしまいがち。だけど、それでは練習の効果は大きく損なわれてしまうことに注意を呼びかけていらっしゃるのです。
では、何のために練習をするのか?
言うまでもなく、「試合で勝つため」です。
「試合で勝つため」には、自分のフットワークのどこをどう修正すべきなのか?
「試合で勝つため」には、自分のスマッシュをどう磨くべきなのか?
こうした問題意識をもって練習に取り組むからこそ、プレイの質は上がるのです。だから、伊達さん自身、現役時代から「練習のための練習」をするのは大嫌いで、「試合で勝つための練習」を徹底したそうです。だからこそ、あそこまでの成績を残されたのだと思います。
これは要するに、「目的と目標の混同」の問題と言えます。
両者の定義を改めて確認しておきましょう。
目的:「なぜ、それをやるのか」という根本的な理由・意義
目標:目的を達成するための具体的な到達点や行動指針
つまり、先ほどのケースは、次のように整理できるわけです。
本来的には、テニスの練習の目的は「試合に勝つ」ことであり、この目的を達成するために、「1日○本のサービス練習をする」とか「1日○分のフットワーク練習をする」といった目標が設定されます。
ところが、日々の練習に取り組むうちに、「1日○本のサービス練習をする」といった目標が「目的化」してしまうことがしばしば起きる。その結果、懸命に練習を頑張ったつもりでも、「試合に勝つ」という本来の目的を達成することができなくなってしまうのです。
「間違った努力」に陥ってしまう
残念なメカニズムとは?
これは、仕事でもよくあることです。
たとえば、駆け出しの営業マンは、「ロールプレイング」の経験を重ねることで、お客様との面談技術を高める必要がありますが、これが自己目的化してしまうケースがよくみられます。つまり、お客様が会ってくださる時間帯(朝9時から夜9時くらいまで)に「ロールプレイング」を行うことで満足している営業マンがいるのです。しかし、これでは絶対に結果は出ません。
営業マンの仕事は、お客様と出会わなければ何も始まりません。であれば、商談可能な時間帯はすべてお客様との面談で埋め尽くし、隙間時間や移動中など、お客様とのアポが入らない時間帯に「ロールプレイング」を行ったほうがより目的を達成することに近付くはずです。
あるいは、組織マネジメントでも同じような現象は起こりえます。
たとえば、「前年比で売上120%必達」といった全社目標を掲げることはよくありますが、この数値目標が「目的化」してしまって、強引な営業をする社員が増えたり、無理な値引きが横行したりすることがあります。
その結果、顧客からの信頼を失ったり、利益率が低迷したりして、「顧客満足度を高めることで、持続的に事業を成長させる」といった本来の事業目的から逸脱してしまうという結末を招くわけです。
このように、「本来の目的」を見失うことには大きなリスクが伴います。
このことは誰にでも、簡単に理解できるはずのことですが、僕たちはしばしば、単なる目標を「目的化」してしまって、そのことに気づけないまま「墓穴」を掘り続けてしまうことがあります。
なぜ、そうなってしまうのか?
「頑張っている自分」に酔ってはいけない
僕は、「努力の罠」にはまってしまうからだと思っています。
要するに、「頑張っている自分」に酔ってしまうということです。
僕自身、京大アメフト部時代には、日々、吐き気を及ぼしそうなほどの過酷な練習・トレーニングを強いられていましたが、それをやり切ったときには、ただそれだけで深い満足感や達成感を感じたものです。
たとえ「試合で勝つ」という本来の目的を見失った「練習のための練習」に終始していたとしても、「苦しい練習をやり切った」という精神的な報酬は与えられる。しかも、一緒に頑張ったチームメイトとも、「俺たち頑張ってるよな!」という一体感のようなものを共有できてしまうという側面もあります。
そのため、「練習のための練習」=「悪い努力」にはまっていることに気づくことができないまま、ひたすら自己満足・自己陶酔という「快感」を追い求めてしまう。その結果、気がついたときには、自ら掘った「墓穴」に落ち込んでしまっているというわけです。
トップアスリートは、あらゆる練習に「意味づけ」をする
この点、やはりトップアスリートは違います。
彼らはみな、徹底的に「勝つ」ことにフォーカスしています。
だから、「頑張っている自分」に陶酔するようなことはなく、冷徹なまでに「本来の目的」を追求し続けます。それもトップアスリートたる所以なのだと思うのです。
たとえば、元プロ野球選手の松坂大輔さんはこのように話します。
「僕は小さい頃から、野球チームで練習しているときに、『この練習、何の意味があるんだろう?』と不思議に思うことがたくさんありました。そういうことがすごくたくさんあったんですが、そういう練習って本当にもったいないと思ってきました。
実際、その練習を命じたコーチにとっては、次の練習までの時間繋ぎという程度の練習ということってあると思うんです。だけど、僕は、そういう意識で練習をするのはすごくもったいないことだと思うので、自分なりに、『この練習は、こういう結果に絶対に繋がる』という意味づけをしたうえで、練習に取り組むようにしていました」
すごいですよね?
このように、どんなことに対しても、自ら「目的」を設定することで、その行為に意味づけをすることができれば、「悪い努力」にはまるといったリスクは避けることができるに違いありません。
たとえば、先ほどの会社のように、「前年比で売上120%必達」という全社目標が掲げられても、松坂さんのような意識をもつ人材であれば、周りに流されることなく、「顧客満足度を高めることで、持続的に事業を成長させる」という本来の事業目的を見据えて、「正しい努力」を重ねることができるはずだと思うのです。
一流選手が「調子の悪い日」に練習をやめる深いワケ
あるいは、伊達さんもすごいです。
すでに述べたように、現役時代の伊達さんにも、朝からやる気が湧かないことがありましたが、そんなときもとにかくテニスコートに行って、1時間はボールを打つようにしていました。そうすることで、やる気が出てくることを知っていたからです。
ただし、1時間ほどボールを打っても、どうしても調子が上がらず、やる気も出ないときもある。そんなときは、スパッと練習をやめて、その日を「オフ」に切り替えたり、トレーニングだけの日にしたりするというのです。
なぜか? 調子の悪い日に、無理にボールを打っていると、悪いフォームを身につけてしまいかねないからです。であれば、思い切って「オフ」に切り替え、気分転換をして、明日からの練習に備えたほうが、「試合に勝つ」という目的に近付くことができる。「試合に勝つ」ために「オフ」に切り替えるのです。ここには、「頑張っている自分」に対する陶酔など皆無。つまり、三流はひたすら頑張り、二流は目標を追い求め、一流は目的合理性を徹底的に追求するのです。
(この記事は、『超⭐︎アスリート思考』の一部を抜粋・編集したものです)
AthReebo株式会社代表取締役、元プルデンシャル生命保険株式会社トップ営業マン
1979年大阪府出身。京都大学でアメリカンフットボール部で活躍し、卒業後はTBSに入社。世界陸上やオリンピック中継、格闘技中継などのディレクターを経験した後、編成としてスポーツを担当。しかし、テレビ局の看板で「自分がエラくなった」と勘違いしている自分自身に疑問を感じ、2012年に退職。完全歩合制の世界で自分を試すべく、プルデンシャル生命に転職した。
プルデンシャル生命保険に転職後、1年目にして個人保険部門で日本一。また3年目には、卓越した生命保険・金融プロフェッショナル組織MDRTの6倍基準である「Top of the Table(TOT)」に到達。最終的には、TOT基準の4倍の成績をあげ、個人の営業マンとして伝説的な数字をつくった。2020年10月、AthReebo(アスリーボ)株式会社を起業。レジェンドアスリートと共に未来のアスリートを応援する社会貢献プロジェクト AthTAG(アスタッグ)を稼働。世界を目指すアスリートに活動応援費を届けるAthTAG GENKIDAMA AWARDも主催。2024年度は活動応援費総額1000万円を世界に挑むアスリートに届けている。著書に、『超★営業思考』『影響力の魔法』(ともにダイヤモンド社)がある。