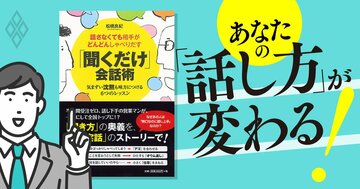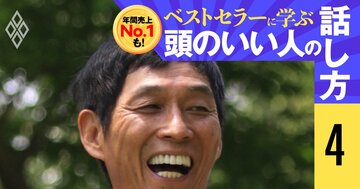頭がいい人は、
地道な努力を怠らない
最近は大学入試の形態が変わってきました。同じ問題を一斉に解く一般入試以外に、 自己推薦やAO入試という方法で選抜されるようになりました。いわゆる入試の多様化です。
そこで感じるのは、受験日に向けて何年もコツコツと準備してきた学生というのは、 やはりすばらしいということです。個性やクリエイティブというより前に、合格するためにやらなければならないことを理解し、受け止め、それを長期にわたり持続することができる人は、当然ながら粘りもあります。
サッカーであれば、まずはボールを蹴るという基本技術がしっかりしていなければ困ります。それには、受験勉強のようにコツコツと繰り返して練習をする必要があります。そのうえでクリエイティブ性が加わると、その選手は非常に強いということになります。
近年、教育の現場では「表現力」というものが問われるようになりました。これは思考判断といわれるものです。新しい価値を見出す知性であり、頭がいいといわれる人が共通してもっている力です。
これを日常的に活用できているのが、たとえば数学者であり、科学者であり、将棋の棋士などもそうです。もちろん、スポーツ選手だってそうでしょう。
今までの方法を学習して知っていて、そのうえに新しい価値を加える。つまりは、 付加価値を見つける力です。「付加」とはすなわち、今までのことをわかっているということ。
それには先述したような、コツコツと積み上げる受験勉強のように、地道な学習の蓄積が必要であることはいうまでもありません。
新たな付加価値を生み出せる人は、受験生型の努力を決して怠らなかった人という言い方もできるでしょう。
体格に恵まれた選手より
「頭がいい」選手
スポーツの世界でも、監督の立場からすれば「頭がいい選手」は大変にありがたい存在です。たとえ身長が低くて体格には恵まれていなくても、頭がいい選手を監督は使いたいと考えます。
それは、監督が求めることをスピーディーに理解し、それを実行できるからです。
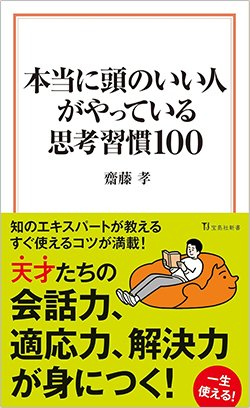 『本当に頭のいい人がやっている思考習慣100』(宝島社新書)
『本当に頭のいい人がやっている思考習慣100』(宝島社新書)齋藤孝 著
監督が自分に何を求めているかを正確にくみ取る。すなわち戦術理解力に長けているのです。
「この試合、相手がこう来るだろうから、今日はこういう戦術でいく。君はこういう役割だ。しかし、相手に大きな変化があれば、それに応じて変更する」と監督が伝えると、それをすぐに理解します。実際、それができない選手もけっこういるのです。
これがもう少し上のレベルの選手になると、用意したシステムが通用しないときに、それを自分でアレンジすることができる。
こうした融通の利く対応力。それこそが、頭がいい人の特徴といえるでしょう。