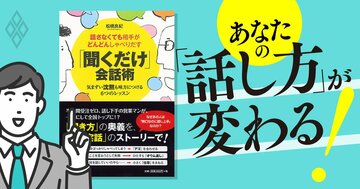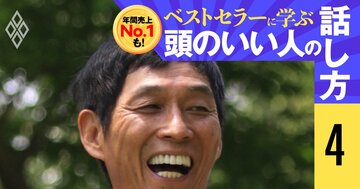写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「頭がよくなりたい」と願う人は多いが、そもそも「本当に頭のいい人」とは一体どのような人物なのか。勉強ができる人、クリエイティブな人、個性的な人…いまの時代に必要な「頭のよさ」について、明治大学教授の齋藤孝氏が解説する。本稿は、齋藤孝『本当に頭のいい人がやっている思考習慣100』(宝島社新書)の一部を抜粋・編集したものです。
「頭がいい人」は
「周りの人を幸せにする」
2023年は、生成AI元年と言える年でした。対話力と創造力を備えたChatGPTを活用する際に、本当の頭のよさが問われる気がしました。
どんな質問をするか。回答をどう発展させ、現実の改善にどうつなげていくか。
頭の「強さ」とメンタルタフネスが、超AI時代には、より重要になってきます。
人から話を聞いて答えたり、本を読んでその内容を人に話したりする行為は、私たちが日常行っている基本的なコミュニケーションです。しかし、誰もが同じようにしているように見えるその行為も、その中身は人によってまったく異なります。
正しく聞いて、正しく返す。あるいは正しく読んで、正しく伝える。シンプルにいえば、頭がいい人はこのインプットとアウトプットが正しくできている人です。
頭がいい人は、言いたいことを短い時間で要約し、わかりやすい言葉で無駄なく伝えることができ、また聞いている側は無駄な時間を使わず、情報を楽にインプットできます。
相手の時間を奪わない、相手に迷惑をかけない人は「頭がいい」ということです。
頭がいい人は会話が上手ですが、それは「おしゃべり」が上手という意味ではありません。ペラペラと口が回る人を「頭がいい」と見る人もいますが、頭がいい人は情報を整理する力や要約する力、構成する力、説明する力などが備わっている人です。
会話とは、イメージでいえば川の流れのようなものです。聞いている相手が、川にジャブジャブとつかって泳いできてくれれば、こちらの意図を伝えることはできます。 しかし、流れが急で、泳いで渡るのが難しいと相手が感じたなら、踏み台となる石を置いてあげることで、その人は容易に川を渡ることができるはずです。
会話における「踏み石」とは、カギとなるワードです。相手が川で溺れたり、流されたりしないように、キーワードとなる石を3つほど置いてあげて、その順に沿って説明することで、相手も踏み石をピョンピョンと渡るように理解できるわけです。会話ひとつをとってみても、頭がいい人はこうしたスキルを普段から何げなく使っているものです。
こうした力を備えた人と組んで仕事をすると、そうでない人との仕事と比べ、成果は格段に期待できますし、何より仕事の最中も余計なストレスを感じなくてすみます。
必然的に、職場での信頼も高まり、「あの人は頭がいいね」という評価につながるわけです。頭がいいということは、周りの人を幸せにするということなのです。