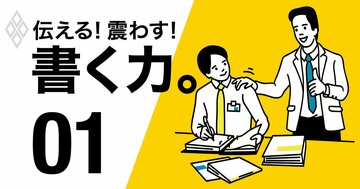高田強さん(著者撮影)
高田強さん(著者撮影)
近年、リモートワークが盛んになる中、ビジネスシーンで重要視されるようになったのが、文章を書くスキル。メールやチャットをはじめ、ブログ・SNS、企画書など、業務の各所で文章を書く力が求められるようになっている。一方で、社会人1年目や若手のビジネスパーソンの中には、なかなかコツをつかむことができず、頭を悩ませる人も多いことだろう。一体、「伝わる文章」には、どのようなテクニックが必要なのか。その疑問について、フリーの編集者でライターとしても活躍し、24年4月末にはビジネス文章のコツを豊富に紹介する書籍『文章コツ100』(メディアパル)を上梓した、高田強さんに話を聞いた。
興味をそそる順番で飽きさせない文章に
1986年、関西を代表する情報誌だった『プレイガイドジャーナル(通称ぷがじゃ)』(エイエヌオフセット)の編集者として、キャリアをスタートさせた高田さんは、「とにかく文章を書くことが苦手な編集者だった」と当時を振り返る。
「出版業界を志したわけですから、もちろん本を読むことは大好きでしたが、日記を付けるとか、文章を書くという習慣がありませんでした。だから、周囲の人たちと比べて、文章を書くことに慣れてないんです。書く時間も長く掛かるし、比喩表現もそれほど上手くはない。幸いにして、潜り込んだ『ぷがじゃ』では、映画の紹介を中心に、私情を挟まず淡々と書く業務が大半でしたから、なんとか乗り越えられたという感じでしたね」
文章作成に苦手意識を持っていた高田さんは、その後、リクルート社の『フロム・エー』や講談社の『KANSAI1週間』などで、編集者として仕事をしながら編集とライティングのスキルを磨いていく。その中で、上手に伝わる文章には共通点があることに気付いたという。
「数多くの原稿を目にする中で、優れた文章には共通点があることを発見しました。ひとつは、文章のリズムがいいこと。スラスラ読めるリズミカルな文章に加え、読み手の興味をそそる順番にうまく構成されているから、飽きさせずに一気に読ませてしまうんです」
そして、もうひとつがしっかりと説明が行き届いていること。長年、情報誌を編集し、現在ではグルメライターとしての顔も持つ高田さんが、グルメ記事を書くことを例に説明をしてくれた。
「例えば、カツ丼の説明を書くときに『大きなトンカツが~~』と書いても、読者はイメージをつかめません。でも、『平均80グラムのカツが、このカツ丼にはたっぷり100グラムも~~』と書けば、そのボリューム感は伝わりますよね。形容詞を使うときに、具体的な数字を加えた原稿は上手だなと思います」