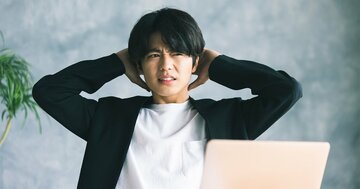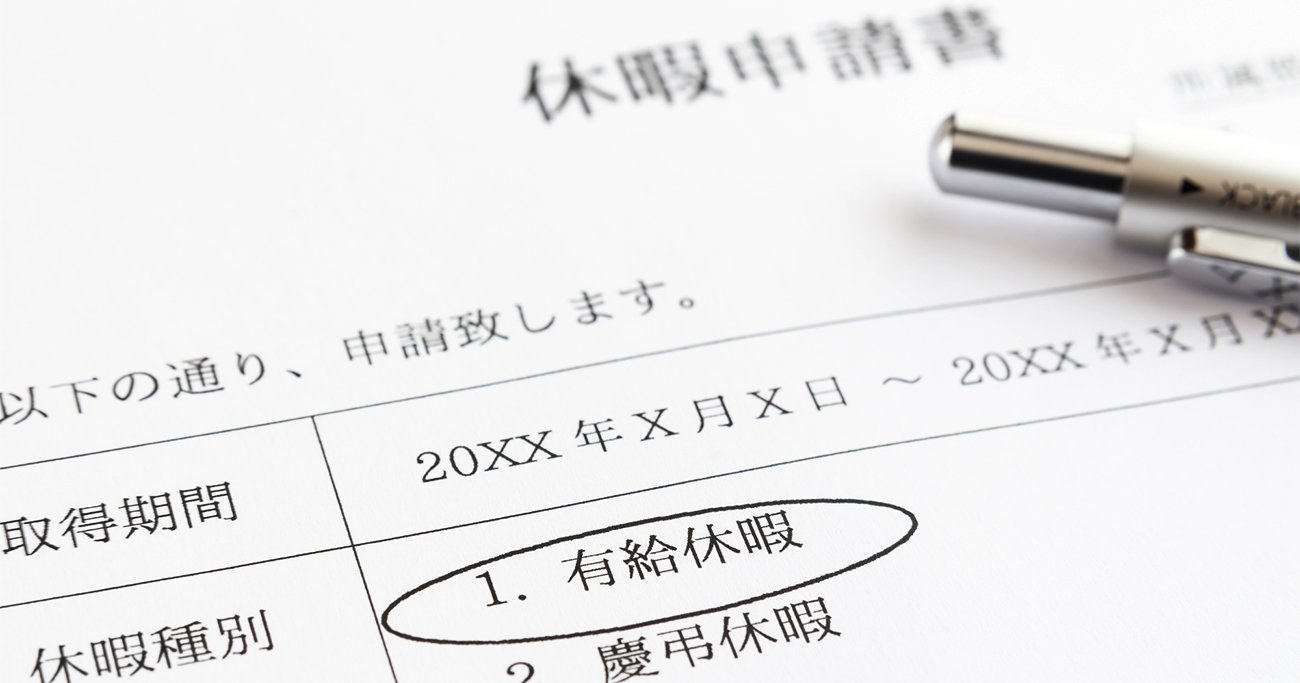 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
会社への貢献が最優先される社会において、過労のサインを自らキャッチすることは難しい。だが、長期的に社会に貢献するためには休むことも大切だ。休まずに働き続けるとどのような健康上のリスクがあるのだろうか。精神科医のパントー氏が、働きすぎによる不安と過剰なストレスに悩むHさんのカウンセリングを通して、日本人の働き方に警鐘を鳴らす。※本稿は、パントー・フランチェスコ『しあわせの処方箋(Tips)~イタリア人精神科医 パントー先生が考える~』(あさ出版)の一部を抜粋・編集したものです。
理由もわからずパニック
突然涙が出てくることも
Hさんは、クリエイティブ業界で働く30代の会社員です。
元々このキャリアを目指しており、仕事に不満もなく、毎朝元気いっぱいで出勤していました。
ですが、1週間前、おばあさまが他界されたときから、調子が悪くなりました。
出勤中、電車でパニックとなり、息が荒くなる。血が頭に上り、周りはまるで現実ではないように見える。
心臓発作なのではないか、脳卒中なのではないかと心配になるほど、症状が激しく次の駅で降りて、駅員さんの助けを求めました。
それが何日も続き、なんとか立ち直って出社できた日もあれば、体調不良で帰宅をせざるを得ないときもありました。
また場所を問わず、突然涙が出てくることもありますが、理由がわからないといいます。
心と体のサインを無視しない
健康なエゴイズムを持とう
会社への貢献が何より最優先されている社会において、過労のサインを自らキャッチするのは難易度が高いことといえます。
「体が悲鳴をあげている」という表現があるくらい、身体的にも相当辛くならない限り、皆さん無理してがんばっていらっしゃるのではないでしょうか。
Hさんが体験したのは、不安と過剰なストレスによる精神的な負担です。
この場合、速やかに休職しないと症状が慢性化してしまい、うつ病、不安障害など、長期にわたる、後遺症を残す障害に進展してもおかしくないと伝えました。
ただ、そこまで説明しても、休みを取るにはためらいがあるようです。
長期的かつさまざまな視点でみても、今、休んだほうが好きな仕事を長く続けられるし、社会に貢献することができると説明しました。
また、「好きな仕事なのに、なぜこんなことになってしまったのか」というのが、Hさんにとっては不可解だったようです。
この場合、電池がたとえとして、わかりやすいのではないかなと思います。
私たちは、電池だとします。
ストレージには限りがあり、それを使い尽くしたら、どれだけがんばりたいと思っても、物理的にエネルギーがないということになります。
実際に私たちは、エネルギーが尽きてしまいそうなときに、常に心と体からサインが出ているはずですが、それを無視してしまいがちです。