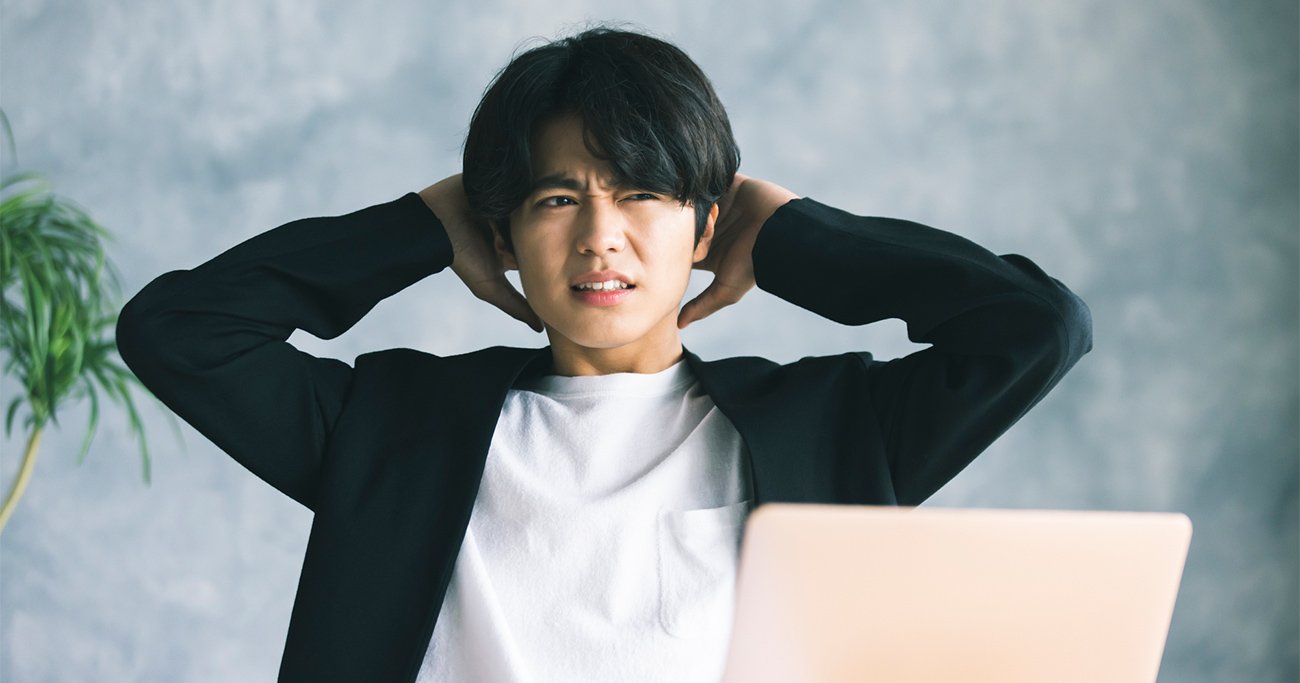 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
日本人はさまざまな場面において感情抑制・抑圧傾向が、かなり強い。だが、この相手の気持ちを慮り「察する」日本人の精神性が心身を蝕んでいる。日本人が抱えがちな苦痛に対してどのように対処すればいいのだろうか。精神科医のパントー氏が「適応障害」と診断したCさんのカウンセリングを通して、日本人の「察する」文化について解説する。※本稿は、パントー・フランチェスコ『しあわせの処方箋(Tips)~イタリア人精神科医 パントー先生が考える~』(あさ出版)の一部を抜粋・編集したものです。
「今、何を感じているの?」
自分の感情を取り戻そう
Cさんは不安が強く、過換気発作と不眠症、意欲低下で受診しました。
最近、上司に叱られたり、結婚相手になじられるのが辛く、日常生活において喜びを感じないといいます。
自分の気持ちが理解されていないと思うけれど、自分の気持ちなんて伝えてもしょうがない、価値なんてないのではとも訴えます。
Cさんは「自分」と「周り」の感情がぶつかり合えば、一触即発の今の状況が、さらに激化してしまうと思っているのではないでしょうか。
そもそも、自身の感情を伝えようとしないのは、「自分には価値がない」「自分が劣っている」という先入観によるものだと思われます。
ただ、その感情の抑制と抑圧こそが、Cさんの辛さに拍車をかけています。
上司に対して無口になるからこそ、叱られる。
結婚相手から見れば、自分に対して無関心というふうに、映っていることでしょう。
まず、Cさんは自分が何者であり、何を感じているかを理解する必要があります。
感情を抑制・抑圧している人は、自分の感情と同律する歯車が「錆びついて」いることも多いため、「お腹が空いた」「疲れた」「眠い」などの簡単なことから、自身との感覚をつなぐ橋を修復してみましょう。
五感を認識するだけで、「自分」と「周り」の区別を取り戻すことができることも多いのです。
感情の抑制と抑圧が
早期の死に関与する
近年メンタルヘルスケアにおいて、感情調節の役割が重要視されるようになっています。
感情調節とは、「自分の目標を達成するために、情動反応、特にその集中的・時間的特徴をモニタリングし、評価し、修正する外発的・内発的プロセス」と定義されています。
要するに、健康的に自分のポジティブな感情・ネガティブな感情と向き合える能力、また、困難な感情に適応的に対処する能力といえます。
感情調節能力には、正しい感情表現能力も含まれます。
自身の感情を調節するには、まず「自分」と「周り」の隔たりを理解しなければなりません。「周り」の感情を誤って「自分」の感情にしてしまうと、いつの間にか居場所をなくす恐れがあるからです。
「自分の感情を知って、取り扱う」ことができないと、「周り」と合わせるために自身の感情を否定、抑制、抑圧してしまいます。
感情抑制とは、他のことを考えたり、物事を我慢したりすることによって、苦痛となる感情を意図的に回避することと定義されます。







