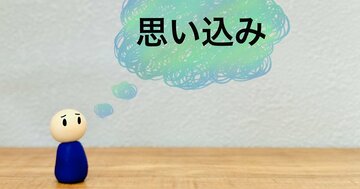大人が地団駄を踏まない理由を
動物行動学から仮説を立てる
では、もう一つの質問:「大人ではなぜ見られなくなるか?」については、どうだろうか?
これについても、動物行動学的に容易に、仮説的答えを返すことができる。
それはこうだ。
脳の中には、怖さや、喜怒哀楽の感情の発生源の主役となる「扁桃体」がある。
たとえば、山を歩いていて、突然、前方に、黒い紐状のものが見えたとしたら、ドキッ! とするのではないだろうか。そのとき起こっていることは、目から入った視覚情報が扁桃体に運ばれることによると考えられる。
扁桃体には「ヘビニューロン」と呼ばれる、ヘビの様々な姿に対応して“ヘビ”を検出する神経配線系が存在し、この活動によって、われわれが「ヘビ」を意識する前に、脳や筋肉系を警戒状態にするのである。それがドキッ! を感じさせるのだ。
ただし、このような状況に出合ったときのわれわれの脳では、目から扁桃体(少し詳しく言えば、目の網膜の視細胞→視神経→視床→扁桃体)という経路のほかにも、目の網膜の視細胞→視神経→視床→大脳→扁桃体という経路も活動する。この経路で情報が扁桃体に到達するまでには、前者の経路の場合に比べ、大脳を経由する分、少し時間がかかる。
後者の経路が前者の経路と異なるのは、目から送られてきた情報が、大脳で、より詳細に、また、それまでに経験した出来事の記憶内容と比較される点である。
山の中の“ヘビ!”の場合、もしそれが、捨てられていた黒いロープだったら、詳細を見れば、また、それまで見たロープの記憶と照らし合わせれば、ヘビではないことが分かり、扁桃体に「ヘビではない。黒いロープだ」との情報が伝えられ、扁桃体の興奮を抑えることになる。そのプロセスは意識にのぼり、黒いロープをヘビだと思いドキッとしたんだ、と自覚することになる。
まずは、危険の可能性がある対象には、「目の網膜の視細胞→視神経→視床→扁桃体」という、素早い経路で、ほんとうに危険なものであった場合に備えて準備態勢をとっておき、少しして、詳しい分析結果を知らせる、という良い戦略だ。