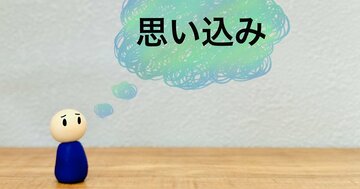このような大脳の働きは、成長とともに発達し、子どもの頃は、扁桃体が、喜怒哀楽などを発生させると、大脳からの制御が弱く、感情の興奮がそのまま拡大し、泣いたり、怒ったり、喜んだりするという行動が現れやすい(ちなみに、大人でも“切れる”という現象が起こるのは、大脳の疲れや不調により、感情の制御が十分に働かなくなって起こるのではないかと推察される)。
子どもの頃、「感情の興奮がそのまま拡大し、泣いたり、怒ったり、喜んだりするという行動が現れやすい」というのは、これまた動物行動学的に、よくできた意味のあることだと私は推察している。というのは、危険への対処能力が十分発達していない子ども期にあっては、泣いたり、怒ったり、喜んだりする、(特に)目立つ行動によって、周囲の個体に助けてもらえる状況をつくっておくことが有利だからと思うからである。
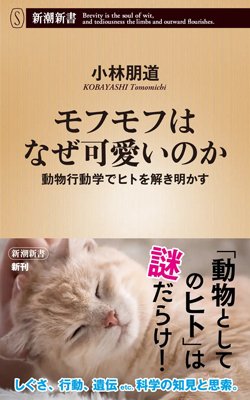 『モフモフはなぜ可愛いのか 動物行動学でヒトを解き明かす』(新潮社)
『モフモフはなぜ可愛いのか 動物行動学でヒトを解き明かす』(新潮社)小林朋道 著
ここまで書けば、地団駄が「大人ではなぜ見られなくなるか?」、お分かりになる読者の方もでてくるのではないだろうか。
そう、地団駄の原因となっている怒りのような感情を大脳が制御するようになるからだ。
なになに? 老化が進んできて大脳の働きが悪くなってきたら、また地団駄を踏むようになるのか?
おそらくその時は扁桃体も老化が進んでいて、それと地団駄を踏めるだけの筋肉もなくなっていて、それはないのでは。
でも地団駄を踏む老人。いたら面白いだろうな。