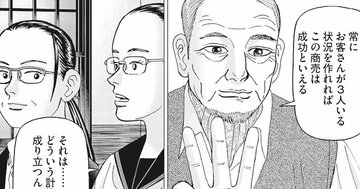『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の投資マンガ『インベスターZ』を題材に、経済コラムニストで元日経新聞編集委員の高井宏章が経済の仕組みをイチから解説する連載コラム「インベスターZで学ぶ経済教室」。第92回は、転職志向が強い若手社員の育成のあり方を考える。
すぐ転職する新人、育てる意味は?
現主将の神代圭介は投資部OBに呼び出され、道塾学園創業家の御曹司・慎司との存続を賭けた三番勝負の経緯と真意の説明を求められる。神代は、投資部の成功の秘訣は毎年新入生を迎える新陳代謝にあり、ワンマン志向の慎司の構想は机上の空論だと断じる。
新入社員という新鮮なメンバーの参加があるからこそ、企業は停滞を免れる。それはその通りなのだが、忙しい日々のなか、「正直、新人教育は面倒」と考える人も少なくないだろう。
最近の若者は転職志向が強く、厚生労働省の調べでは、新卒入社の4分の1は2年以内に離職するという。手をかけても「収穫期」には居なくなってしまうのでは、と思えば指導に身が入らないかもしれない。
私自身は新聞社に勤めていたころ、新人・若手の育成にそれなりにエネルギーを注いでいた。特に40代に入って本社勤めのデスク(編集者)になってからは、現場の記者が一人前になれるよう、出来るかぎりサポートを心掛けた。
一番力を入れていたのは「反省会」。その日の新聞作りが一段落したら記者に電話をかけ、初稿と最終稿を見比べて修正部分にどうして私が手を入れたか説明する。もっと良い記事にするための取材の視点やファクト、データなども検討する。
ひとり15~20分程度かけて、2~3人に指導をしていた。新人数人を書き手に指名して連載企画を何度かやったこともあった。
人員削減と業務負担の増加が加速した時期でもあったので、そんな手間をかけている私はかなりの少数派だった。それでも続けたのは、それが「恩返し」だったからだ。駆け出し記者だった頃、同じようなことを当時のデスクがやってくれたから、自分は記事が書けるようになった。今度は私がバトンを渡す番だった。
育つ奴だけ勝手に育ち、ダメな奴はダメなまま
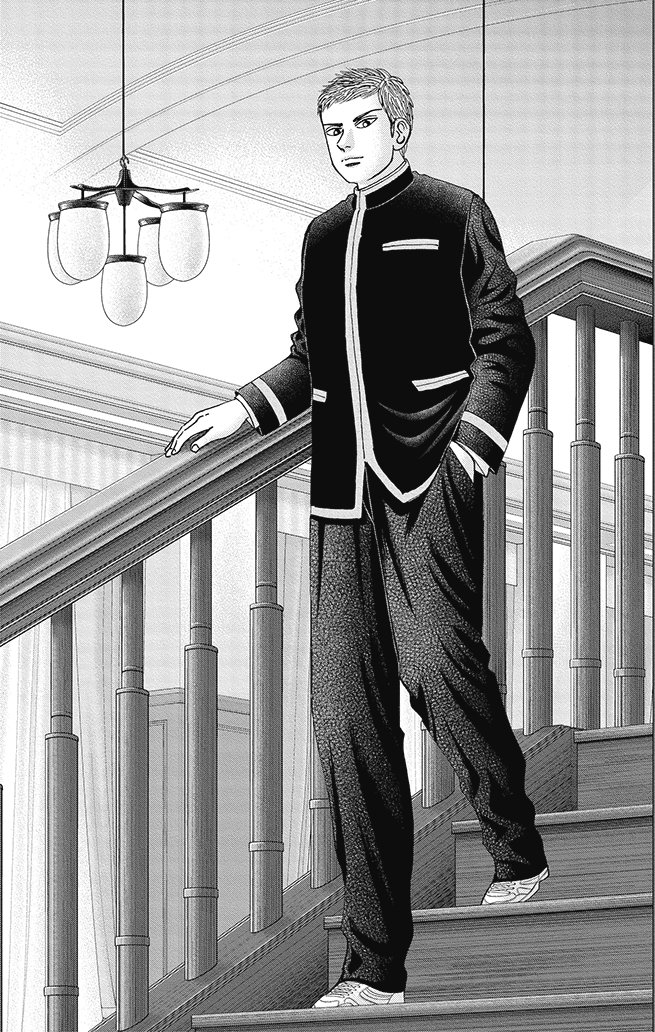 『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
こうした徒弟制度のようなあり方は、今風ではないかもしれない。だが、新聞社に限らず、そうしたバトンタッチが新陳代謝を支える土台なのだと私は信じる。
「上の世代から受けた恩は下の世代に返す」は言い尽くされた言葉ではあるが、ただの綺麗ごとではなくて、そうしないと世の中は回らないのだ。日本全国津々浦々、そんな世代間バトンリレーがいろいろな現場を支えているはずだ。
実際、私の実感としては、そうした社内の流れが滞ってきたな、これが続くと大変なことになるぞ、と危惧し始めて10年ほどたつと、「現場」はかなり荒れてしまった。有体に言えば、育つ奴だけ勝手に育ち、ダメな奴はダメなまま、という傾向が目立つようになった。
新陳代謝の担い手である新人・若手の「歩留まり」が落ちれば組織は停滞する。停滞はやがて後退となり、悪循環が回りだす。そうなってから立て直すのは容易ではない。
神代が指摘するように、新陳代謝を失った組織は「できる人」に依存するしかない。目先はうまく回れば結果オーライかもしれないが、そんな人材もいつかは歳をとり、現場を去っていく。個人の力量と運に頼るのは組織としてリスクが大きい。
「人生は配られたカードで勝負するしかない」。良く知られたスヌーピーの名言だが、これは個人に限った警句であって、手持ちのカードを補充・入れ替えできるのが組織の強みのはずだ。有力なランナーほど転職でチームから抜けてしまう可能性が高いかもしれないが、それでもバトンをつないでいく以外、組織が生き残る道はない。
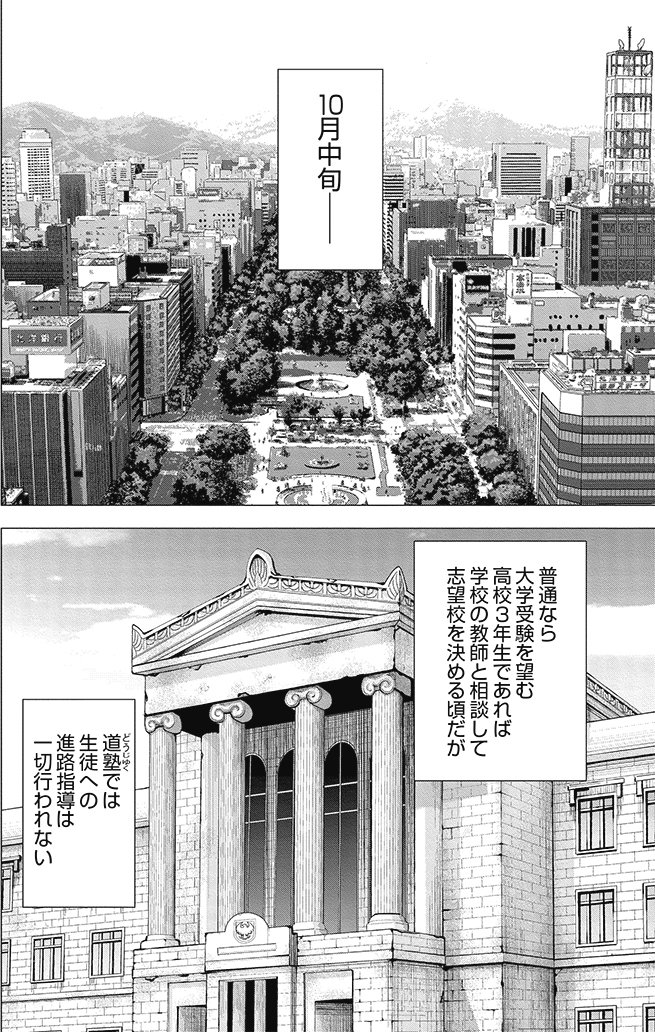 『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
 『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク
『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク